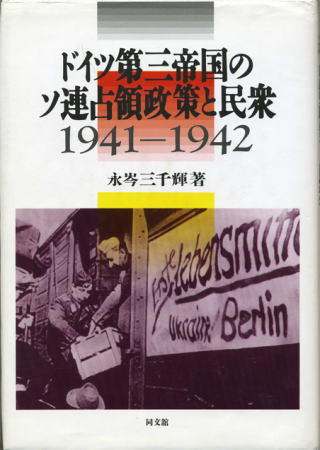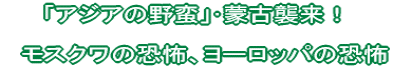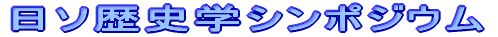
国際歴史学会(現在も世界的学会として開催され、今度はシドニーとのこと)の活動のなかで、分野別・国別部会の活動のひとつとして、日ソの歴史学者が研究会を組織したものだと聞いている。
日ソ歴史学シンポジウムにおいては、大塚史学のなかでは国際的活動の最前線にいた高橋幸八郎教授が中心だった。

(この写真は、1976年ゲッティンゲン大学
における社会経済史学会のとき)
すなわち、故・高橋幸八郎氏は、大塚史学の業績を踏まえて封建制から資本主義体制への移行に関する国際的論争に参加して国際的に有名となった(東大の教授・名誉教授で旧土地制度史学会の会長などを歴任)。そして、日ソ歴史学シンポジウムの日本側オーガナイザーの一人として活躍したと伺っている。
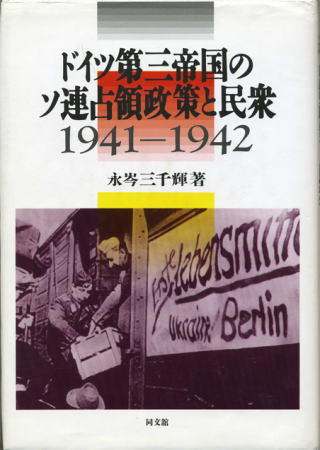
90年ころ、『ドイツ第三帝国のソ連占領政策と民衆 1941−1942』(同文舘、1994年)の元になる論文をいくつか『経済学季報(立正大学)』に発表していたこともあって西川正雄教授(東大教養学部、定年後、専修大学文学部)のご推薦があったようで、日ソ歴史学シンポジウムの当時の日本側代表をなさっていた和田春樹教授(当時、東京大学社会科学研究所の教授)から声をかけていただき、最初、「わたしなどがなぜ」と躊躇したが、お引き受けし、参加した。
40年5月以降の西部戦線における第三帝国の電撃的勝利が、オランダ、ベルギー、フランスの生産キャパシティーを掌中に握ることを可能とし、その迅速な無傷状態の勝利が対ソ攻撃の野望を膨らませたこと、しかし、40年夏の西部戦線での電撃的勝利の前提は39年8月の独ソ不可侵条約であり、したがって、41年の対ソ攻撃の一因(重要原因)は、ソ連みずからが急場しのぎにヒトラー第三帝国と手を結んでしまったことの結果であること、そして、ソ連が急場しのぎに追い込まれる一因(重要原因)が、ノモンハン事件であること、こうしたことを確認する報告を行った。
故・藤原彰一橋大学教授や中村政則一橋大学教授、百瀬宏津田塾大学教授など、わが国の歴史学界の代表的研究者といっしょにシンポジウムに参加でき、いろいろとご教示頂いたことは幸せであった。
百瀬教授とは滞在中、モスクワのホテルが同室だったので、「小国」の存在意義・歴史的意味について、実にたくさんのことを学ばせていただいた。
シンポジウムそれ自体よりも、こうした諸先生との交流の機会を得たことのほうが研究の進展のうえで大きかったようにも思われる。
最初のころの日ソ歴史学シンポジウムは、「国賓待遇なみ」とかで、たいそう優遇されたようであるが、ソ連崩壊直前のシンポジウムはそうした待遇はなかった。
しかし、下にも書くように、第二次大戦の決定的な局面の現場を肌身で感じることができたことは、そして、帰国直後にソ連が崩壊したことは、私のその後の仕事に決定的な(自分にとっては飛躍的な)意味を持った。


会場の科学アカデミーの建物 アカデミーから市内俯瞰


(アカデミー玄関、91-06-05)

1991年6月初旬、日ソ歴史学シンポジウム参加。たしか10回目か11回目のシンポジウムであった。2年−3年おきの開催だったという。
いまでは、直後の8月にソ連が崩壊したので、最後の日ソ歴史学シンポジウムとなった。
チェレメチェボ空港からモスクワ市内中心部へのバスの中から見た (第二次大戦のとき、41年12月にドイツ大軍のモスクワ攻略を労働者・市民が武器とを取って総出で阻止した記念の鉄塔、敗退したドイツ軍の戦車等を鋳直して建立)は、私の歴史観を揺さぶるものであり、巨大な二つの大軍・巨大な二つの国民(連合)の
(第二次大戦のとき、41年12月にドイツ大軍のモスクワ攻略を労働者・市民が武器とを取って総出で阻止した記念の鉄塔、敗退したドイツ軍の戦車等を鋳直して建立)は、私の歴史観を揺さぶるものであり、巨大な二つの大軍・巨大な二つの国民(連合)の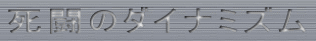 のなかで、20世紀世界史を見ることの必要性を感じ取ったものである。
のなかで、20世紀世界史を見ることの必要性を感じ取ったものである。
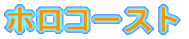 も、巨大な二大国民(連合)の死闘の過程で見ていくとき、本当の姿をとらえ、内在的に理解する(正当化することとは別)ことができる。そのヒントを得たのが、現場体験・現場の実感。
も、巨大な二大国民(連合)の死闘の過程で見ていくとき、本当の姿をとらえ、内在的に理解する(正当化することとは別)ことができる。そのヒントを得たのが、現場体験・現場の実感。
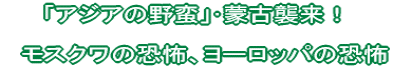
そのもうひとつの衝撃的な場面が、モスクワ近郊ウラジーミル・スーズダリのエクスカーションでの経験であり、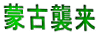 の図であった。
の図であった。
のちに(95年8月)、アウシュヴィッツ見学のさい、足を伸ばしてクラカウ(第三帝国時代、総督府の首都となっていた)にもいったが、そのクラカウもjまた蒙古襲来におびえた町であった。町の中心には、蒙古襲来の危険を知らせた人(蒙古軍に喉を射抜かれたとか)が、警鐘を鳴らした教会があった。

「アジアの野蛮」・「蒙古襲来」の図
ヒトラーは、1939年8月22日、ベルヒテスガーデンのオーバーザルツベルク(そこにある山荘のベルクホーフBerghof)で、ポーランド攻撃を国防軍司令官の将軍たちに説明するなかで、まさにこの「蒙古の野蛮」、「アジアの野蛮」を利用した。ドイツ民族の生存圏の獲得・拡大のためにポーランド人を殺戮する、と。
ヒトラーは、下記の発言が示すように、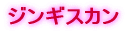 を
を とみなし、自らをそれに比しているのである。
とみなし、自らをそれに比しているのである。
いやジンギスカン以上の英雄との自負があったのであろう。
「我々の強さはスピードと野蛮性にある。ジンギスカンはたくさんの婦女子を、死に追いやった、わざと、いや、たのしみながら。
歴史はジンギスカンを国という物の偉大な創造者とみなしている。
私について西欧文明がどれほど軟弱なことを言おうと、そんなことは問題ではない。私は命令を発した。だれでも批判がましいことを一言でももらそうものなら、射殺する。
戦争の目的は明確な国境線をひくことにあるのではない。むしろ敵を肉体的に殲滅することにあるのだ。
そこで、わたしのどくろ部隊を召集した。当面は東部においてだけだが。ポーランド人、ポーランド語の男女子供を、徹底的に無慈悲に、死に追いやる命令を与えた。これこそ、我々が必要とする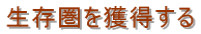 ゆいいつの道だ。・・・・ポーランドの住民を根絶し、ドイツ人が入植しなければならない。」
ゆいいつの道だ。・・・・ポーランドの住民を根絶し、ドイツ人が入植しなければならない。」
(Danuta Czech, Auschwitz Chronicle 1939-1945. From the Archives of the Auschwitz Memorial and the German Fereral Archives, foreword by Walter Laquer, New York 1990, p..1)
人類の世界史において、ヒトラーは、ジンギスカン以上に有名であり続ける可能性はある。
ヒトラーが、「極端の世紀」、20世紀のひとつの「巨人」、(陸の 怪獣)の親玉であることはたしかである。
怪獣)の親玉であることはたしかである。
なぜ、世界はヒトラーを「巨人」、「世界史的英雄」に仕立て上げたのか?
19世紀末ー20世紀の世界の帝国主義列強の全動向を把握する必要があろう。
ちなみに、ヒトラーを頂点とする第三帝国の国家機構・国民大衆の総体をひとつの と見る見方は、ノイマンの『ビヒモス』’邦訳あり)で有名だが、そうした見方(巨大な怪物を想像すること、海怪獣リバイアサンとの対比)は、ビヒモスの言葉そのものが旧約聖書からでていることを見てもわかるように、古代の聖書の世界からあったことであった。
と見る見方は、ノイマンの『ビヒモス』’邦訳あり)で有名だが、そうした見方(巨大な怪物を想像すること、海怪獣リバイアサンとの対比)は、ビヒモスの言葉そのものが旧約聖書からでていることを見てもわかるように、古代の聖書の世界からあったことであった。
ヒトラーと同時代でいえば、チャーチルも『第二次世界大戦』(ノーベル賞受賞作、邦訳・文庫本あり)のなかで、同じような比喩をしている。
(スターリンが第二戦線を開くように求める時、巨大な怪獣の比喩を揚げながら、ドーバー海峡からの進攻の不可能性を強調する文脈で、第三帝国ドイツを、ドーバー海峡いったいを堅い幾重もの甲羅で防御した巨大な怪獣になぞらえて)
日本が世界史と接触する上でも、大きな画期・巨大な経験となるのが、 であることはいうまでもない。
であることはいうまでもない。
----シンポジウム関連写真及びエクスカーションの写真-----


(ウラジミール・スーズダリに向かう途中の農村、91年6月7日) (エクスカーションで泊まった部屋)



(91年6月8日エクスカーション寺院見学、途中休憩・散策)








ポクロフスキー寺院(教会)


教会内部の牢獄

(雪のように舞う花粉、道端にかたまる)



91年6月9日



(赤の広場)


(モスクワ地下鉄)
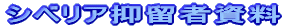
91年6月10日


(ソ連邦文書館)


(日本人シベリア抑留者・資料)


軍事史研究所