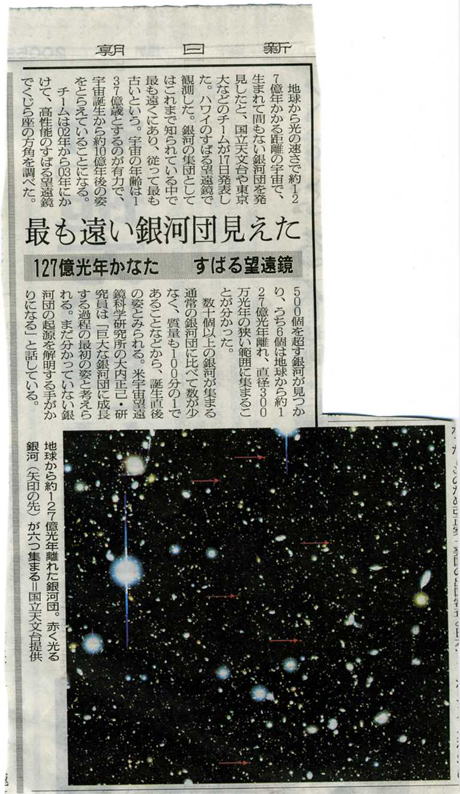�o�ώj�u�`����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@No.2�@File: kogikeizaishi423:
�ŏI�X�V���F2008�N6��19��(��)
�S�̎j�E���̎j(�F��[1]�̋�ԂƎ��ԁA���m�ɂ͎���̗Z������)�̒��ł��l�ގj�E�Љ�j���o�ώj�̈ʒu�t�� [2]�\����1�\
|
4-1�@���@ �� �@�� �@�x �@�o�i�����j |
|||
|
GROSS DOMESTIC
EXPENDITURE (Cont'd) |
|||
|
|
|
|
|
|
4-1A�\�����Q�ƁB |
|
||
|
See headnote,
Table 4-1A. |
|||
|
|
|
|
|
|
B�@���@�@���i���a55�N--����11�N�C���a55�N�x--����11�N�x�j |
|||
|
AT CONSTANT
PRICES (1980--99, F.Y. 1980--99) |
|||
|
|
|
|
|
|
�i�P�ʁ@10���~�j�i����7��N��j |
|||
|
(At market
prices in calendar year 1995)(In billions of yen) |
|||
|
�N�@�@�� |
Year |
���ԍŏI����x�o |
���{�ŏI����x�o |
|
|
�@ |
Private final
consumption expenditure
(A) |
Government final
consumption expenditure
(B) |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
�@ |
��@�@�@�N�@�@�@�@�@Calendar year |
�@ |
|
���a55�N |
1980 |
174,289 |
44,896 |
|
56 |
1981 |
175,724 |
47,484 |
|
57 |
1982 |
183,021 |
49,775 |
|
58 |
1983 |
188,256 |
52,109 |
|
59 |
1984 |
192,860 |
53,790 |
|
60 |
1985 |
200,096 |
53,822 |
|
61 |
1986 |
206,582 |
56,385 |
|
62 |
1987 |
215,068 |
58,354 |
|
63 |
1988 |
226,077 |
60,343 |
|
�������N |
1989 |
236,707 |
62,078 |
|
2 |
1990 |
247,223 |
63,629 |
|
3 |
1991 |
253,878 |
65,678 |
|
4 |
1992 |
260,391 |
67,446 |
|
5 |
1993 |
265,029 |
69,602 |
|
6 |
1994 |
271,791 |
71,591 |
|
7 |
1995 |
275,627 |
74,647 |
|
8 |
1996 |
282,180 |
76,763 |
|
9 |
1997 |
284,313 |
77,784 |
|
10 |
1998 |
284,475 |
79,285 |
|
11 |
1999 |
287,988 |
82,423 |
�Q�D�F���j[9]�E�E�E����F���Ȋw�̓��B�_�E�E�E���݂̉Ȋw�I����i�ɂ���Ċm�F�ł���F���̐��a���Ȋw�I�Ɋm�F�ł��錻�݂̉F���̒a���E�E�E�r�b�O�o���B
�����r�b�O�o�����A������100���\150���N�O�i�e��f�[�^�ɂ��o���c�L�A�ŋ߂ł�150���N�Ƃ���̂������悤��[10]�j�B���̔N��́A���̐ԕ��Έڂɂ�鋗���m�F�Ȃǂ�[11]�B
100�����N���邢�͕S���\�����N�ȏ㉓������̌��̃L���b�`(�ŐV�V���j���[�X)�B
���{�����E�I�Ȋw�I�v���Ƃ��ẲF���]���������̉f���B
�����̉F����100���N����150���N���N�����B��ԓI�L����́A�����ŁA150�����N�̍L�傳���B
�Ƃ�������̑O�́H
�r�b�O�o���̎��̑傫���́H
���㉽�S���N�������̉F���́A�`��ς��A���ł���̂��H�@
�����S���N�����ƁA�r�b�O�o���̂Ƃ��̂悤�ȉ�ɁA���Ȃ킿�A����ȉ��̋ʂɎ��k����̂��H
�����čĂуr�b�O�o�����J��Ԃ��̂��H�@
���邢�͕ʂ̃V�i���I���H�@
����F���_�E�f���q�F���_�̒���ۑ�I[12]
���̉𖾂́A���{�Ɛ��E�̌�����Ȋw�I�F���_�̍Ő�[���s���l�тƂɊ��҂��悤[13]�B
�r�b�O�o���Ɋւ���13�N�قǑO(1989�N��)�̃z�[�L���O�̐����F
�u1929�N�ɃG�h�E�B���E�n�b�u�����A�ǂ���̕��������Ă��A�����̋�͂͂���ꂩ��}���ɉ��������Ă����Ƃ�������I�Ȋϑ����s����[14]�B����������A�F���͖c���������̂��B����͏����ɂ͓V�̂��т�����l�܂��Ă������Ƃ��Ӗ�����B�����A100���Ȃ���200���N�O�ɂ͂��ׂĂ̓V�̂��܂����������ꏊ�ɏW�܂�A�����������F���̖��x�͖����傾�����������������悤�Ɍ�����̂ł���B���̔����ɂ���ĉF���̎n�܂�̖��́A���ɉȊw�̗̈�Ɏ������܂ꂽ�̂������B�n�b�u���̊ϑ��́A�F���������ɏ������A�����ɔZ���������r�b�O�o���ƌĂ�鎞�_�����������Ƃ����������B[15]�v
�u�w�����P���Ă��錻�݂̉F���̎p�ȂǂƂ����̂́A�����Ė����ɒ�����������̂ł͂Ȃ��B�x���������F���Ɋm�M�����Ă�悤�ɂȂ����̂͂������Đ̂̂��Ƃł͂Ȃ��B�M�ҁi���������E�E�E���p�Ғ��j���A1960�N�ɑ�w�𑲋Ƃ��ĉF�������w�̌��������ׂ���w�@�ɓ��������ɂ́A�܂����Ȃ��Ƃ����炩�ł͂Ȃ������B���ꂩ��5�N�قǂ���1965�N���F�����̕��˂̔���������A�������K���t�̃r�b�O�o���F���̍l�����������ƍl������悤�ɂȂ����B�E�E�E1970�N��O���ł��f���q�����w���傫���O�i�����B�����Ă��̑O�i�ƌ��т��������Ńr�b�O�o���F���_�͂�����i�傫����邱�ƂɂȂ����̂ł���B[16]�v
�u�������̉F���́A���悻150���N�ȑO���r�b�O�o���Œa�����A����ȗ��c���𑱂��Ă���B�c���ɔ����F���̖��x�Ɖ��x�̒ቺ�ɔ����ĕ����͂��̑��`�Ԃ�ς��Ă����̂ł���A���̈Ӗ��Ō��݈�ʂɎ�����Ă����c���F���_���i���F���_�Ƃ������B���K�w�̓V�̂��A���邢�͓V�̂��\�����镨���i���f�j���A�r�b�O�o���ȗ����悻150���N���F���̐i���ɂ���č������݂��Ă���̂ł���B
�@���z�n�̓V�͖̂�46���N�ȑO�Ɍ`�����ꂽ�ƍl�����Ă��邪�A��ɏq�ׂ����Ƃ����l����A�`�����旧���悻100���N���F���̗��j��w�����Ēa�����A���݂Ɏ����Ă���Ƃ������Ƃ��ł���B[18]�v
�K���t�̃r�b�O�o���F���Ɠ��{�̌���F���_�����̑������E�ђ��l�Y[19]
�������������⍲�����F�����A�r����[20]�����Ȃǂ̓��{�̌���F���_�̌����҂���Ă��̂��A�ђ��l�Y���s��w���_�����B
���̗ю��́A���{�ŏ��̃m�[�x���܊w�ҁE����G���̂��Ƃɑ�2�����E����܂��Ȃ�46�N4���A����i�������A1�N���������j�Ƃ��č̗p���ꂽ�B�����āA���삩��u�V�̂̌��q�j����������������ǂ����v�Ƒ����ꂽ�Ƃ����B
�@���ꂩ��Ԃ��Ȃ�48�N�B�č��̕����w�҃W���[�W�E�K���t���F���͒������E�������x�̏�Ԃ��甚���I�Ȗc�����͂��߂��Ƃ���u�r�b�O�o���F���_�v��B
�@�����K���t���_�Ɗi�������̂��A�ђ��l�Y���B
�@
�K���t�́A�����̉F���ɂ͒����q���������Ȃ��A�F���c���ɂ�鉷�x�ቺ�Œ����q���z�q�ɕ��A���̗z�q�ƒ����q�̊j�Z���ŁA���̌�̓V�̂��\�����邷�ׂĂ̌��f���������ꂽ�Ǝ咣�B
�@���̃K���t�̎咣�́u�тɂƂ��Ă��D�ɗ����Ȃ��B�v�u�F���̏����͒����q����ł���͂����Ȃ��v�ƁB
�@�т͑f���q�_�Ɠ��v�͊w�̎�@����g���āA�F�������̗z�q�ƒ����q�̑��ݗʂ��v�Z�ɒ����B�܂���Z��㔼�������B
�@�u��l�Ŕ��N�ԁA�W�����Ă�����v���ʂ��܁Z�N�ɘ_���Ƃ��Ă܂Ƃ߂�B�F�������܂�Ă�������̉��x�͐��S���x�i��̃��C���o�[�O�̌����ł�1000���x�j�ŁA�u�����q����z�q�v�A�u�z�q���璆���q�v�Ɠ]�����锽�����������N���A�z�q�ƒ����q�́A�قړ������݂��Ă���C�Ƃ������e�������B�c���ɂƂ��Ȃ��ĉF���̉��x���������Ă���ƁA�z�q�̐��������q���������Ȃ�B�c���J�n100�b��ɂ́A���x��10���x�قǂɉ������āA�z�q�̐��͒����q��4�{���x�ɑ����A�z�q�ƒ����q�̌����Ńw���E�����q�j�̍������n�܂����A�Ƃ̉����B
�@�u���\��A�}���ɉF���_�̕W�����_�Ɉ���Ă����r�b�O�o�����_���A���{�̎Ⴋ�����҂��⋭�����̂��v[21]�B
�r�D���C���o�[�O�ɂ��A�u�������Ƃ��A�����ɋ�����������͕̂ς�邱�Ƃ̂Ȃ��F���ł���v���A���̂悤�ȁu�s�ς��͂܂������ˋ�̂��̂ł���v�B19���I������20���I�ɂ�����ϑ��̗��j�����������Ƃ́A�u�F���ɂ����Ă͋�́i���_�Ƃ��M�����N�V�[�Ƃ��Ă��j�ƌĂ��P���W�c�̓��X���A�����x�ɂ��߂��悤�ȑ��x�ł��݂��ɉ��������Ă����v�Ƃ������Ƃł���A�u�F���������������̏�Ԃɂ������Ƃ𖾂��ɂ��Ă���v�B�u��������݂̔����I�c�����ߋ��Ɍ������Ă����̂ڂ�ƁA�ߋ��ɂ͂��ׂĂ̋�͂͌��݂��������ƌ݂��ɐڋ߂��Ă���A��͂�͂������̂��ƁA���q�⌴�q�j���������ꂼ��ʁX�ɂ͑��݂����Ȃ������ق����������ł��������Ƃ��킩��B���ꂪ�g�����̉F���h�ƌĂ�鎞��v�ł���[22]�B
����1979�N�m�[�x�������w�܂����C���o�[�O�ɂ��w�F���n���͂��߂�3�����x�_�C�������h�ЁA�i�V�Łj1995�N�́A�u�F���t�˔w�i��y�����f�̑��ݗʂɂ��Ă̍ŋ߂̊ϑ����ʂƑf���q�����w�̒m������g���āA�J蓂��Ă܂��Ȃ��F����{�i�I�ɕ��͂��𖾂����A�͂��߂Ă̈�ʏ��v�Ƃ����B�u�F���������I�ɊJ蓂��Ă���100����1�b�ŁA�t�˂̒��ɓd�q�Ɨz�d�q�Ƃ킸���ȗz�q�A�����q���Ƃ��Ă���1000���x�̔M���F���X�[�v���A�c���ɂ�ċ}���ɗ₦�Ă䂫�A����10���x�ŁA��������ꂪ���Ă��镨�����`���Ƃ�͂��߂��Ƃ���܂ł̖�3���ԁv��`��[23]�B
���炵���_�C�i�~�b�N�ł͂Ȃ����I�I
�@
����s���u���̒��ŕ����Ȋw�ȉF���q���������E�I��א鋳�������z�n�������ы��낤�Ƃ���Ō�̏u�Ԃ̉F���T���q������̎ʐ^�i��������ɂ����G�j���Љ�Ă����B���̉�ʂ̒��S���ɂ����n���iYou�@are�@here�Ə�����Ēn����������Ă����j�͂������ɐ�����߂ď����ȓV�̂Ƃ��āA�����̐��̂Ȃ��ɂ������Ɍ����邾���ł������B��������Ȃ��f���E�n�������ɁA�����Ȃ�Ȃ�ق�,�������邱�Ƃ͍���ł���B�V���b�L���O�ȁA�܂��F���D�n�����Ƃ����C���[�W���Ă��t������悤�Ȉ�ۓI�Ȏʐ^�i�G�j�ł������B
�R�D��͎j�F�����̋���̗��j
�@��F���̑S�̂��炷��A�����ۂ��Ȃ����ۂ��������̋�́B
1���N�قǂň���]�����Ă���Q�����^��́i�t�L�F2005�N5���A�wNEWTON�x�A�C���V���^�C�����ΐ����_����100�N�L�O�̓��W�������Ă�����A�����̋�͂̉�]��2���N�Ɉ�����Ƃ������B�Ȋw�̐������́A�������Ɨ��_�̑o������i�W���Ă���̂��낤���A����ɂ��Ă��A��͂̉�]�����Ɋւ��ẮA���̐��N�ԂɐV���Ȕ��W���������悤�ŁA���ł����]2���N�Ƃ����̂��ŐV�̏��ł����j�B
�����̑��z�n�E�n���͂��̓V�̐��͂ƂƂ��ɐ��a���獡���܂�46��ق�,��F������]���Ă���̂��B�@
���̋�͂̂��̂܂��[�����̕��ɂ������z�n(���z�Ƃ��̘f��)�̗��j[32]
���̂Ȃ����n���j[33]�E�E�E��46���N[34]�A
�L���ǂ܂�Ă���C����j�̌[�֏��ɂ��A
�n���A���Ȃ킿�u���z�n��O�f���B���a1��2000�L�����[�g���̒n���́A�{������Ȃɓ��ʂȐ��Ƃ��Đ��܂ꂽ�̂ł͂Ȃ��B
����̑��z�n�`���_�ɂ��A�n����46���N�O�ɁA���n�̑��z����芪���_�X�g�ƃK�X�̉~�Ղ̒��ŁA���܂ꂽ�B�ƂȂ�ǂ����̋�����ΐ��Ɠ����悤�ɁA�_�X�g���W�܂萬�����Ęf���ƂȂ����̂ł���B���z�ɔ�r�I�߂������̂ŃK�X�����͏��Ȃ��A�����̘̂f���ɂȂ������A����������A�ΐ��Ɠ��l���B�����ɂ�����Ȃɂ������͂Ȃ��B�E�E�E�@
�͂��ߔM�������f�����₦�͂��߂āA�������������Ă����B���z���牓���A��⏬�����ΐ��ł́A��C�������A�܂��c�������͓����Ă������B���z�ɋ߂������ł́A���n�̂Ԍ�����C�����܂�ω������Ɏc��A�������ʂŕ\�ʂ͍����ɕۂ��ꂽ�B���Ԃ̒n���ł́A��C���̐����C�����x�̒ቺ�ɂ�Đ��ƂȂ��ĕ\�ʂ��������A���ꂪ�傫�ȕω��������炵���Ƃ����Ă���B�C����_���Y�f��n�����A����������A�₪�Ă͋�C�̑g���܂ő傫���ς��錴����������̂�����B[35]�v�@
�S�D�n���j�iErdgeschichte)�̒��ł̊C�Ɛ����Ƒ嗤�̗��j�E�E�E�n���w�Ȃǖ��@�I���R�̏��Ȋw�A
�C���痤�ւ̐����̏㗤
�O�q�̌[�֏��ŊC���͌����B
�u�ς����Ƃ����A�n������ԑ傫���ς����̂́A�������Ƃ����Ă��悢���낤�B
�@�n�������܂�Đ����N����10���N�ȓ��Ƃ������������ɐ��܂ꂽ�����́A���i���j���Ȃǂ����n�I�ȒP�זE�����Ƃ��đ唭�W�����B����͌���̐����i�^�j�����j�̂悤�ȍזE�j���������A�זE���̋@�\�������\���łȂ����j�������������A���z�G�l���M�[���z���āA��_���Y�f�Ɛ������Y���������_�f���������B�܂�A���������B�����ނ̌������͑S�n���I�ɍL����A20���N�ȏ��ɂ��킽���đ����������A�n����C�̎听�����߂Ă�����_���Y�f�͂قƂ�ǂȂ��Ȃ��Ă��܂��A�����ɂ���܂łȂ������_�f����ʂ��������B���ꂾ���łȂ��A�Y�f�͐ΊD���Ζ��ȂǂɂƂ肱�܂�Ēn���ɂ�����A�C���ɂƂ��Ă�����ʂ̓S���_�f�ƌ��т��Ē��a����ȂǁA���̊Ԃ���K�͂ȁu�n�������v���i�̂ł���B�E�E�E
�@�����́A�V�����I����f�{���I�i��l���N�O�j�ɂ́A����܂ł͐Ԓ������r�n�ɂ����Ȃ��������n�ɏ㗤���J�n���A�܂������܂ɑS���n��ł��߂����Ă��܂����B
�@�C�͑������琶�܂�āA���̌�40���N�ɂ킽��A�傫�ȕω��������ɒn���̑啔�����������Â����B���j������20���N����25���N�A����ɂÂ��^�j�P�זE������10���N�A�C�͐��������₩�ɐi�������Ă����B���̌�A�J���u���A�I������Ɏn�܂������̔����I�i���\���זE��������O�t���A���ނƐA���Aঁi�́j���ށA�M���ށA�����Đl�ނւƑ����\�́A���̈��肵���C�ł������ƈ�Ă�ꂽ����̂������Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B[36]�v
�T�D�����j�E�E�E�����w�Ȃ�
�E ���ׂĂ̐������������A�������Ă������ł���P�ʂƂ��Ă̗L�@�I�זE�F�@
�E �u�����A���̐��B�@�\�v�u�ԕ������E�����̐���@�\�v�Ȃnj����`�w�����̍Ő�[�̏��_�Ԍ���ɂ́A���Ƃ��ACf �A���זE��`�w������HP�����T�v�@in:�@.�A���זE��`�w������HP
�T�|�P�A�A���j[40]�E�E�E�A���̔��B�j�A�n���}�̌����̐i���E�E�E�E���̍Ő�[���_�Ԍ���ɂ́ACf.��`�i���wHP�A����т��̂Ȃ��̈�ʌ����u�R���M�̂͂Ȃ��v�A�C�l�̌n���}�A���n�Q�m������Q�m������ѐ��F�̂��i���̐����Ȃǂ��ʔ����B
�T�|�Q�A�����j�E�E�E�����ɋ��ʂ��鏔���o�A�]�̌`���A�]�̔��B�A�]�_�o�Ȃǂ̎��R�Ȋw�I�����̍Ő�[���_�Ԍ���ɂ́ACf.�_�o�s���w������HP�@
�@�@�@�@�@�@�@�@��HP�ɂ��A�u�`���E�ɐF�o�����邱�Ƃ��Ȋw�I�ɏؖ����ꂽ�̂́A�����ŋ߂̂��ƂȂ̂ł��B�A�Q�n�͊w�K�����F�𑼂̐F���猩�����A����ɓ������邳�̊D�F������������邱�Ƃ��ł��܂����B�Ɩ��̐F��������Ă��A�������͓̂����F�Ɍ����Ă��邱�Ƃ�����܂����B�v�Ƃ����B�F�o�̓`���E�̂悤�ȍ����ɂ����Ă����݂���Ƃ���A�����l�Ԃ̐F�o�Ƃ��̊�b�ɂȂ��̍\���������i���̋C�̉����Ȃ�悤�Ȓ����Ԃ̒��Ŕ��B���Ă����Ƃ������Ƃ��낤�B
�E ��`�q�����́A�܂��Ɂu��`�v�̌��t���[�I�Ɏ����悤�ɁA���R�E�i�l�Ԃ����̂�����ł͎��R�̈ꕔ�j�̏����ۂ̗��j�����̈ꕔ�ł���A���R�̑��l�ȗ��j�I���W�̓��B�_�̕��q�\������ׂɉȊw�I�ɕ��͉𖾂��Ă���B
�E ���ٓI�Ȏ��R�����̍����I���B�_�́A�{�w�̎��R�Ȋw�n�̐�������HP�̊e���Ɍ����������B���Ƃ��A�ߌ��V�L�����p�X�́u���̒����q�V�X�e���Ȋw�v�̐����ɂ��A�u�������ۂɊւ��^���p�N������`����~����DNA�Ȃǂ̍\���Ƌ@�\�ƁA�����̑��ݍ�p�Ȃǂ̉𖾁v�ƂȂ��Ă���B
�E �u���̌����ɂ͐�ΓI���݂�����B�n���Ɋւ��ẮA���܂��܂ȔN�㑪��̕��@�������āA���Ƃ͂܂������Ɨ��ɔN��̎ړx���^�����Ă���B���������āA�����ЂƂł��o��ƁA���̒n������ɂ��̉��ɑΉ����鐶���������Ƃ������������炩�ƂȂ�B�������ߋ�����ɂ��킽���āA�����̑����̎��オ�������B�����āA���ł̎��オ�������Ƃ������Ƃ́A�����i�����l���邤���Ŕ��ɏd�v�Ȏ����ł��邪�A����ׂ�ɂ͉���p����ȊO�Ɍ����̎藧�Ă͂Ȃ��B
�E �@����ɑ��āA�����̐����̈�`�q����ߋ��̐i���ׂ���@�ɂ́A���ɂ�錤���ɂ͂Ȃ���ʐ�������B�����^���Ă������́A�����i���j�̌`�Ƃ�������ꂽ���̂ł���B������W���̑傫���A���̗e�ρA��ʂ̊p�x�Ȃǒ�ʓI�ȑ���͉\�����A�����͐�����̐i���I�Ȉʒu�Â��ɔ�Ⴗ��悤�ȗʂł͂Ȃ��B�������A��`�q�̂c�m�`����z��̂������i���邢�͂��ꂩ��v�Z�����ʁj�́A2�̐�����̐i���I�Ȉʒu�Â��ƒ������Ă���B
�E �@����^���p�N���i���Ƃ��w���O���r���j�̃A�~�m�_�z����A2�̈Ⴄ������Ŕ�r���Ă݂�B��������ƁA�����@�\�̃^���p�N���Ȃ̂����A�A�~�m�_�z�قȂ��Ă���B�������A��r���鐶����̑g�ݍ��킹�ɂ���āA�ǂ̂��炢�̊����̃A�~�m�_���قȂ��Ă��邩���������Ă���B�q�g�ƒ��̃w���O���r���ł�25�p�[�Z���g�̃A�~�m�_���قȂ��Ă���̂ɑ��āA�q�g�Ƌ��ł͖�50�p�[�Z���g�̃A�~�m�_���������Ă���B
�E �@�������������A������2�̐����킪�i����ŕ������Ƃ���������̏��ƁA�g�ݍ��킹�Ă݂�B�܂�A2�̐����킪�������̔N���ɑ��āA����2�̐�����̃^���p�N���̃A�~�m�_�z��̒u����������ׂĂ݂�ƁA���҂������W�ɂ��邱�Ƃ��킩��B�^���p�N���̃A�~�m�_�z��̒u�������A����Ύ��v�Ƃ��Ďg����Ƃ������Ƃ��킩��B�w���O���r���̏ꍇ�́A�A�~�m�_�z��100������ɂЂƂ̒u����������̂ɁA���悻600���N�̊������K�v���Ƃ������ʂ������Ă���B
�E �@����������͂����Ă����ƁA�܂�����N�オ�m���Ă��Ȃ�������ɂ��Ă��A�w���O���r���̃A�~�m�_�z��ׂ邾���ŁA���łɐi���I�ʒu�Â����͂����肵�Ă��鐶����Ƃ̈ʒu�W���A��ʓI�ɋ��߂邱�Ƃ��ł���B����͉���I�Ȃ��ƂŁA���ʑc��̉�������ɓ����Ă��Ȃ��Ă��A2�̐����킪�ǂ̂��炢�߉��ł��邩�Ƃ������Ƃ��ʓI�ɕ]�����邱�Ƃ��ł���̂ł���B[41]�v
�M���ނ̒�����
��{�\�I�ȑ��ʂ䂷�飂ɂ��������������邵���Ȃ��B
�{�\�͉���������̂��H
�H�~�́H�E�E�E�E�̂̐����ێ��E���Ȃ̐����̐��Y�E�Đ��Y
���~�́H�E�E�E�E�ނ̐����̈ێ��E�q���̐��Y�E�Đ��Y
�@�{�\�I�Ǝv����l�Ԃ̗~�]���A���j�I�`�����ł���B
�Ƃ���Ή\�Ȃ��Ƃ́A�����{�\�̏��������𖾂��A����������ƉȊw�̗͂œ��䂷�����Ƃ������肦�Ȃ��B
�{�\�̓������A�×�����̐��E�e�n�̗ϗ��A�@���A�����Ȃǂ̉ۑ�ł���g���ł��������A���̎�@�E�d���̈Ⴂ�����@���A���ϗ��A�������̂������ƂȂ��Ă���[58]�B����́A��������Ȋw�̐��ʂ̌��W�ɂ���Ă����Ȃ��ׂ����Ƃ������Ƃ��낤�B
�������������l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
���㐢�E�̏����A���Ƃ��p���X�`�i���A�C�X���G���ƃp���X�`�i�̖��́A�P���Ȣ�{�\��̖�肩�H
�l�ނ́A�l�ގj�̌��ʂƂ��Ċl�������Ȋw�Z�p���\���Ɏg�����Ȃ������̐l�ԓI�\�͂��J�����Ă��Ȃ��A�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��̂��H
�@�l�Ԃ͉Ȋw��i���������B�l�Ԃ͂��̉Ȋw�̍ō��̔��W��l�Ԃ����܂��܂̖ړI�Ɏg�p����B
�@���̍ہA�_�C�i�}�C�g�̂悤�ɓy�؍H���Ȃ��J���E���Y���v���X�̖ړI�̂��߂Ɏg�p�������̂��A�����ɁA���̓����Ȋw�Z�p�I���\�ɂ���āA�l�ԎЉ�E���Y�����j��������B�ǂ���̖ړI�Ɏg�p���邩�́A�l�Ԃ����A�Љ�̍l�����A���l�ԃO���[�v(�����ƁE���ƘA��)�̐���ɂ��B
�@�Ȋw�I�^���ƉȊw�̗́A����͐l�Ԃ̗͂ł���A�l�Ԃ����̎��Ă�͂��ǂ̂悤�Ɋ��p���邩�A����͐l�Ԏ���ł���B
�@
�l�ԁE�l�ނ́A���ݎ����Ă��鎩�������̗́��Ȋw�̗͂̎g�p���@�A�p�r�����߂�B
�@�_�C�i�}�C�g�́A�����ɁA����ł͐��Y�̂��߂ɁA�l�Ԑ����̌���ׂ̈ɗ��p����A�����ł́A�G����l�ԎЉ�E�G����R���͂̔j��̂��߂ɂ����p���ꂽ�B
���q�͂̌����Ƃ��Ă̗��p���A�O��͓G�ΓI�Ȑ��E�������āA�푈�����Ă���Ƃ��������������āA�G��r�ł��邽���ɍs��ꂽ�B
�@�l�ލō��̉Ȋw�I�B���ł��錴�q�Ȋw�A���q�͂̉Ȋw�I�𖾂��A�R����i�Ƃ��Ă̌����J���ɐU��������̂́A����E���Ƃ����G���O��ƂȂĂ����B
�u�Ȋw�̐i���͍��⌴�q�̐��E���𖾂��A���̍ŏ��̏ؖ������e�ł������͕̂s�K[59]�v�ł������B
�s�K�Ȑ��E���A�Ȋw�̗p�r�����߂��B
�@���E�����a�ɂȂ����i�K�ł́A�����I�ɂ́A���q�͂̓G�l���M�[���Ƃ��āA���p���ꂽ�B
(�����ɁA���ݓI�ɂ́A���̐��Ƃ����G�ΓI�W�̒��ŁA�G��r�ŁE�}�������i�Ƃ��āA�������̑��̕����w�H�w�W�̎�i���˂ɊJ�������K�͉����ꂽ[60]�B�����͂��܂Ȃ���}�~�ͣ�Ƃ��ĊJ�����p������Ă���B�G�ΓI�ȗv�������Љ�ł́A�����J�����Â����Ă���B�C�X���G���p���X�`�i�A�C���h�p�L�X�^���Ȃ�)
�l�ԁE�l�ނ��G�ΓI�ȏ����Ƃ�G�ΓI�ȏ��O���[�v�ɕ�����Ă��邩����A�G���闼���̐w�c���A�Ȋw�Z�p���l�Ԃ̗́E�Љ�̗͂�G��j�邽�߁A�G��}�����邽�߁A�G��}�����ޖړI�Ŏg�p����A�g�p���悤�Ƃ���͕̂K�R�ł���B
�l�ԁE�l�ނ��G�ΓI�ȏ��O���[�v�A�G�ΓI�ȏ��Љ�A�G�ΓI�ȏ������A�G�ΓI�ȏ����ƂȂǂɕ�����Ă��邩����A���̂�����̑����ō��̉Ȋw�Z�p��G�̟r�ŁA�G�̗}���Ɏg�p���悤�Ƃ���B
�l�ԁE�l�ނ��A���݂ɓG�ΓI�łȂ��Љ���n�o���Ă��������Ȃ��B
�l�ԁE�l�ނ́A���݂ɓG�ΓI�v�����g�債�Ȃ��悤�ɁA���X�A�T�d�ȗ����I�ȓw�͂�ςݏd�˂Ă��������Ȃ��B
�l�ԁE�l�ނ́A��蔭���̂��т��ƂɁA�����̎�i���g���ĉ�������悤�ɁA�Љ�S�̗̂����I�\�͂����߂Ă��������Ȃ��B
�l�ԁE�l�ނ̓������G�ΓI���v�����Ȃ����邱�ƁA���ꂪ�l�ԁE�l�ނ̉ۑ�ł��낤�B
���̂��߂ɂ́A�����G�̌����E�����ɂȂ��Ă��邩�A�G�̍����͉����A���̑����I�ȗ�O�ȉ𖾁������I�𖾂��O��ƂȂ낤�B
�Ƃ�����A�ϗ��A�@���A�����́A�݂̕{�������Ƃ͂ł����A���̂ɕ����I�����I�G�l���M�[���[�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�݂̕{�����A�������ێ����镨���I�ȕx���A�l�Ԃ́A�Q��E�Љ���`�����āA���R�E�n���ɓ��������A���̘J���E���Y�ɂ���Ċl�����Ă����B
���Y�Ƃ́H
�l�ԁE�l�ނ̕x�̐��Y�Ɛl�ԁE�l�ނ̓��́E���]�E�����Ƃ̊W�A���݂̃_�C�i�~�b�N�Ȕ��W�W�������A�l�ގj�ł���B
�T������l�Ԃւ̐i���j�̂Ȃ��ł��J������̖���
�@�@�@�B���E�H�Ɖ��̐i�W�̂Ȃ��ŁA�l�Ԃ͎�̊��G��r���E�E�E��̐V���ȍĔ���
�@�@�ߑ㋳��w�̕��y�X�^���b�`�́u�q���̎�̕q���Ȋ��G�����R�ɔ��������A����������邱�Ƃ�����̂͂��߂ł���v�Ƃ������t�E�E�E�l�ޔ��B�j�ɂ������̖����̏d�v��[61]
�u�l�Ԃ��������g�������ł���v�Ƃ�����`������悤�ɁA�Z�p�͐l�Ԃ�����Â�����̂ł���B�i���̂Ȃ��Ől�Ԃ́A�����̎p�����Ƃ莩�R�ɂȂ���p�Ȏ������������ƂƁA�]�����B�������Ƃɂ��A���݂̂悤�ȓ��ʂ̈ʒu���l�������̂ł���B�������A��p�Ȏ��̍I�݂Ȉ������]���h�����Ĕ��B�����A�]�̔��B������ɐi�������ݏo���Ƃ����`�ŁA���҂����������Ȃ���A�V�����Z�p�A����ɂ����������肠���Ă����B
�@���̂悤�ɍl����ƁA�Z�p�͒P�ɕ��ݏo�����߂̕��ւł͂Ȃ��A�l�Ԃ������邱�Ƃ̖{���ɂ�����荇�����̂ł��邱�Ƃ��킩��B[62]�v
�l�ގj�̓��B�_�̈���A�����l�Ԃ��]
�u�]�̒��ɂ́A��1000���̃j���[�����i�_�o�זE�j������B���ꂼ��̃j���[�������A�V�i�v�X�ƌĂ�鐔�炩��ꖜ�̌�����ʂ��đ��̃j���[�����ƊW������ł���B���̕��G�ȃl�b�g���[�N�̂Ȃ��ɁE�E�E�L���ȑz���͂̐��E�A�i�����ł́j���o�̐��E�ݏo���閧���B����Ă���B�v�@���̌���]�Ȋw�̒m����������ƌ��Ă݂邾���ŁA�����̔]�������ɂ��̂������@�\���������邩���z�������B�u�L���ȑz���́v�Ƃ����Ă��A�]�����@�\���炷��A�ق�̈ꕔ���g���Ă���ɂ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����B
�V�˂Ƃ�����l�͔]�S�̂��g���Ă���Ƃ�������B
��l���g���]�̃l�b�g���[�N�ɔ�ׂāA�V�˂��g���]�̃l�b�g���[�N�́A���\���{�ł���̂��H�@
����̔]�Ȋw�ɂ��A�]���\������v�f�ł���u���̑f���q�ɂ́A�S�͂Ȃ��B���̃j���[�����ɂ��A�S�͂Ȃ��B�]�̏����ȕ��������o���Ă��A�����ɂ͐S���Ȃ��B�S�ݏo���̂́A�]�S�̂ɂ܂������āA1000���̃j���[���������グ��A���G�ŖL���ȊW���ł���.�܂�A�S�ݏo���̂́A�]�Ƃ����V�X�e���Ȃ̂ł���B[63]�v
���̓y��Ƃ��Ă̔]�A�V�X�e���Ƃ��Ă̔]�������l�Ԃ́A�F���j�A�n���j�A�l�ގj�̐��ʂƂ��āA�l�l�̓��̒��Ɏ����Ă���B
���́A���̓y��Ƃ��Ă̔]������������Ă��邩�ǂ����A1000���̃j���[������������ׂ��W�����������l�b�g���[�N�Ƃ��āA�c�����s�ɋ@�\���Ă��邩�ǂ����A�ł��낤�B
�@�����āA���̏c�����s�̊����Ȕ]�̃j���[�����זE�̓������\�ɂ���������A�n�m���Ă��邩�ǂ����B
�l�ԏ��l�����炾�̂Ȃ��A�]�̂Ȃ��ɂ݂�Ȏ����Ă����A�F���j�E�n���j�E�l�ގj�̐��ʁA���̂ЂƂ�ЂƂ�݂�Ȑ��ݓI�ɂ����Ă�����\���Ɋ��������Ă��邩�ǂ����A���̊������̂��߂̏����͉����B
�@����̗����E�Ȋw�͂��̂悤���]�̓������̂��̂�[���S�ʓI�ɔc�����邱�Ƃ��ۑ�Ƃ��A�����ɑO�i���Ă���B
���̌���Ȋw�̐��ʂ�����A�����͊w�Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B
�u�]�̋@�\�Ǎ݂̌X���v�ƈ�̐������L�@�I�\���̂Ƃ��Ă̔]�ɂ�铝��
�E �]�̊e�@�\���]�̊e�����ɕ�����Ă���B
�E �j���[�����͂��ꂼ��̋@�\�ɑΉ����đI��I�ɔ�������B
�E �]�̋@�\�Ǎ݂́A�u�K�w�\�����`������Ă���[64]�v
����珔�@�\��������̂Ƃ��Ẵj���[�����E�V�i�v�X�E�l�b�g���[�N
�E
�]�זE�S�̂̏��j���[�����Ƃ��̏��@�\�̗L�@�I�\���I���̓I�V�X�e���I�A��
�u�������̈ӎ��ݏo���Ă���̂́A�]�̒��̃j���[���������ł���B�E�E�E�����_�ł́A�������̈ӎ����j���[�����̊������炢���ɐ��ݏo����邩�ɂ��āA�m���Ɍ����邱�Ƃ͏��Ȃ��B�����A������m���Ȃ̂́A�������̈ӎ����A�]�̃j���[�����̃l�b�g���[�N�S�̂̃V�X�e���_�I�������琶�ݏo����Ă���Ƃ������Ƃł���B
�@�Ⴆ�A�����ӎ��̒��Łw�Ԃ��F�x���������Ƃ���.���̎�ϓI�̌��ɁAV�S��̐Ԃ��F�ɑ��������I�𐫂����j���[������������^����E�E�E�B�������A���̂Ƃ��A�w�Ԃ��F�x�Ƃ����\�ۂ́AV4��̒P��̃j���[���������ɂ���Đ������̂ł͌����ĂȂ��A���̃j���[�������]�Ƃ����V�X�e���̒��ő��̃j���[�����ƌ��W���̉��ɐ������̂ł���B�E�E�E�E�w�Ԃ��F�x�Ƃ�����ϓI�̌��ݏo���j���[�����̊W���́A���o�삾���ɂƂǂ܂�킯�ł͂Ȃ��B�܂�A�]�́A���o�������o���Ƃ��ď������邱�ƂɏI�n���Ă���̂ł͂Ȃ��B�]�́A�ŏI�I�ɂ͊���������Ă������Ɋ�Â��āA�������K�ȍs������邽�߂ɑ��݂��Ă���B���Ȃ킿�A���o��ŏ������ꂽ���o���́A���炩�̌`�œ����̉^���ɔɉh����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�E�E�E�E[65]�v
20���I���E�E�E���x�ɔ��B�����@�\�����j���[�����̔����I���~���[�j���[�����̔���[66]�E�E�E�u���ɉf�����悤�Ɏ����̍s�ׂɂ�����̍s�ׂɂ���������j���[�����v�E�E�E�~���[�j���[�����́u�x�e���Ԓ��ɋ��R�������ꂽ[67]�v�B�\�����ʁA���҂��ʔ����B�K���[�[�����́A�������̌`��̕��̂�A�������̍s���ɔ����Ċ�������j���[������T�����Ƃ��Ă��āA����Ƃ͑S�����������̃j���[�������B
�@�Ռ��I�����E�E�E1990�N�㏉���A�C�^���A�A�p���}��w�A���B�b�g���I�E�K���[�[�ƃW���R���E���]���b�e�B�̔����i���̑�]�玿�̉^���O�삩��j�E�E�E���o�̏��Ɖ^���̏���Z�����锽�����������j���[�����̔����B�~���[�j���[�����́A�u�����́v�s�ׂƁu����v�̍s�ׂ����т���Ƃ����Ӗ��ŁA���ȂƑ��҂Ƃ����A�ӎ��̍��{���Ɋւ���������Ă���B
�@�~���[�j���[�����́A����̔��������������܂łɔ������ꂽ�j���[�����ƈ���āA�u����Δ]�̏���̑S�ĂɊւ��悤�ȓ����������Ă���v�B
�@�u���o�Ɖ^���A���ȂƑ��ҁA��Ԓm�o�A�{�f�B�E�C���[�W�i�g�̊��o�j�B���̂悤�ȁA�]�Ƃ����V�X�e���̍����Ɋւ��悤�ȃj���[�������A�]���́u�^���O��v���^���v���O���~���O���s���̖��ƕЕt�����Ă����ꏊ�Ō����������炱���A�Ռ��I������[68]�v�ƁB
�@�]�Ȋw�̗��j�́A����Ӗ��ł́u�܂�������Ȕ������������j���[����������Ƃ́v�Ƃ��������̗��j�Ƃ��I
�@1962�N�̔����E�E�E�̂��Ƀm�[�x���܂���܂����A�����J�̐_�o�Ȋw�ҁA�f�C���B�b�h�E�q���[�x���ƃg�[�X�e���E���B�[�[���̔����c�L��V1��i��ꎟ���o��j�ŁA�u�������̕����ɌX���������v�����ɔ�������j���[�������B
�@
�~���[�j���[�����ɑ������镔�ʁi�~���[�V�X�e���j�́A��MRI�i�z�q�f�w�B�e�@�j�Ȃǂ��g���������ɂ�����l�Ԃ̑O���t�̉^���O���ł��������Ă���A��[69]�B
�u�~���[�j���[�����̔����ȍ~�A���͂�A���o����Ɖ^����������ė������悤�Ƃ���A�v���[�`�͕s�[���ł���Ƃ����F�����L�܂��Ă���B���o�^���A�����܂߂��]�S�̂̃V�X�e���_�I�����Ƃ������_����A�P��̃j���[���������̓d�C�����w�f�[�^���܂߂��S�Ă̔]�Ȋw�̒m�������������Ƃ��ӎ�����n�߂Ă���B�V�X�e���Ƃ��ė������悤�Ƃ���̂łȂ���A�]�Ƃ������G�ȑ���̐������������������Ƃ͂ł��Ȃ��B���ꂪ�]�Ȋw�́w�V�X�e���_�I�]��x�̃��b�Z�[�W�Ȃ̂ł���B[70]�v
�~���[�j���[�����́A���̋�̓I�ȑ��ݏꏊ�i�^���O���j�ł̋�̓I�ȋ@�\�����x�ł������ł���B�����w�I�זE�w�I�Ɏ��o���A�~�����[�j���[�������u�����̃j���[�����v�ł���B
�@�u�~���[��[�j���[�����Ƃ����P�Ƃ̃j���[�������A�������̈ӎ����x���Ă���Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B�~�����[�j���[�������A�^���O������Ƃ肾���ăy�g���M�̏�ɒu���A���̕ϓN���Ȃ������̃j���[�����ł���B�~�����[�j���[�������]�Ƃ����V�X�e���̒��œ��ʂȖ������ʂ����Ă���Ƃ���A���̓��ʂȖ�����^���Ă���̂́A�~���[�j���[���������͂ރj���[�����̊W���ł���[71]�v�ƁB
�@�O���t�̉^���O��̃j���[�����Q�̑��݊W�E�@�\�A��