�X�V���F2004/09/22
1990�N��̓��{�o�ώj�|�o�u������E���̐���́E�O���[�o�����̒��ł̓��{�o�ρ|
�O���u�`�ŁA�Ȃ������{�o�ώj�Ɋւ��ė͓_��u��������������āA90�N�㒷���\���s�����肪�w�E����钆�ŁA���{�ɂ����钷���I�o�ϔ��W�̎�v�X���Ƃ��̊�{�I���v����c�����Ă������Ƃ�������炾�A�Ƃ������B�s�����ɂ�(����s������������������ɂȂ�A�ނ��댵����)�ѓO����@���B
���Y�̏��v���A���{�̒~�ρA�J���̐��Y���̏㏸�ȂǁA��A�̑��݂Ɋ֘A�������v���ł���B
�O���̍u�`�œ��v���Љ�Ȃ���ׂ̂��悤�ɁA�o�u���ɂ�����n�������Ƃ��̕���ɂ�����n�������̃_���[�W�E�E�E���Y���l��700���~�K�͂Ō������B���̋��Z�I�}�C�i�X�v���͌���I�B
�����I�Ȑ��Y�g��(�v�����g���݂��̑�)������I�ȎЉ�(���{�Ɛ��E)�̎s��K�͂̑���Ƃ���ɉ��������Y�\�͊g��A���̗�O�Ȍv��Ȃ��ɁA���@�I�ɓy�n����߂��@�l��Ƃ̉ߏ�ȕ��B
���������Y�Ǝ��{�ɑ��āA����܂�������Ƃ����s��\���Ɋ�Â����Y�v���W�F�N�g�����邩�Ȃ����Ȃǂ����܂��Ȃ��A���@�I�ȓy�n�w���ɑ��Ď�����݂������Z�@�ցB
�ݕ����{�̎����ݕ����{�݂̑�����A�o�����A�����I�s��g�奐��Y�g��̊�Ղ����@�����܂܋��Z�Q�[���ɋ��z�����B
�y�n�S�ۋ��Z�A�y�n�̐��Y�I�ȗ��p�\���Ɋւ����O�Ȍv�Z�����̓��@�I�y�n����߁��؋����ēy�n�w������葤���炷��Ζc��ȕ��A�݂��葤�̋��Z�@�ւ��炷��Εs�Ǎ��B
���Ԃ��̂悤�Ȗϑz�Ɏ����𓊉������̂�����A�ł��t���͕̂K�R�B
���̂��ڂ̖@�l��Ɓi�Y�Ǝ��{�Ƌ��Z���{�j���w�����͓̂��R�B
�Ƃ��낪�A���̃o�u������̕��S�����邽�߂ɁA���{����̢�������ƣ�Ȃǂ̐Ԏ��x�o�B
���̢���v�n������A�����I�ȕK�v���ȂǂɊւ��Ă͑�ÂȔ��肵�����Ȃ����̂ŁA�����̂悤�ɍ��Ƃ��������������A���܂�719���~�̌��I�ݐύ��ɖc�����Ă���B
�����������ꂪ���̍����x�����̂��H�@
�N���o�ύ����i2003�N�A2004�N�j�̂Ȃ��ł́A����ň����グ������Ă���B�܂�A��ʍ����̏�����ɑ���ېŁi���Ȃ킿���Łj�ł���B�������A���z�ɏ��ݐύ��̕��S�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B
�������A�o�u���ɋ��z�����̂́A�������H
���@�Ɋ������܂�A�t�a���������������������A����Ȃ��Ƃɂ������̂Ȃ����������̕��������B�Ƃ�킯�A�o�u�����ɂ܂��q�ǂ��������l�X�₤�܂�Ă��Ȃ������l�X�A���Ȃ킿�Ⴂ�l�X�ɐӔC���Ȃ����Ƃ����͂͂����肵�Ă���B���̐ӔC�Ȃ��ЂƂтƂ��A�c��Ȍ��I���̕��S�킳���Ƃ���A����͕s�����ł͂Ȃ����H�@����łƂ����̂́A���ڐ�(�@�l�ŁA�����łȂ�)�ƈ���āA�����S���A�Ƃ�킯�Ꮚ���w�ɏd���̂�������ŋ��ł���B
�o�u���c���ɖz�������̂́A���|�I�ɂ͖@�l��Ƃł���A�����ɂ�铊�@�ł���B
�Ƃ��낪�A���L�̐Ő������ɂ���āA�@�l��Ƃ́A���̍��Ƃ̍����Ԏ��̌������ꂵ������ɁA���ł��������Ă���B���N�x�����ŁA�@�l�֘A�Ő���1��3040���~�����ł����̂ł���B
����ɁA�����̒��ł��T���Ȑl�X����Ƃ��Ďx���������ł②�^�ł��A���łł���B�o�u����������A�o�u�����ɑ�������������Z��،��ƊE�A���邢�͋��Z���Y�E�،����̍��Y�������Ă���l�X�ɂ́A���N�x960���~�A���N�x�ȍ~1250���~�̌��łƂȂ��Ă���B
�S�����ɊW�������ł̐ŗ��́A�܂��������Ɉ����グ���Ă��Ȃ��B
�������A�N���o�ύ�����ǂނ�����A����ő��ł̈��͂͂܂��܂������܂��Ă���Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
���łɁA���L�iH16�N���o�ύ��������j�̕t�\1�|22�������悤�ɁA�������Ǝ҂ɑ������[�u�����������Ƃɂ���āA�������Ǝ҂ւ̉ېł������A���N5040���~�̑��łƂȂ�B��ʍ����̏����ł������������邱�ƂɂȂ�B���N4,790���~�̑��łƂȂ�B�����̍��������S���邱�ƂɂȂ��^�o�R�ł����łƂȂ��Ă���B
���������Ő����v���A���������ǂ��̗��v�����A�ǂ��֕��S�������邱�ƂɂȂ邩�A�������茩������K�v������B
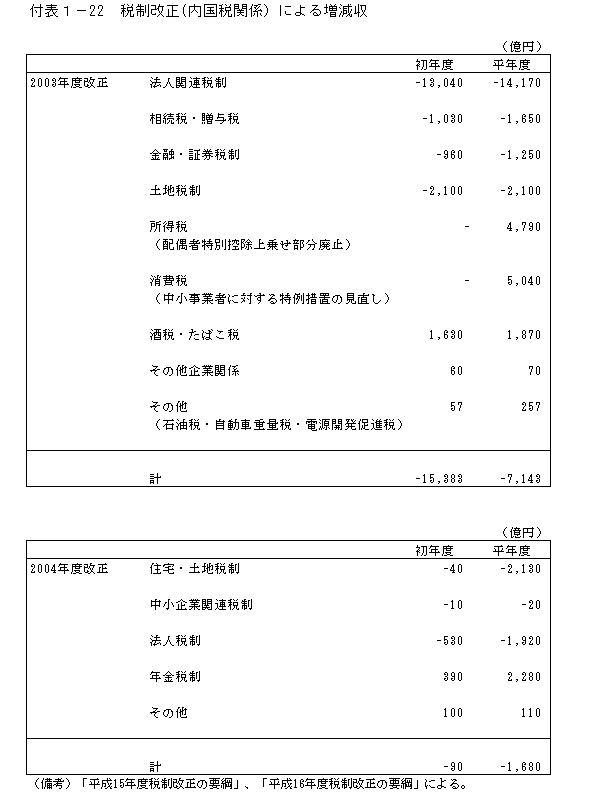
�����͂��łɁA�o�u���Ⓒ���炻�̕���A�����Ē����s���̂Ȃ��ŁA���ƂƂ������S���Ă����B
��Ƃ̓��X�g�������s���A���������āA���S���Ɨ��͏㏸�𑱂����B96�N����2002�N�܂ł͎���Ɋ��S���Ɨ��������Ȃ��Ă���B�������Ȃ��Ȃ�n�߂��̂�2002�N�ł���B
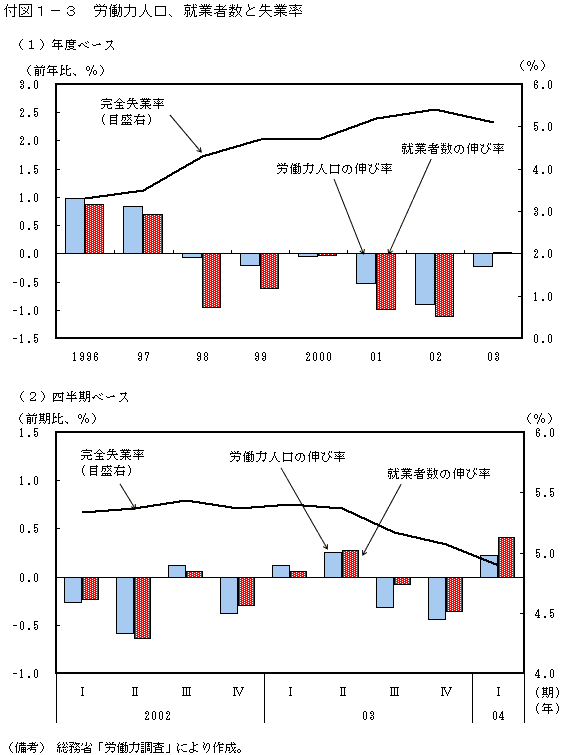
�����̕��S�́A���Ƃ����ł͂Ȃ��B�����̉ƌv�x�o�́A�s���̒��Ŏ���Ɍ�������������Ȃ������B�������������璙�~�ɉ镔���͏��Ȃ��Ȃ����B
���̓_�������̂��A���̕\�ł���B���~�����������A���������Ɖƌv�ŏI����x�o���X���I�Ɍ������Ă��邱�Ƃ�������B�����~�܂肪�����2003�N�ɂ���Ă����A�Ƃ����Ƃ���ł���B
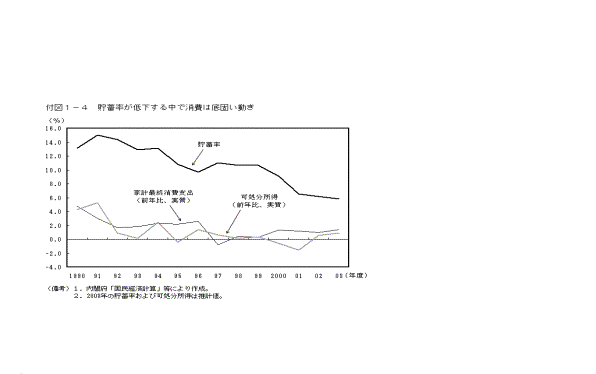
�@������}���ɐi�ޒ��ŁA���ɂ�����c��̐l�X���N�������ɓ��鎞���ɂȂ��Ă��āA���݁A�����ď����̋ΘJ�����́A���N�x�̔N�������������āA�N�����S�����������邱�ƂɂȂ�B
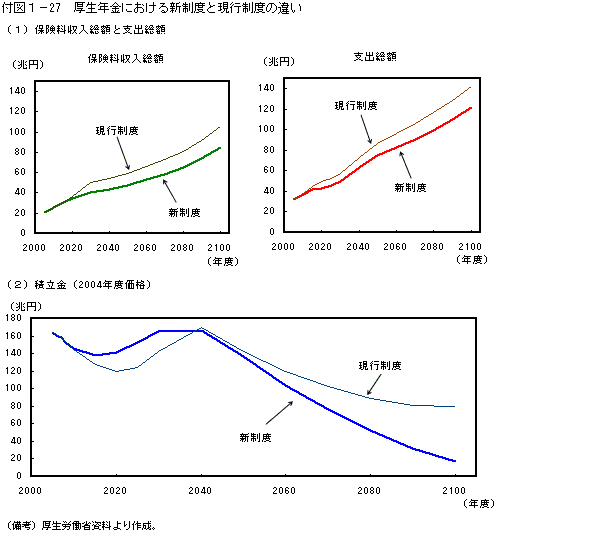
����ł́A�@�l��Ƃ́A���̢�����s����̂Ȃ��ŁA�s���ɋꂵ�ފ�Ƃ��肾�����̂��H
�����ł͂Ȃ��B
������g��Ƣ�����g�ݣ�Ƃ悭������悤�ɁA�@�l���㏸�g�傷���ƌQ�Ɖ��~��k�������ƌQ�Ƃœ����Ă��邱�Ƃ��݂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���̓_�ŁA�O���u�`�A����ёO���e�X�g�ŗ��p�����@�l��Ɠ��v�͉�����Ă��邩�H
����x���̓��v�����Ă������B
|
�N ��,�o �c �g �D, |
�� �� |
�� �{ �� �K �� �� |
||||||||
|
|
||||||||||
|
|
300���~ |
300�` |
500�` |
1,000�` |
3,000���~ |
1�` |
10���~ |
|||
|
�@ |
�� �� |
500���~ |
1,000���~ |
3,000���~ |
�`1���~ |
10���~ |
�� �� |
|||
|
|
|
�@ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
����3 �N |
�@ |
1,561,300 |
a)132,420 |
b)688,750 |
352,074 |
279,600 |
83,897 |
20,126 |
4,433 |
|
|
|
8 |
�@ |
1,674,465 |
33,439 |
573,562 |
223,481 |
714,972 |
100,381 |
22,891 |
5,739 |
|
|
13 |
�@ |
1,617,600 |
16,621 |
586,546 |
205,683 |
673,041 |
105,616 |
23,950 |
6,143 |
|
������� |
�@ |
744,506 |
48 |
288 |
345 |
613,448 |
100,496 |
23,762 |
6,119 |
|
|
�L����� |
�@ |
850,054 |
987 |
583,439 |
202,763 |
57,837 |
4,839 |
178 |
11 |
|
|
�@����������� |
�@ |
23,040 |
15,586 |
2,819 |
2,575 |
1,756 |
281 |
10 |
13 |
|
|
�u���Ə��E��Ɠ��v�����v�i10��1�����݁j�ɂ��B�������C����3�N��7��1�����݁B����3�N�͒��茧�����s�C�[�]���̊�Ƃ������B |
||||||||||
|
1) �ߕ��C���̑��̑@�ې��i�������B 2) �f��E�r�f�I����Ƃ������B
a) ���{��100���~�����B b) ���{��100�`500���~�B |
||||||||||
|
�����@�����ȓ��v�Ǔ��v�������o�ϓ��v�ێ��Ə��E��Ɠ��v���u���Ə��E��Ɠ��v�����v |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
��L10�N�ԁi1991�N����2001�N�j�ɁA10���~�ȏ�̋����Ƃ́A1700�Ђ������Ă����B
���̃N���X�����{��1���~����P0���~�̑��Ƃ��A3600�Јȏ�������Ă���B
����ɁA���{��3000���~����1���~�̊�Ƃ̐���2��2��ЂقǑ����Ă���B
�������āA���{���̑傫��3�̃����N�́A�o�c�`�ԂƂ��Ă͊�����Ђ������A����10�N�Ԃɒ����ɑ����Ă���̂ł���B
���{�̒~�ϥ�W�����O�i���Ă��邱�Ƃ�������B
���{��1000���~����3000���~�̒��K�͊�Ƃł�10�N�Ԃ�����Ă݂�A40���Ћ߂������Ă���̂ł���B
�ׂ��i�����j���l�������Y�Ǝ��{�́A��������K�͂ɏW�߂Ă���ɒlj����{�Ƃ���B�~�ς�����]���l(����)�Y���g�傷�邽�߂Ɏ��{�Ƃ��ē�������(��������]���l�̎��{�ւ̓]��)�B
�u���{�̒~�ρB���Ȃ킿�A�����̈ꕔ���̎��{�Ƃ��Ă̎g�p�B�v�i�}���T�X�w�o�ϊw�ɂ����鏔��`�x�P�[�Y�m���ŁA11�y�[�W[�ʖ���A176�y�[�W]�j
�u�����̎��{�ւ̓]���v(�}���T�X�w�o�ϊw�����x��2�ŁA�����h���A1836�N�A320�y�[�W[��g���ɔŁA�����A181�y�[�W])
���Y�K�͂̊g��Ǝ��{�~�ϥ���{�W�����Ƃ̋��剻���A�s���̃C���[�W�̔w��Ői�s���Ă������Ƃ�������B
�������鎑�{��`��Ƃ́A�㏬���ׂȊ�ƌQ�����������őł��|���A�㏬���{����K�͌o�c���s�ꂩ��쒀����B
�����s���������͂܂��ɁA�㏸����@�l��Ƃ��A���Y�͂����߁A���������A�s�ꋣ���ɏ��������A���{��~�ς��A�o�c�K�͂��g�傷��̂ł���B
�����ɂ́A���{��`�~�ς̈�ʓI�@�����ѓO���Ă���B
�t�Ɏ��{���z�����Ȃ��K�����݂�ƁA�����Ȃ��Ƃ�1996�N����2001�N�̊Ԃ����ł��������Ă���B
���{��300���~�Ȃ���500���~�̊�Ƃł́A�L����Ќ`�Ԃ��������A�قړ��������ێ��Ȃ���������Ă���B
���{��500���~����1000���~�̃N���X���������A10���Ћ߂��������Ă���̂ł���B
�����̃f�[�^���番���邱�Ƃ́A��{�I�ɑ�K�͂Ȋ�Ƃ������A�܂���r�I�傫�Ȏ��{��1000���~�ȏ�̊�ƌQ�������Ă���̂ł���B
����ɑ��āA���{��1000���~�����̊�ƌQ�̐��͑S�̂Ƃ��Č������Ă���B����Ȋ�Ƃ��傫�Ȋ�Ƃ������A���K�͗�K�͂̊�Ƃ���������Ƃ������ƁA�܂��ɂ��ꂱ�����{�̏W���Ƃ����ׂ����̂��낤�B
�����s���Ƃ�����90�N��ɁA���́A����������ɕ������i��ł����̂ł���B�܂��ɢ�����g��Ƣ�����g�ݣ�������Ƃ������Ƃ��킩��B
�����āA�u�����g�v�͢�ׂ��(����)�����{���ɓ]�����A���{���𑝂₵�A��А��𑝂₵�Ă���̂ł���B�������A���̉ߒ��ŋ@�B�Z�p�̓����A���Y�ƌo�c�̍������𐄐i����B�����Ɂu���X�g���v���i�W����B�����l�̐��́A���ΓI�Ɍ�������(���ΓI�ߏ�l�����Y�Ɨ\���R�̑n�o)�B
������A�u�����s���v�̒P���Ȉ�ʓI�ȃC���[�W�́A���������ׂ��ł���B
��ɕ������i�W�����Ƃ�����{�I������c�����Ă����K�v������̂ł���B
�����ꂽ10�N��́A���K�͂��K�͂̊�ƁA�������ꂽ��Ƃɂ��Ă����邱�Ƃł���B
�傫����Ƃ́A��������Ǝ��{�~�ς��A�㏬�̊�Ƃ𓑑����A�܂��A�o�c�̍�������l���팸���s�����{�K�͂ɂ����Ă����ɂ����Ă��傫���������Ă���̂ł���[1]�B����������{�I�������A���L�ɏq�ׂ题_����́A�������Ă��Ȃ��B
�ȏ�̂悤�Ȋ�b�I�f�[�^���������肩�ݒ��߁A80�N��㔼����̃o�u���o�ςƂ��̕�����90�N�㒷���\���s�����A�����_�łǂ̂悤�ɍl���邩�́A����̌o�ύ\�z�E���̕�������T�邽�߂ɂ͏d�v�ł��낤�B
���L�̘_�������邩����A90�N�㒷���s���̕��͂ɂ����āA�o�u���Ƃ��̕���̉e���̉𖾂�������Ɛ^���ʂ���s���Ă��Ȃ��Ɗ�����B���̂����A������GDP520���~�O��ɂ���ׂāA700���~�ɂ��c���ł��鍑���z�̈Ӗ�(�����j�])���ǂ̂悤�ɍl���邩�A����I�ɏd�v���ƍl����i���̓_�A�s����w�E�e�c�����̍u�`�����ɁA����߂ĕ�����₷���u�����j�]�N�\�v�A����Ѣ���{�̌��I���̌���ƃ����N�������̂ŎQ�Ƃ��ꂽ���j�B
50���~�̐Ŏ��ŁA���N30���~�̍��s���ė\�Z���z80���~�Łu�����\���s���v�����낤�Ƃ��Ă������Ƃ̂��́A�������x����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�B������l�߂̂��߂ɂȂ��ׂ����Ƃ͉����H�@���N30���~���̍��s���Ă���Ȃ��ŁA�u�����v���N�v�̂��߂Ə̂��Ă���ɍ����x�o���Â���ׂ����H
�o�u���ɋ��z���A���̕����̒����s���ɂ����ẮA�����j�]�Ɋׂ��Ă��鍑�Ƃ��碌���������������o���A���ǁA700���~���̗ݐ�(���킵���́A�u�킪���ɂ�������I���̌��v2003�N3���A�����ȗ������F����15�N�x�N���o�ύ�����H15�N10�����t�{�A��16�N�x�u2004�N�x���̍��y�ђn���̒������c����719���~���x�v[2])�ƂȂ����킯�����A�o�u���ɔM�������l�X�A���̕����ɐԎ������𑣐i���A�����܂Ŗc��ȐԎ���ݐς��Ă����l�X�A�����������Ɛ���ɉe����^���A������^�c���Ă����̂͒N���E�ǂ̂悤�Ȑl�X����ǂ̂悤�Ș_�����H
����x�A�����o�ϊwpolitical economy�̑��̂����ꂩ��ᔻ�I�ɍl�������Č��邱�Ƃ����߂��Ă͂��Ȃ����H
------------------------------�@
��������̋c�_������Ȃ��A����܂ł̊e��c�_(������X�^���_�[�h�Ȍo�ϊw�ɂ����邻��)�������_���������ɂȂ����B
�P�D �l�c�G��E�x�����`�E���t�{�o�ώЉ���������ҁw�_���@���{�̌o�ϊ�@�|������̐^�����𖾂���|�x���{�o�ϐV���ЁA2004�N5�����A�ł���B�X�e�B�O���b�c�w�}�N���o�ϊw�x�̈�ʗ��_�̔ᔻ�I�����̉ߒ��ŁA���̖{���ǂނ��ƂƂȂ����B�����A��nj�̊��z�����A�u��_���v�Ƃ����قǂɂ͉s���Η��_�͌���ꂸ�A�����A�c�_���ׂ��ȕ����őΗ�������Ⴄ�Ƃ���������B���ǁA�����ꂽ10�N��́A�ǂ̂悤�Ȏ�v���̘A�ւɂ����̂Ȃ̂��A�������藝���������̂Ƃ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B
�Q�D �֘A���āA��L�Ƙ_�҂����l�����ʂ�����N�O�̖{�A��c�K�v�j�{�{��w�ҁw����ꂽ10�N�̐^���͉����x���m�o�ϐV��ЁA2003�N6��
�R�D
����I�I�Y�w���{�o�ρ@��Ƃ���̊v���\��g�D���珬�g�D�ց\�x���{�o�ϐV���ЁA2002�N�E�E�E1940�N�̐������͐�̐������̌p�����u���܂���{�͐��E�ōŌ�̎Љ��`�o�ύ��ɂȂ����Ƃ����ĉߌ��ł͂Ȃ��v�Ƃ̌����B���͐�̐����\�A�^�Љ��`�ł�����B���L����c��������͂ƒ����W���I���Ƒ̐�(�Љ��`�̐�)�ɂ����鋤�ʐ��B����{�Đ��̑����́A���{�Ɋ��҂���̂���߂邱�Ƃ��B�E�E�E����{�ւ̈ˑ���́A1940�N�̐��̊�{�I�ȃ����^���e�B�ł���B���̈Ӗ��ɂ����Ă��A40�N�̐�����̒E�p���K�v�Ȃ̂��B��@�u��7�́@��w���v���Ȃ��d�v���v�ł́A����{�̑�w�̌�i�����ᔻ���A����n�̐��Ɨ{�����K�v��A�u���Z�ɂ�������Ƃ̕s���v��������ォ��ς��ʊw���\����A�u�w���Г����B�x�ł��܂���Ă����l�I�����v�̂������ᔻ���A�v���t�F�V���i����X�N�[���̑n�݊g�[���āB
�w�]�ƈ���厖�ɂ���o�c�x�̑�����咣�B��o�c�҂��������i�҂œƐ肳���̂́A��ƌo�c�Ɋ���̈ӌ��������Ȃ����炾�B����͊������������B�Ŏ�v�Ȗ������ʂ����Ă��炸�A��s����̎ؓ���ɗ����Ă��邩��ł���B�������āA���{�^��Ƃ́A�]�ƈ����\�����鋤���̂ł���A�]�ƈ��̐�������邽�߂̑g�D���ƊϔO����Ă���B����̏��L���Ƃ͍l�����Ă��Ȃ��̂ł���B�Ƃ��ɑ��Ƃɂ��ẮA���������l������ʓI���B�]�ƈ��̂��Ƃ��l���Ȃ���ƌo�c�͔��Ƃ�����B�������A�w�]�ƈ���厖�ɂ���x�Ƃ������{�^�o�c���A���ǂ͊�Ƃ𐊑ނ����A���ƂƂ����`�ŏ]�ƈ��ɍł������Ȍ��ʂ������炵���邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ���ip.199�j�ȂǂƎ咣�B�������A��̓I�ȕ��͂�����킯�ł͂Ȃ��B
�O���u�`�ʼn��Љ���ɒO�h�V��l�{��`��ƣ�_�̒�����ᔻ����X�^���X�B
�@�ŏ��̓�̖{�̂Ȃ��ŁA��X�^���_�[�h�Ȍo�ϊw������������i�g��m��߂�����͂Ȃ��y����̔@���H�I���c��{����w����ꂽ10�N�̐^���͉����x�����Ap.22�j�Ƃ����ӏ��ɖڂ��~�܂�B
�@��̖{��ǂ݁A�܂���3�̖{�����Ă��A90�N�㒷���s���̌������߂����ẮA�܂��Ɍ���I�Ȑ����͂̂��镪�͂��o�Ă��Ȃ����Ƃ���������B����͂Ȃ����H��X�^���_�[�h�Ȍo�ϊw��̖��ͥ��L�������Ӗ����Ȃ����H�@���Ȃ��Ƃ��o�ς̘_���A�o�ϊw�̊�{�_����Ȃ����K�v�͂���̂ł͂Ȃ����H
�Ƃ�����A
�P�D�l�c�G��E�x�����`�E���t�{�o�ώЉ���������ҁw�_���@���{�̌o�ϊ�@�|������̐^�����𖾂���|�x���{�o�ϐV���ЁA2004�N5����
�u�܂������v�`���E�E�E�u���{�o�ς́A1990�N��ȍ~�A�����̒���ɂ���A���̌������߂����_�����J��L�����Ă����v�ƁB
����ł́A������̒����Ƃ͂Ȃɂ��H�@�{���܂������̂Ƃ炦���́A���̂悤�ł���B
�u�ɒ[�ȉ���Ƃ��āA90�N��̓��{�̎���GDP���A1991�N���猻���̔N��1.2���ł͂Ȃ��āA����܂ł̃g�����h�ł���N��3���Ő������Ă�����A2003�N�̎���GDP��679���~�ɂȂ��Ă���B�Ƃ��낪�A�����̎���GDP��547���~�ɂ����Ȃ��i�������95�N���i�j�B���Ȃ킿�A�����̎���GDP�̓g�����h��GDP����20�����Ⴂ���ƂɂȂ�v�ƁB
�Ƃ���A�𖾂��ׂ��́A80�N��܂ł̔N��3���̐������𐬗����������v���ł���A90�N�㐬����1.2���̏��v���ł���A���̔�r�ł���B
�{������������Ƃ���ł́A���̌����������Ƃ����B
�u��̌����́A���{���}�N������A���Ȃ킿���Z���������̉^�c�Ɏ��s�������߂����v���s�\���ƂȂ�A���{�o�ς͂��̐��ݐ����͂�������Ȃ������ƍl�����ł���B������̌����́A����A������̌����́A10�N�ȏ��������͋����\�͂����v�s���Ő������Ȃ��������߂ł͂Ȃ��A�������̐��ݐ����͂̓݉��ɂ����̂��Ƃ����l�����ł���B���̌����ɂ��A���v���N����̎��s�����A���ݐ����͂�ቺ�������\���v�������d�v���Ƃ������ƂɂȂ�B�v
���݂Ɋ֘A�������A���݂ɔr���I�ł���Ƃ����킯�ł͂Ȃ����A�4�̐����L�ͣ�Ƃ����B
�u�P�@��͓��{�o�ς������Ă���\�������������Ȃ��������炾�Ƃ�����\������
�@�Q�@�h�����ׂ��Ƃ��Ɏh�����Ȃ�������������̎��s�ɂ��Ƃ�������������v����
�@�R�@�f�t���������炵�����Z����ɂ����̂��Ƃ�������Z�����v����
�@�S�@�s�Ǎ��̑��������Ɏ��s�������Ƃ���s�@�\�ቺ��ʂ��Ē�����������炵���Ƃ������s�@�\�ቺ�v����
�܂��ɂ���珔�v���́A��̓I�Ɏ��ؓI�Ɍ����ׂ��ł���B��������ꂼ��̐��̎咣�҂ɘ_���������Ă�����āA���ݔᔻ�A���ᔻ���f�ڂ����̂��A�{���ł���B���̈Ӗ��ŁA���̐����ᖡ���Ă݂鉿�l�́A�\���ɂ���B
�u�P�́@���{�o�ς̒�����Ƌ����T�C�h�@�{��w�v�́A�Ƃ��ɁA�u�����̉����d�����ɂ����GDP�M���b�v���g�債�����ۂ̎������A���{�o�ς̒�����̎p�ł���ƌ����c�_�ɒ��ڂ���v�B�u���v�T�C�h�̘_�҂�������������̉����d�������A�����T�C�h����݂�ƁA���{�̗�������ቺ������v���ƂȂ�A���ꂪ���{�~�ς�݉������A1990�N�ォ��̌o�ϐ�������ቺ�������ƌ������W�b�N�����藧�v�ƁB
�����āA����������̏㏸���A��������ቺ�����Ă������Ƃ��m�F����A���{�o�ς������ꂽ10�N�����E�p���邽�߂ɂ́A������(���҂��܂߂�)���㏸������悤�Ȏ{�K�v�ł��邱�Ƃ���������v�B
�������A�����s���Ƃ́A�܂��ɒ����I�ȍ\���I�ȁu�������̒ቺ�v�ł���B���̑��݊W�����Ȃ�A������s����̂���Ȃ��`�Ɠ����ŁA�Ȃɂ����͂��Ă��Ȃ����ƂɂȂ�B
��(����)�����i��p��c�{v�j�Ŋ����������������ł���(���㍂���v���ȂǁA���낢��̎w�W�͂��邪�A�l�����ׂ����v���͉��L�Ŏw�E����悤�ɁA���������ł͂Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���A����ނ��덂�x�ɔ��W�������{��`�@�l��Ƃ̏ꍇ�ɂ́A�H��@�B�ݔ��ȂǕs�ώ��{�����̑傫����c�������A�������Ɍ���I�ɑ傫�ȃE�G�C�g���߂�[3])�B
���������ቺ����v���́Ap�����Ȃ��Ȃ邱�Ɓi�s�ꋣ���̌����Ȃǂɂ�闘�������̈��k�j�A��p�ic���@�B�⌴���̃R�X�g�A����ɒ������j�̎�X�̗��R�ɂ�鑝��̌��ʂ��A������������������B��������̒ቺ��̈�����A���������Ĕ��グ�S�́i��+��+������+���j�ɐ�߂�����������̑��ΓI�����ł��邱�Ƃ͎��������Ac�̕ϓ��v�����������ɂ͊W����B����v�̑��������𗘏����ቺ�̗v���Ƃ��ċ�������̂́A��ʓI�ł���A�C�f�I���M�[�ɂ����Ȃ��B
�Ȃ��A���������炢���Δ��グ�������Ȃ����A���グ�������������Ȃ�i���̐�Ίz�Ɣ��グ�ɐ�߂銄������������j�̂͂Ȃ���(����T�C�h���炢���A�Ȃ����{�̏��i�����v����Ȃ����A���v���E���v�J�ł��Ȃ���)�A�Ȃ��������d���I���A�Ȃǂ̏��v�����������͂��ׂ��ł���B
����I�I�Y(2002)�w���{�o�ρ@��Ƃ���̊v���x���{�o�ϐV���ЁE�E�E�u���{�o�ς̒���͎����I�ȗv���ɂ���Ĉ����N�����ꂽ���̂ł���A��̓I�ɂ͒������n�߂Ƃ����A�W�A�����̋}���ȍH�Ɖ��ƃA�����J�𒆐S�Ƃ���IT���ɓ��{�����x�ꂽ���߂ɐ������v�E�E�E����́A���Ȃ�L���w�E����Ă��邱�Ƃ����A����������̓�̎����I�ȏd�v�ȗv�����w�E���Ă���B
��A�W�A�����̋}���ȍH�Ɖ���𑣐i����v�����A�������E�������ɑ剻�����߂���{���(���{)�̒������̑��A�W�A�����ւ̐i�o�ł���A���ꂪ�A���{�����̐��Y�̋��������炷���̂Ƃ��āA���������Ă܂����ƁA���X�g����K�R��������̂Ƃ��āA�L���w�E����Ă���B���������āA���{���{�E���{��Ƃ̗����ɑ剻�s���i���Ȃ킿�A�������������߂ẴA�W�A�����ւ̐��Y�ړ]�E�H��ړ]�j���A�|���ē��{�����̌o�ς��I�ɒ������(���ɕς��V�Y�Ƃ�n�o�����Ȃ�����)�A�Ƃ������ƂɂȂ�B
��A�����J�𒆐S�Ƃ���IT���ɏ��x�ꂽ��Ƃ����̂��ǂ̒��x�̎����Ȃ̂��A����I�I�Y(2002)�ɒ��ړ������Č����Č���K�v������B
�����T�C�h�̗v��������������ؕ��͂Ƃ��āA��\�I�ȕ��͂Ƃ���Hayashi, Fumio
and Edward C. Prescott (2002), �gThe 1990s I Japan: A Lost Decade,�h Review of
Economic Dynamics 5, oo.206-235���Љ��Ă���B����ɂ��A�u1990�N��̓��{�o�ς́A�J�����Ԃ̌������S�v�f���Y���㏸���iTFP�㏸��[4]�j�̉����V�t�g�ɂ��A�����o�H���ቺ�������߂ɁA�����]�V�Ȃ�����Ă���Ǝ咣���Ă���v�Ƃ����B
���{�̘J�����Ԃ�90�N��ɂ����Ė{���Ɍ��������̂��낤���H�i����.ILO���v[5]�j
��T�[�r�X�c�ƣ�A��ߘJ������������艻�����̂́A�܂���90�N�㒷���s���ɂ����Ăł͂Ȃ����B
����͂����Ƃ��Ă��A���̋c�_���ƁA��������̌����́A�J���ҁE�ΘJ�҂̢�J�����Ԃ̌�����ɂ���[6]�Ƃ����B
����ł́A�J�����Ԃ���������A�����������E���邱�Ƃ��ł���̂��H�@���{�̎Y�Ƌ��͂Ȃ��Ȃ�̂��H�@�A�W�A�����̑��ΓI������J���҂Ƃ̋����ɏ��Ă邱�ƂɂȂ�̂��H�@���̋c�_���ƁA���̐������A90�N��ɐV�������A�W�A�̍H�Ɖ��̐i�W�̓��{�o�ςւ̉e���Ȃǂ����͂���邱�ƂȂ��A���{�̘J����(���̘J�����Ԍ���)�Ɍ��������邱�ƂɂȂ�B���ۓI�ȘJ�����Ԕ�r[7]����l���Ă��A���������͂Ȃ����H�@
�܂��A�A�W�A�����̍H�Ɖ��ɓ��{��ƁE���{���{���g�����o���Ă������̂ł͂Ȃ����H�@�����������{�����͂ǂ��Ȃ�̂��H
���{�̎��{�E��Ƃ�������J�������߁A�A�W�A�H�Ɖ��̔g�ɏ���Ē������n�߂Ƃ���A�W�A�����ɊC�O�i�o�𐋂���Ƃ��A����œ������{�̎��{�E��Ƃ��Ȃ��ׂ��́A���{�̘J���҂��ΘJ������V�����n�o���邱�Ƃł͂Ȃ������̂��B�܂��ɁA���{��ƁE���{���{�̈�ʓI�ň���I�ȑΊO���{�A�o�E�H��ړ]�̍s�����A���{�o�ς̒�����̌��������o�����̂ł͂Ȃ����H
�Ƃ���A�݂�����i�߂Ă����A�W�A�o�ς̍H�Ɖ��̌��i�K�܂��āA���{�ƃA�W�A�����̕��ƊW���\�z���邱�Ƃ��K�v�ł��낤�B���̎��A���{�̍H�Ƃ̍��x���A�@�B�Z�p�̍��x�Ȕ��B�ɂ��ƂÂ����Y�V�X�e�����A�A�W�A�����̐����ƂƗL�@�I�ɘA�g���邱�ƂɂȂ낤[8]�B
���������W�J�́A�A�W�A�������݂ɂ�����r�O�I�i�V���i���Y������̂����ɓE�ݎ��Ȃ��ŒB������Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B���{�ɂ����邻�̎�̓I�ӔC�͂��������{���g�̍s���ɂ���B
�{��̎咣�́A���������̍��܂������̎�v���Ƃ��ČJ��Ԃ��A�w�E����Ƃ���ɂ���B
�u1970�N�ォ��ŋ߂܂ł̐��v�ł́A�S�Y�ƁA�����ƂƂ��A���������̏㏸���������̒ቺ�������炷�Ƃ����W�����m�Ɏ�����Ă���v�Ɓip.16�j�B
�������������Ƃ���ƁA90�N��܂ł̔N��3���̐������͂ǂ��Ȃ邩�H���̏��v���́H�@���̏��v���̂ǂꂪ�ǂ̂悤�ȗ��R�łȂ��Ȃ����̂��H
�{��́A90�N��̔N��1.2���ւ̐������ቺ�Ƃ������������߂Ă����̂ł͂Ȃ��̂��H
���������Ɨ������̊W�����߂Ă����̂��H
������ɂ���A�{��̋c�_�́A90�N��̒�،��������������̏㏸�ɋ��߂�Ƃ�����ʓI�ȕ��͂��A��ƂȂ��Ă���B
��������͌��_�͂����炩�ł���B
���Ȃ킿�A�u���������̓����Y���㏸�Ɍ������������ւƐL�k�I�ɕω�������ƂƂ��ɁA�]���ȏ�ɘJ���͂̎Y�ƊԈړ��𑣂�������Ƃ�K�v������v�Ɓip.21�j
����ɂ������A��2�͂́A�ᔻ�I�ł���B
�u2�� ���{�o�ς̒�����͍\����肪�������|�Y�ƍ\�������s�ǐ��̔ᔻ�I�����|�@�@�@������v
�@�����Œ��ڂ����p�ꂾ�����܂����������Ă������B
����{�X�g�b�N�Ƃ����{���I���Y�v�f�ł͂Ȃ����̣�Ƃ�����`(p.42)�A�����ɂ�����u�o�ς��K�v�ɉ����đ��������邱�Ƃ̂ł��Ȃ������ł���{���I���Y�v�f�Ƃ��Ă̘J���́v�Ƃ�����`�ip.43�j
�ł���B
�@�ߑ�o�ϊw�ł́A�u�{���I���Y�v�f�v���ǂ������Ӗ��Ɏg���Ă��邩�B�L��t�E�w�o�ώ��T�x�Ŋm�F���Ă����ƁA�u���̐��Y�ɗp������o�ώ������Ȃ킿�J���E�y�n�E���{�͈�ʂɐ��Y�v�f�ƌĂ�邪�C���̂������{���������J���Ɠy�n�i��̎��R���܂ށj��{���I���Y�v�f�Ƃ����B���Y���ꂽ���Y��i�Ƃ��Ă̎��{�܂��͎��{���ɑ���p��v�ƁB
����GDP����ݐ��������Z�肷���ŁA�u���{�X�g�b�N�Ƃ����{���I���Y�v�f�ł͂Ȃ����̂��܂���ݐ�����𐄌v�v����͖̂�肾�ƌ����̂ł���i��.42�j�B����ɂ������āAGDP�M���b�v���邢�͐��ݐ������𐄌v������@�Ƃ��ẮA�u�o�ς��K�v�ɉ����đ��������邱�Ƃ̂ł��Ȃ������ł���{���I���Y�v�f�Ƃ��Ă̘J���͂Ɋ�Â��Đ���GDP���l����ƌ����A�I�[�N���@����p�������v���@�v���̗p���ׂ����ƌ����B�����A���̕��@��I�����邱�ƂŁA�Ȃɂ��킩��̂��H
Krugman(1998)(p.168)�ł́A��I�[�N���@���Ɋ�Â��āA1998�N���̓��{�̃f�t���M���b�v��(����GDP�ɂ�������f�t���M���b�v�̔䗦)��10�����x�Ɛ��肵�Ă��飂Ɓip.44�j.
������A�ǂ��Ȃ�Ƃ����̂��H��������̐^���͉����Ƃ����̂��A���̊̐S�̂��Ƃ͂�����Ă��Ȃ��B
�����A��S�@�����v�s���̌��ʂƂ��Ă̋[���I�\����裂Ƃ����^�C�g�����炵�Ă��A�����v�s���Ɍ��������Ƃ߂Ă��邱�Ƃ͂킩��B
�Ȃ��A�����v���s�������i����j�̂��H�@
�u�����v�v�ƌ����Ă��܂��ΊȒP�����A���̂ǂ̂悤�ȕ������ǂ̂悤�Ɍ��������̂��H�@���̋�̓I���l�������A���𖾂̂��߂ɕK�v���Ǝv����B
P�D45
�������A������w�E���邩����ł́A�w�o�ϔ����x(����13�N��)���A���ۓI�Ȍ��t��A�˂邾���ł���B
���Ȃ킿�A�u�ߔN�ɂ�����\���I���Ƃ̑����̑����́A�ٗp�̃~�X�}�b�`�ɂ����̂ƍl������v�Ƃ����̂́A�����ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��ł��낤�B�����������Ƃ��������A���̎��Ƒ����̢��������A���������ǂ̕���ŁA�ǂ̎Y�ƂŁA�ǂ̂悤�ȋK�͂̊�ƌQ�ɂ����Ĕ��������̂��A���̋�̓I���g�������A�u�~�X�}�b�`�v�̋�̑��𖾂炩�ɂ���͂��ł���B�����̌��n�́A�u�ŋߎ��_�ɂ����鎸�Ɨ�5���̂����A�\���I���Ɨ���4����A�z�I���Ɨ���1�����x�ƂȂ��Ă���v�Ƃ��Ă��邪�A���̕������������_���ƃf�[�^�Ƃ����炩�ɂ����K�v������B���ꂪ���@���Ă��邱�Ƃ����͔ᔻ����B
����́A���������p���Ȃ���A�������A�u90�N��ɓ����ċK���ɘa���i���̂̈ˑR�Ƃ��Ďc����I�K���A���Ԋ�Ƃ̌o�c������ӎv����V�X�e���̐��x��J�Ȃǁv���w�E���Ă��邪�A���������v����80�N��̔N4�����ς���90�N��̔N1���ւ̎���GDP��������3�����̒ቺ�������炵���Ƃ́A�ƂĂ��M���������A�Ƃ����B
�@���������A80�N��̔N����4���̐��������\�������v���͉����H�@���̗v�����ǂ̂悤�ɐ��x��J���Ă���̂��H���ꂪ�����炩�ɂ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�@���Ԋ�Ƃ̌o�c�����̂����Ȃ镨�������ɏƉ����Ȃ��Ȃ�A�ӎv����V�X�e���̂ǂ̂悤�Ȑ��x��J��90�N��ɋN�����̂��H�@�̐S�Ȃ��Ƃ����m�ɂ���Ă��Ȃ��Ƃ��낪���ł��낤�B
�����������v�����͂��������Ă��Ȃ��B�ɂ�������炸�A��P��I�ȑ����v�s�����������̌������ƍl����B������v��̒����������A�Y�ƕ����n��̌ٗp�~�X�}�b�`���E�s���𖾂炩�ɂ���͂������A���̋�̓I�ȕ��͂͂Ȃ��B
P�D47
����(2002)���Q�Ƃ��A�u�č��ɂ����Č���ꂽ1990�N��㔼�ɂ����������̐i�W�Ɛ��Y���̐L�ї��㏸�Ƃ������ۂ͓��{�ɂ����Ă��N�����Ă���v���Ƃ��������Ă���Ƃ��A�u90�N��㔼�̓��{�ɂ����ẮA��ʓI�ʔO�Ƃ͈قȂ�A���Y���͏㏸���A�������͊g�債���v�Ƃ����B
�����A���́A�u�������v���ǂ̂悤�Ɋg�債�����Ƃ������Ƃł��낤�B���Ȃ킿�}���ȋ����g�傪�A���v�̌@��N�����ɑΉ����Ȃ��ꍇ�A�����Ǝ��v�̃M���b�v����������B
�������A���{�̎���GDP�������͒ቺ���������B�����\�͂̊g��ɔ������v�g�傪�S�̂Ƃ��Ă͔������Ȃ������B����͎����Ƃ��Ă��A������v���k���������磂ƁA���ʂ����������Ă݂Ă��A��̓I���g�͂܂������킩��Ȃ��B�Ȃ��A�ǂ̂悤�ȕ���ł̎��v�������A����ɂ�������v�g��̌��ʂ���������قǂ̑傫���������̂��H�@����͐������Ȃ��B
��̓I�Ȏw�E�́A���{�o�ϐV��(2001)�L���̈��p�ɂ̂ݎ�����Ă���B���Ȃ킿�A����݁A�s���Y�A���ʂ̕s�U�O�Ǝ�̑ؗ���Ƃ����Y�ƍ\���̒����s�ǖ��A�ƁB
�Ƃ��낪�A�Ȃ����Ƃ������R�ƃf�[�^�Ɋ�Â������Ȃ��ɁA���������s�U�O�Ǝ�̑ؗ��Ƃ������́A�u�K�������Y�ƍ\�������s�ǂ̌����ł���Ƃ͂����Ȃ��v�Ƃ��A�ނ���A��Y�ƍ\�������̌����ł���A�Z�p�i�����r�D�ʍ\���̕ω����X�����݂��邩����K�����݂��飂ƁB�u�\���s���́A�s��̎����z���@�\�̍�p�������V�O�i���v�ƁB
����ꂪ�m�肽���̂́A���̋�̓I�ȓ��e�ł���B�ǂ̂悤�ȕ���ɉߏ�Ɏ������z������A�ǂ̂悤�ȕ���ɉߏ��Ȏ������z������Ă���̂��A���̋�̓I�w�E�ł���B
����ɂ��ẮAp.48�ŁA�u���́A���{��90�N��ȍ~�ɂ����ẮA�w�s�U�O�Ǝ�x�̂悤�Ȓ���v�Y�����Ȃ��Ȃ��k�������A�ؗ������܂܂ɂȂ��Ă���_�ł���v�ƁB
�@�u����v�Y�Ƃ��Ȃ��Ȃ��k�����Ȃ��v�̂́A����v�ł������c��郁�J�j�Y���������Ă��邩��ł���B���̃��J�j�Y���͉����H�@���ꂪ�m�肽���B�������̐����͂Ȃ��B�����́A�u���̗��R�́A�{���͂��̒���v�Y�Ƃ���J�����̑��̎������z�����Ă����ׂ��������v�Y�Ƃ��\���ɑ��݂��Ă��Ȃ�����ł���v�ƁB
�V����������v�Y�ƣ�̑n�o�������ۑ肾�A���ꂱ���K�v���A�Ƃ����̂͘_���I�ɂ��̂Ƃ��肾�낤�B
���́A�V�Y�Ƃ̑n���Ȃ̂ł���B����͓����ɐV�������v�̔����ł���A�n���ł���B
�Ƃ��낪�A����������������u�n���v���ۑ�Ƃ��Ď����̂ł͂Ȃ��A�����_�ɂƂǂ܂�B���Ȃ킿�A�u���̂悤�ȍ����v�Y�Ƃ������Ȃ��̂́A�o�ς��P��I�ȑ����v�s���̏�Ԃɂ��邩��ł���v�ƁB�܂�A����ł́A���X����Ȃ̂ł���B�@�@
p.49
5 ���͎��v�������������|�{��_���ւ̃R�����g
���̖��̐ݒ�̎d�����g�́A�{���S�̂��т����̂����A���̒P���Ȑݒ�ɖ�肪����悤�Ɏv����B
�T�@�ɂ������邵���_�Ȃǂ��܂߁A90�N�㒷���s��(���)�̐����Ƃ��āA�����I�ȋc�_�́A�݂��Ȃ��B
��U���@�������s�\���������̂�������
�R�́@������؊��ɂ������������̌��ʂɂ��ā@�@�R�ƗI�I�v
4�́@�������90�N��̍����^�c�@�@�@�@�������E��������
�R�́@
�@90�N��ȍ~�̌i�C�z�݂̂Ȃ���A��Ƃ��č�������ɋ��߂�
�@�����A�i�C�̏㏸�Ɖ��~�ɉe�������̓I�ȏ���(�A�����J�̌i�C�����A���������Ȃ�)�����Ȃ薾�m�ɏq�ׂ��Ă���B���ۓI���_�����������P,�Q�͂��A�v�����͂͂��ꂾ����̉����Ă���B
�������A��������̗L�������������鎋�_����́A�����Č��ւ̓��͌����Ă��Ȃ��B
�P�@������̎�v�v���|���v�ʂ������ʂ�
p.82-84�@�u2001�N�x�N���o�ύ����v�i�P�C���Y�o�ϊw�E�����ᔻ�̌��n�j�E�E�E����ݐ��͂̒ቺ����L�[���[�h�E�E�E������������{�o�ς��E�o���Ă������߂ɂ͋����ʂ̋�����}����ݐ����͂������グ�˂Ȃ�Ȃ���u����܂ł̂悤�ɐ��{�x�o���g�債�Ă�������v�����Ă��A���̉����ɂ͂Ȃ�Ȃ��B���ݐ����͂̈����グ�͌o�ύ\�����v��i�߂邱�Ƃɂ���ĉ\�ɂȂ�v�B���{�o�ς̐��ݐ������ɂ��āA�u80�N��O����3�����A�㔼�̃o�u������4���������Ă������A90�N��㔼�ɂ�1�������ɗ�������ł���A�Ɛ��v���Ă���B�v�ݔ������̗������݁A���q���E����ɔ����J���l���̐L�т̓݉��������̔w�i�ɂ���Ƃ���̂����̕��͌��ʂł���B��̂Ƃ���A����Ɉًc�͂Ȃ��v�ƁB
�Q�@������؊��̌i�C�z�ƍ�������
1 �i�C�z�E�E�E�E�}�\3�|1�E�E�E�Q�l�ɂȂ�B
�@
2�@�i�C�ǖʂƍ�������̌���
p.90
(1)91-93�̌i�C���~�ǖʂƍ�������E�E�E�E������o���̎������x���A�܂������͏��K�͂ɂƂǂ܂��Ă����E�E�E��@�ӎ�����r�I���������E�E�E�
(2)94�|96�N�A�i�C�̉E�㏸�ǖʂƍ�������E�E�Ep.93�u���������̊g��𒌂Ƃ�������x�o�̊g�傪���Ȃ�̒��x�i�C�̗������݂�h���A���̊Ԃɖ��Ԏ��v�����X�ɗ͂����Ď���Ɍ_�@�̏㏸���������悤�ɂȂ�Ƃ����A�i�C�̗��z�I�ȓW�J�v
(3)97�|98�N�A�i�C�̍ĉ��~�ƍ�������
�@�u97�N�ɂ��Ă݂�ƁA���I�Œ莑�{�`�����啝�Ƀ}�C�i�X��^�v
p.93-94�@�u97�N����̌i�C���~���A96�N�����ȍ~�̌��������팸����̉e���������Ă���E�E�E�v
p.94 �97�N4������̏���ŗ������グ�i�R����5���j�ɂ���ĕ������㏸��E�E�E�u��������x�o�̐L�ї���96�N��2.4��������97�N�ɂ͂O�D�X���ւƑ傫���ቺ�v
�@�@�@�@�@�u����ŗ��̈����グ�����������}�����A���̂��Ƃ�����GD���������̒ቺ(�i�C�̉��~)�������������ʂ������E�E�E�v
p.96�@�96�N�x�����̌��������}���Ɏn�܂�����Č����A�E�E�E�o�ϐ������̗������݁A�����Či�C�̉��~�������炵���E�E�E��E�E�E�����Č��͕K�R�I�v���ł͂Ȃ������̂��H
p.96�|97�@�A�W�A�o�ϊ�@�A98�N�̗A�o�̗������݁A�ꕔ���Z�@�ւ̌o�c��@�A98�N�̃}�C�i�X����
p.97 �u���̊Ԃ̍�������̑Ή�������ƁA�Ή��̒x��ƃ`�O�n�O�����ڂɕt���B���ꂪ�i�C�̗������݂�[�����������Ƃ݂���E�E�E�v
�@�@�@��傫�ȏ�Q�ƂȂ����̂́A�w�����\�����v�@�x�ł���B97�N�x�ُ̋k�E�����Č��^�\�Z�̐������āA98�N�x�ȍ~�̍Ώo���������}�����Ă����ƌ�����|�́w�����\�����v�@�x�E�E�E�u98�N�x�\�Z�ẮA�w�����\�����v�@�x�Ɋ�Â���ʍΏo��O�N���A11�N�Ԃ�̃}�C�i�X�Ƃ���ُk�^�E�E�E��͌����
�E �E�E�ƌ������]�������A
�@(�S)�X�X~�Q�O�O�O�N�A�i�C�̉E�㏸�ǖʂƍ�������
�@p.98�@�@�u�Ƃ�����A99�N���ȍ~�A�i�C�̓o�u���o�ϔj��ȍ~��x�ڂ̉E�㏸�ǖʂɓ���B�X�V�N����X�W�N�ɓq���Ă̑�^�̌i�C��A�����ĂX�X�N�ɓ����Ă��Ȃ��������ꂽ���͂Ȍi�C��|�o�ϐV����v(�������t,�X�X�N�P�P���P�P���A���ƋK�͂P�W���~�A���������U�E�W���~�Ȃ�)�̌��ʂ������Ă̂��Ƃł���v�ƁB
�@�@�@�@�E�E�E�������A����ł́A���ƍ������Č��͂ǂ��Ȃ�̂��H
�@�@�u�����ւ̊�^�x���[���ƂȂ��Ă��܂������I���v�̑����ɑ����āA�Q�O�O�O�N�x�̌o�ϐ����Ɋ�^�����̂́A�A�o�Ɩ��Ԏ��v�̑����ł���B�i�C�E�㏸�̐i�s�ƂƂ��ɁA���̎�������I���v���疯�Ԏ��v(�ƗA�o)�ɒu�������ƌ����A�X�S�|�X�U�N���Ɠ��l�̍D�܂����]���������ł��݂ĂƂ��v�ƁB
(5)�Q�O�O�P�N�A�R�x�ڂ̌i�C���~�ƍ�������
�@��i�C�̉E�㏸�͂���߂ĒZ���ԂŏI�����A���{�o�ς�2000�N11���ȍ~�A�o�u���j��ȍ~3�x�ڂ̉��~�ǖʓ��肷��B�E�E�E�A�����J�i�C�̎����|����ɋN�����Ă̗A�o�̗������݁|�ɂ��̎�������߂邱�Ƃ��ł���B�
(6)�@2002�N�ȍ~�A����߂Ċɂ₩�Ȍi�C�ƍ�������
p,100�|101�@�u�ɒ����̐i�W�A�A�����J�o�ς̎�̎�������(�ɂ��A�o�̑���)�ɂ��A�i�C��200���N�ɂ���߂Ċɂ₩�ɉɓ]�������A���̉��x�͂���߂Ċɂ₩�E�E�E�������͂�A���̊Ԃ���������(�x�o�}������{�Ƃ��鐭��)�̌��ʂł���(���тɊ�Ɠ|�Y���A���Ƒ��������炷�s�Ǎ������̑��i�Ƃ����f�t������𐭕{�������ĂƂ��Ă��邱�Ƃ̌��ʂł�����)�E�E�E�v
�R�@��̕⑫�@
�@��������̌��ʂ�ے�I�Ɍ��錩���ɂ���
�@���������̏搔���ʂɂ��āE�E�E�E�o�ϊ�撡�̢���E�o�σ��f������ɉ����鐄�v�Љ�
���̑��E�]�܂�����������ɂ���
p.104�@�@�Ƃ���ׂ��ł͂Ȃ���������i�����p�n�̐�s�擾�A�ݐi�ŗ��̈�����������̂Ƃ��鏊�����ŁA�@�l�Ō��ŁA�n��U�����̌�t�A���X�j
�@�@�̂�Ηǂ���������i����Ō��݂����̑�\�I�Ȃ��̂ł���B���̂ق��A�����̑����A���T�[�r�X�E�����T�[�r�X�E��ÃT�[�r�X�̏[���̂��߂̐E���̑����A���邢�͗\�Z�̊g�[�ȂǁA����E�����̂��߂݂̂Ȃ炸�A�i�C��Ƃ��ėL���ł������낤������������j�A�ƁB
�R�ƒ��w��\�����v��Ƃ������z�x�i��g���X�A2001�N�j���2�́@�i�C�������������͕̂s�Ǎ���肩����Q�Ƃ���A�ƁB��s�Ǎ����ł͂Ȃ��B��������̎��s�ł��飂Ƃ����̂��R�Ƃ̌��_�B
�S�@���_�@
p.105
�u�X�O�N��̒�����؊��́A97�N�łQ�����ĂƂ炦��ׂ��E�E�E�X�O�N��O���A���Ȃ킿�X�V�N���܂ŁE�E�E�o�u�������s���Ƃ�������̉��E�E�E�X�O�N��㔼�ȍ~�A���Ȃ킿�X�V�N�ȍ~�ŋ߂܂ł��A�V�������؊���Ƃ��ĂƂ炦��E�E�E�v
�u�X�O�N��O���̔N���ώ����������͂P�E�T��(�X�P�N��X�U�N)�Ɗm���ɒႢ���A����͍��������o�u�����̔����Ƃ��ė����ł���E�E�E�o�u�����ƍ��Z���Ă̐������͂R�D�Q��(�W�T�N��X�U�N)�ł���A�o�u�����ȑO�|�W�O�N��O���|�̓��{�o�ς̐������ƂقƂ�Ǖς��Ȃ��E�E�E����A�X�O�N��㔼�̔N���ώ����������͂O�D�T��(�X�V�N��Q�O�O�Q�N)�Ȃ����A�O�D�V��(�X�U�N��Q�O�O�Q�N)�ł���A�E�E�E���{�o�ς̖{���̒�͂X�V�N����n�܂����E�E�E�v
p.105�u�X�O�N��O���ɂ�����A�o�u���i�C�̔����s������̉��ɂ������g���I�ȍ����������傫�Ȍ������������E�E�E�E�v
p.106�u90�N��㔼�|97�N���ȍ~�|�����{�o�ς̢��أ�������炵���̂́A��������ُ̋k�^�ւ̋}�]���ł���B�����āA�������s���̖K��̂��ƁA��������͍Ăъg���^�ւƓ]�����Či�C�̎�v���ƂȂ邪�A�A�����J�o�ς̎����ƂقƂ�Ǔ������ɂӂ����ыُk�^�ւƓ]�����ē��{�o�ς̢��أ�������邱�ƂɂȂ�v
�u�O�����̊g���^�̍�������Ƃ��̌��ʂɂ��قǖ��͂Ȃ��A�㔼���̎��k�^�̂���ɑ傫�Ȗ�肪�������v
����{�o�ς̢��أ���A�����������Ԏ��̊g����A96�|97�N���ɂ�������������̌���ɂ��̈������o���飂Ƃ����̂��R�Ƃ̌��_�B
�@�ǂ̂悤�ȍ������L���ł���A�ǂ̂悤�ȍ�����������I����̉����ɂȂ������̂��A�Ƃ�������̓I���͂��K�v�ł��낤�B
4��
�������90�N��̍����^�c�@�@�@�@�������E��������
�P�@�͂��߂�
�@
�Q�@�i�C��Ƃ��Ă̗L����
p.112 �o�ϊ�撡�Ȃ�9��ނ̓��v����(�}�\4�|1)�܂��A�����I�Ɍ��Č��悤�Ƃ��錩�n
p.113�@�u�����̌����ł́A������ɂ����Ă������x�o�̊g��⌸�ł�GDP�▯���Ƀv���X�̉e���������炷���Ƃ��m�F����A�������i�C�̉��x���Ɉ��̖������͂����Ă������Ƃ�������B�������Ȃ���A�E�E�E�E��������̐�����ʂ�90�N��i���邢��80�N��㔼�ȍ~�j�ɒቺ�������Ƃ�������Ă���B��������̌��ʂɂ��ẮA�搔���ʂ̑傫���ƂȂ��Ō��ʂ̎��������d�v�ł��邪�A�}�\4�|1�Ɍf�����e�����ɂ������������̕ύX�ɂ������C�m�x�[�V�����ɂ�������GDP���̔������݂�ƁA4����(1�N)�Ȃ���6�l����(1�E5�N)���x�Ő�����ʂ��������Ă���A���ʂ̎������Ƃ����ϓ_�������������͗͋������������̂ł��������Ƃ�������B���̌��ʂ́A�w�����ɂ��i�C�h������߂�Ƃ����Ɍi�C���������Ă��܂��x�Ƃ����ꕔ�̐ϋɍ��������_�҂̎w�E�𗠕t���Ă���B
���̂悤�ɁA��������̌��ʂ�����I�Ŏ������Ɍ��������̂ƂȂ��Ă��闝�R�Ƃ��ẮA��������̖����ɑ���g�y���ʂ��������A�����o�����i�C�̎����I�ȉɌ��т����̂ɂȂ��Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ��l�����[9]���B�v
p�D114�@�}�\4�|2�@�C���p���X����
�@�@1981�N��2�l����~2001�N���l�����E�E�E���I���Œ莑�{�`��[10]�A���ԑ��Œ莑�{�`���A���ԍŏI����x�o�AGDP�f�t���[�^�[�A����у}�l�[�T�v���C�iM2+CD9�j(���c)��5�ϐ�����Ȃ�VAR���f���𐄒肵�A��������Ƌ��Z����̐����ύX�����ԏ���Ɩ��ԓ����ɗ^����e��(���I���Œ莑�{�`������у}�l�[�T�v���C�ɌW���C�m�x�[�V�����ɑ��閯�ԑ��Œ莑�{�`���҂�і��ԍŏI����x�o�̃C���p���X����)
p.115�@�u����ɂ��ƁA���������̊g��͖��ԏ���ɑ��Ĉꎞ�I�Ƀv���X�̉e����^������̂́A���̌��ʂ͔��N�Ȃ���1�N���x�ŋ}���Ɍ������Ă���B����ɑ��A�}�l�[�T�v���C�̑��������ԏ���ɗ^������ʂ́A���Ԃ̌o�߂ɂ�Ēቺ���Ă������̂́A�����I�ł���B�܂��A���ԓ����ɑ���e���ɂ��ẮA�}�l�[�T�v���C�̑����ɔ������ԓ����̑�����1�N���x�Ńs�[�N�A�E�g������̂�20�l������ł��s�[�N���̔������x�̌��ʂ��c���Ă���̂ɂ������A���������̊g��͌��ʂ��قƂ�ǔF�߂�ꂸ[11]�A1�N�����̒Z���ł͖��ԓ����ɑ��Ăނ���}�C�i�X�̉e����^���Ă��邱�Ƃ�������B�v
p�D115�|116 �u���ԏ���Ɩ��ԓ����̂�����ɂ��Ă���������̊�^�����Z����ɔ�ׂď����Ȃ��̂ɂƂǂ܂��Ă���E�E�E�B�ȏ�̌��ʂ́A�w��������̖����ɑ���g�y���ʂ����������Ƃ��A��������̌i�C��Ƃ��Ă̗L����������I�Ȃ��̂ɂ��Ă���x�Ƃ����������x��������́v
p.116�@�u��������̌��ʂ�����I�Ȃ��̂ł���Ƃ��������́A���j�I���U�����𗘗p�������͂ɂ����Ă��m�F�����B�v
p.117�@��ȏ�̓_���܂Ƃ߂�ƁA��������͌i�C��Ƃ��Ă܂����������ł͂Ȃ��������̂́A���̌��ʂ�80�N��㔼�Ȃ���90�N��ɒቺ�����\���������A�g���I�ȍ����^�c�ɂ���Či�C���v�邱�Ƃ��ł���ق����̐�����ʂ͑傫�Ȃ��̂ł͂Ȃ������Ƃ������ƂɂȂ�B���������āA�����o�����s�\���ł��������Ƃ�������̌����ł���ƌ��������͎x������Ȃ����̂Ɣ��f�����
�R�@�����\�����v�̉e��
�@�����\�����v�A����ő��łȂǂ̉e���Ɋւ��āA�{�͂̎��M�҂͌i�C�ւ̃}�C�i�X�̉e����Ⴍ�]���B
�@���_�I�ɂ́A�����Z�@�ւ̔j�]�ȂǁAp.121�u�X�V�N�H�ɐ��������Z�V�X�e���̕s���艻�ɔ����i�����̈������i�C�ɑ傫�ȉe����^�����v�ƁB
�@�������A�����Z�@�ւ̔j�]�́A�ȂɂɗR�����邩�H�@�����ɍ����\�����v�̉e���͂Ȃ��Ƃ����邩�H
�@�����\�����v�̂��߂́u���������v�}���́A���Z�@�ւ̑ݏo��̌o�c�s�U���g�債�A���݉�������Ƃ����o�H�����ǂ��āA���Z�@�ւ̔j�]�Ɍ��т����̂ł͂Ȃ��������H
�@�y�E���ݓ��̘V�܂̔j�Y�́A�܂��ɢ����������̔�������A�ߏ艻�ƊW����ł��낤�B
���������Ӗ��ŁA���̐߂̎咣�́A�����I�ł͂Ȃ��B
�S�@�\�������̒x��Ɣ�P�C���Y����
p.122 �u90�N��̍����^�c�͒Z���I�Ȏ���ɕ肪���ŁA�����̎��_���������̂ł������B�o�ϑ�̍���ɍۂ��ẮA�������܂���̢�K�ͣ���d������A�����颐^������߂���c�_�������Ȃ���܂ł͌o�ϑ�̎��Ƒ��z���A����Ȍ�͢�^����̑傫�����o�ϑ�̌��ʂ�]�����邤���ł̏d�v�ȃ|�C���g�ƂȂ����B�o�ϑ�̓��e�̌���ɂ��ẮA�i�C�ɑ��频���������d�v�ȑI����Ƃ���A�o�ϑ�ɐ��荞�܂�����Ƃ̌������͂����Όy�����ꂽ�v�ƁB
�@�[�l�R���~�ς̑�^�����������A�������āA�s����Y�I�������������Ƃ������������N�������Ƃ���A��������̂�����Ƃ��Ă͎��s�ł���B
�u���̂悤�ȍ����^�c�́A�i�C���ꎞ�I�ɉ��x��������ʂ��������Ƃ��Ă��A�{���Ȃ����ׂ��\��������x�点��Ƃ����R�X�g�����̂ł������v�Ƃ����]���́A���̂�����őÓ��ł��낤�B
���ŁA�u�ݎ��ɂ킽��i�C��ɂ����ẮA�������Ƃ����̒��S�I�Ȗ������ʂ����Ă������A�]���^�̌������Ƃ̃X�g�b�N����(���Y�͌���)��90�N��ɓ����Ē������ቺ�������Ƃ܂���A�������Ƃ𒆐S�Ƃ��������x�o�̊g��͌������̒Ⴂ���̂ł�����[12]�v�ƁB
�@�u���̂悤�Ȍ������Ƃ̊g��́A���Ƃɂ�����A�Ƌ@����g�傳���A�ٗp��Ƃ��Ă͈��̖������ʂ������Ƃ����邪�A���Ƃ̐��Y�����ቺ����Ȃ��ŏA�ƎҐ��̑��������������Ƃ́A�{������ׂ��\�������̕����Ƃ͋t�̓����ł�����[13]�v�ƁB
P.122-123�@��i�C��Ƃ��Ă̍�������̐ϋɓI�Ȋ��p���咣����_�҂���͢�s���̌����͎��v�s���ɂ���̂�����A���v�ʂ̑�Ƃ��č����[�u���u����͓̂��R�ł��飂Ƃ̎咣���J��Ԃ��Ȃ���Ă������A���̎咣�̑Ó����f���邽�߂ɂ́A����v�s���̌����͉�����Ƃ������Ƃ��l���Č���K�v������B�Ⴆ�A�ߔN�ɂ��������̐L�єY�݂̌����Ƃ��āA������s����Ƃ������Ƃ��w�E����邱�Ƃ����邪�A���̂悤�ȏꍇ�ɂ͈ꎞ�I�Ȏ��v�lj�����u���Ă��i�C��Ƃ��ď\���Ȑ��ʂ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���̏ꍇ�ɕK�v�Ȃ̂́A�����s���̌����ɂȂ��Ă���ٗp��N���A�������̏������ʂ������P�����鐧�x���v�����{���邱���ł���A�����͌i�C����d������_�҂������Δᔻ�̑ΏۂƂ��颍\�����v��ɑ����鐭��ł���B�
P�D124�u�i�C��̖��ڂŏ����̐��Y������ɂȂ���Ȃ�������Ȍ������Ƃ��s����ƁA�o�ϑS�̂Ƃ��Ă��̕������������p�\�Ȏ������������Ă��܂����߁A�����s�̏������S�������ӎ�����āA�����_�̏���������Ă��܂��\��������B�܂��A�{���ł���Ό����_�̑��łɂ���đ[�u�����ׂ��������S�������s�ɂ���Đ摗�肳��A�߂�����������@�������̕��ƂȂ鋰�ꂪ����ꍇ�A�i�C�h����Ƃ��Č��ł����{����Ă��A����ɂ���Ă������č����j�]�̃��X�N�����܂�A���̃R�X�g�̕�����苭���ӎ������悤�ɂȂ邽�߁A���ł��ނ������̌��ۂ������炵�Ă��܂����Ƃ�����B���ꂪ��������̔�P�C���Y���ʂƂ����錻�ۂł���B[14]�v
�@
�T�@����v�z�̍\�����v
�@���ȏ��I�ȃP�C���Y�I��������̔ᔻ
�@�90�N��ȍ~�̒��������������ō����^�c�i�̎��s�j�̓}�C�i�[�ȗv���ɉ߂��Ȃ������ɂ�������炸�A���̌�����ُk�I�ȣ�����^�c�ɋ��߂錩���͈ˑR�Ƃ��č��������飂Ƃ��āA����ɔᔻ�I�B
p.126 ����{�Ƃ����ǂ��ʂ��Ă��ȗ\�Z��������Đ���^�c���s�����Ƃ͂ł��Ȃ���ƁB�E�E�E������Ԏ��̃T�X�e�i�r���e�B�ɑ��錜�O����A�����o�����S�O����Ă��錻��
�@�@�u�g���I�ȍ�������͂����\��������x�点������ɍ�p�������ł���v�E�E�E��d�_����𒆐S�ɒlj����Ȃ��ꂽ�͂��̍����x�o���A���ۂɂ͏]���^�̌������Ƃ��T�|�[�g���邱�ƂɎg���Ă��܂���Ƃ�������萫
p.127 �E�E�E����̈Ӗ��ŁA��s�i�C����������o����Ƃ����i�C�[�u�Ȑ���v�z�̍\�����v���Ђ��Â��s���Ă������Ƃ��A�d�v�ȉۑ裂ƁB
�u�����s���̌����ɂȂ��Ă���ٗp��N���A�������̏������ʂ������P�����鐧�x���v�����{���邱�Ɓv�Ƃ����̂��ϋɓI�咣�����A���āA�ٗp�Ɋւ��鐧�x���v�Ƃ́H�N�ࢉ��v��̋�̓I������́H
�U�@���_
�@ ��������̌i�C�h�����ʂ͌���I
�A ����ŗ��̈����グ������\�����v�Ɍ��������g�݂��f����̌i�C��ނ������炵���Ƃ��������͎x������Ȃ�
�B �ߑ�Ȍ����s�A�������S�̏����ւ̐摗��Ȃǂ̌i�C��̔�P�C���Y����
�R�Ƃ̃R�����g�E���W���C���_�[
����ɑ��钆���̍X�Ȃ郊�W���C���_�[
��V���@���Z�ɘa�ɂ���ɂӂ݂��ނׂ��������̂�
5��
���Z����̎��s��������������@���c���E�ѓc�f�V
6�� �s�\���ȋ��Z�ɘa��������̌������@�n�ӓw
5��
�@�P�@������̌����ɂ��Ă̓�̍l����
p.149 �u90�N��ȍ~�̓��{�o�ς̃p�t�H�[�}���X�́A���ς�������GDP�̐�������1���O��ɂƂǂ܂������Ƃ�A��т��Ď��Ɨ����㏸�������ƂȂǁA��v�ȃ}�N���o�ώw�W�ł݂邩����A�ߋ��̎��тƔ�r���Ă��A���邢�͑��̐�i�o�Ϗ����Ɣ�r���Ă��A�������s�����Ȃ��́v
�@�u�ɏz��ݔ������z�ƌĂ�Ă���ʏ�̌i�C�z�ł���A10�N���̒����ɂ킽�肱�̂悤�ȏ��������邱�Ƃ͓���v
p.150
�@�\���h�E�E�E�\�����̑��݁A90�N��̌o�ϒ�ɂƂ��Ă��ꂪ��v���A�Ƃ���l�X
�@�{�͂ɗ���E�E�E�u��X���}�N���o�ϐ���̎��s��������̎�v���ł���ƍl���Ă���v�ƁB������ɂ킽���Ă��镨���Ǝ��Y���i�̉����̎����A�܂�f�t���Ƃ��������́A���Z����̎��s��������̌����ł��邱�Ƃm�Ɏ����Ă��飂ƁB
���̌����̕K�R�I���ʂƂ��āA����Z����̉^�p�����{�I�ɓ]�����f�t����j�~���A�}�C���h�ȃC���t���������������ƁA���Ȃ킿���t���[�V����(���t��)��������s�������Ƃ��A���������E�o���邽�߂ɂ͌������Ƃ̂ł��Ȃ�������ƁB
�@��}�C���h�ȃC���t�����������风�i�E��@�͉����H�@���̗L�����̏ؖ��́H
p.172
5
������
��ȏ�Ő��������悤�ɁA10�N���đ����Ă��錻����{�o�ς̒���������A���̕����I�Ȏ��Ԃ̒����������ɂ��Ĕ�ݕ��I�Ȍ��ۂł���ƒf�肷�鍪���͔���ł���B����ɑ��āA���Z����̎��s�������ɂ킽��o�ς̒���ƃf�t���������N����������͗��j�I�ɂ��m�F����Ă���B�����āA���Z���[������{�ɓK�p���ĕ]�������݂�ƁA�����Ƃ���90�N�ȍ~�قڈ�т��ċ��Z������������ߓI�ȃX�^���X���ێ����Ă������Ƃ�������B����ɁA�Ó��Ǝv�������Z���[���i�}�b�J�����E���[���j�����ۂɓ��{�o�ςɓK�p����Ă����ꍇ�A����GDP�̐����Ɛ����́A���тɔ�r���Ė��m�Ɉ��艻����邱�Ƃ��A�P���ȃ��f���̃V�~�����[�V�����Ŋm�F�ł�����ƁB
�@
�@�����������Ƃ���ƁA����ȂɊȒP�Ȃ��Ƃ��Ȃ����ⓖ�ǂɂ͂킩��Ȃ��̂��i�ł��Ȃ��̂��j�H
�@���Ȃ킿�A���Z���[���i�}�b�J�����E���[���j�́A�Ȃ����{�o�ςɓK�p����Ȃ������̂��H
�@���̖{����Ɏ��܂ŁA�}�b�J�����E���[���Ƃ͉�����m��Ȃ������̂ŁA�L��t�E�o�ώ��T�������Č����B�������A���o���ꌟ���ł͂łĂ��Ȃ������B�{�͂̎��M�҂��炷��A10�N�ȏ�ɂ킽���ē���ӔC�҂����́A�u���Z���[���i�}�b�J�����E���[���j�v��m��������A�K�p���l���Ȃ������A�Ƃ������ƂɂȂ�̂��낤���H
����ł́A�}�b�J�����E���[���Ƃ͉����H
�S�@���Z����ƒ�����̎��ؓI�W�A�iii�j�}�b�J�����E���[���̐������݂邱�Ƃɂ��悤�B
p.164�u �ݕ��ʂ��畨���Ɏ��郁�J�j�Y�����u���b�N�{�b�N�X�ɕ��u[15]�����Ƃ��Ă��A���łɏq�ׂ��悤�ɁA�i�g�����h�C���Ȃǂ��{������ɂ́j���W�̐����������Ƃ͔ے�ł��Ȃ��v�ƁB�ݕ��ʂƕ����̊W�ɂ����āA���W����������A�Ƃ������Ƃɂق��Ȃ�Ȃ��B
�@�����A����͂Ȃ����B���̐����́i�����Ȃ��Ƃ������ɂ́j�Ȃ��B�����W�Ƃ��āu���W����������v�Ƃ����킯�ł���B
�u�����ŁA����GDP�ƃx�[�X�}�l�[[16]�̊Ԃɔ��W�̐������邱�Ƃ����肵�Ȃ���A�������萔�̉ϐ����l�������̂��A�}�b�J�����E���[���ł���Ƃ�����v�ƁB
�@
�@����GDP�����i���Y�̑��ʂƂ��̌�����\�����邩����ŁA�܂����̌��������ʎ�i�ɂ�銄�����A�M�p���x�̔��B�x�ɂ���Ă��鎞������n��ɂ����đ��ΓI�Ɋm��ł�����̂ł���Ƃ���AGDP�̕ω��A�M�p���x�̕ω��ɂƂ��Ȃ��āA���W���ω����Ă����͓̂��R�ł��낤�B���̔w��ɂ���̂́A������A���i���Y�̑��ʂ₻�̉ݕ��ւ̓]�����x��A���̑��x���K�肷��M�p���x�̔��B�x�����Ȃǂł��낤�B
�@�Ƃ���ŁA�}�b�J�����E���[���͂ǂ̂悤�ɓK�p����̂��H
p.164-165�u���Ȃ킿�A�x�[�X�}�l�[���������x�[�X�}�l�[�̗��ʑ��x�̒ቺ+����GDP������������������̂Ɖ��肵�A����GDP�������ɖڕW�l��^���A����Ɛ����I�ȃx�[�X�}�l�[���������������邱�Ƃ�������̃��[���Ƃ��悤�Ƃ������̂��v�ƁB
�@�����āA�u�������{�o�ςɓK�p���Č���ƁA�e�C���[�E���[����p�����ꍇ�ɓ������90�N��O���ɂ�����ߏ�ȋ��Z�������߂Ƃ����������ʂ邱�Ƃ��ł���v�ƁB�e�C���[�E���[���̓K�p�ɂ����Z����ւ̐f�f�i����j�͂��Ƃł݂邱�Ƃɂ��āA�c�_�̑���������Ǝ��̂悤�ɂȂ��Ă���B
p.165�u�}�\5�|1�͖���GDP�̖����N��5��������ڕW�Ƃ���}�b�J�����E���[���ɏ]�����P�[�X�ŁA�K�v�Ƃ����x�[�X�}�l�[�̑������ƁA���̎��ђl���r���Ă���v�ƁB
�@�������A�����N��5�������Ƃ����̂́A���������ǂ̂悤�ɂ��Đ����������ڕW�Ȃ̂��낤���H�@���̌����I�����͉��Ȃ̂��H�@���ƂȂ��Ă���̂́A80�N��܂ł̔N��3���ɔ�ׂāA90�N��h��1���ɒ�����Ă��邱�Ƃł͂Ȃ������̂��H�@�Ȃ��˔@�A�T�����ڕW�ɂȂ�̂��H
�����I�������s���̖ڕW�l�Ōo�ϐ���E���Z������]�X������A�^�c���Ă����̂��낤���H���{�I�^�₪�N���B���̂悤�ȁu�����N��5�������v�Ƃ����ڕW�ɏƂ炵�āA���тƔ�ׂ邱�Ƃɂǂ̂悤�ȈӖ�������̂��낤���H�@����͖��Ȃ��Ƃ���A���̂悤�ȕ��͂ɂȂ�B
�u����ɂ��A80�N��̃x�[�X�}�l�[�������́A�㔼�̈ꎞ���������قڃ}�b�J�����E���[���ƌn���I�Ȍ덷���������ɐ��ڂ��Ă���v�ƁB�������A�܂���80�N�ケ���́A���̌㔼���ɂ�����o�u����K�R�������̂ł͂Ȃ��̂��H80�N��x�[�X�}�l�[�̑������́A�o�u���o����̌��݂���]�����鎞�A�ʂ����đÓ��Ȃ̂��H�@���̋^��͂��Ă����āA���̕��͂�����ƁA�u90�N��O�����ɂ̓x�[�X�}�l�[�̑������͂��悻6�����x�ňێ������ׂ��ł��������A���ۂɂ͕��ς���3�����x�̐L�тɂƂǂ܂��Ă����ɂ����Ȃ��̂ł���v�ƁB
�����A���̍��́A���₪�ǂ̂悤�Ȏ�i�Ŗ��ߍ��킹��悩�����ƌ����̂��H�@���̊̐S�ȋ�̍�����Ă��Ȃ��B�x�[�X�}�l�[���������i�͉����H�@�x�[�X�}�l�[�𑝂₷���v���̂ǂ���ǂ̂悤�ɓ���͑��삵����̂��H�@���ꂪ������Ă��Ȃ��B�o�ϖ@���ɏ]�����������ł̃x�[�X�}�l�[�̑�����i�Ƃ͉��Ȃ̂��H
����͎�����Ȃ��܂܁A���̂悤�ȓ���ᔻ�������B
�u����ɁA��K�͂ȋ��Z�ɘa�Ɉڍs�����Ƃ����Ă���95�N�ȍ~�ɂ́A���łɁiGDP�f�t���[�^�[�ł݂�Ɓj�f�t�����n�܂��Ă���A���ڋ����̑����ɂ���Či�C�Ɏh���I�Ȍ��ʂ����邱�Ƃ͍���Ȃ��̂ɂȂ��Ă������A�ˑR�Ƃ��ē��{��s�́u�펯�I�v���x���ł̋��Z�ɘa�����s���Ă��Ȃ����Ă��炸�A�f�t���̌����}���ɏ㏸�����邱�Ƃ��K�v�ɂȂ��Ă����x�[�X�}�l�[�������ɁA�����̃x�[�X�}�l�[�������͂܂������ǂ����Ă��Ȃ��������Ƃ�������v�ƁB
�u�x�[�X�}�l�[�𑝂₹�Όo�ϐ������B���ł���v�ƌ������ꂩ�炷��A�f�t�����Ƀx�[�X�}�l�[���u�}���Ɂv�㏸�����邱�Ƃ��u�K�v�v�Ƃ����c�_�́A���藧�B�����A��̓I�ɂǂ�����̂��H��������̂��H
���̏͂̎��M�҂���т����ȃf�[�^���A���̏͂̎��M�ҍ쐬�́u�}�\5�|1�@�}�b�J�����E���[���ƌ����̃x�[�X�}�l�[�������v�ip.164�j�ɂłĂ���B���Ȃ킿�A2000�NQ1�̃x�[�X�}�l�[�̌�����A�����I�ɋ��s���ꂽ�ƌ�����ω��A���Ȃ킿2002�NQ1�ɂ����Ă��̂������u�����x�[�X�}�l�[�������v��������̂ł���B�������A2002�NQ1�Ȍ�A�u�����x�[�X�}�l�[�������v�́A�O�L�̋}���ȑ���̋t��p�̂悤�ɁA�������Ă���B���������x�[�X�}�l�[�̗������͂ǂ̂悤�ɕ]������̂��H
�}�b�J�����E���[���̐����Ƃ��̓K�p�Ɋւ����������ނ�����A�o�ύ�����������I�ȉӏ��͂܂������Ȃ��B�i����̐���̑Ó����ɂ��ẮA�����K�v�ł��邪�j
�e�C���[�E���[���Ƃ͉����B
P.163�u�S�@���Z����ƒ�����̎��ؓI�W�v�A�ii�j�e�C���[�E���[���@�����Ă݂悤�B
�@�@�܂��A�u���Z����̕]���v�ŁA�u90�N��̋��Z���A�勰�Q���ɂ�����u���{�ʐ��̎����v�̂Ƃ肱�ɂȂ��Ă����e���̋��Z�������l�ɁA�ߏ�Ɉ������ߓI�Ȃ����ł��������ۂ��f���邽�߂ɂ́A�P�ɋ���������A�}�l�[�T�v���C�̐L�ї��̍�����ώ@���Ă��Ӗ��͂Ȃ��v�Ƃ����B�u�����������Z�I�ȕϐ��̓������A�}�N���o�ς̏��Ɣ�r���đÓ��ł��������ۂ��f����K�v������v�ƁB���������u��Ƃ��č����L���p�����Ă�����̂Ƃ��āA�e�C���[�E���[���ƃ}�b�J�����E���[���Ƃ�����̋��Z���[��������v�ƁB
�@����Ȃɑf���炵���ŏo�̏��Ƃ̂悤�ȃ��[���A�u�����L���p�����Ă���v���[�����A�Ȃ�����͓K�p���Ȃ������̂��H�@�s�v�c�ł���B���Ȃ��Ƃ��A�}�b�J�����E���[���̓K�p�Ɋւ��镶�͂�ǂނ�����́A�L�����͗��_�I�ɏؖ�����Ă��Ȃ��悤�Ɏv����B
p.163-164
�@�u�ii�j�e�C���[�E���[��
�@�@�@���Z����̎�i�ϐ��Ƃ����Z��������p����e�C���[�E���[������{�o�ςɓK�p�����ł������ꂽ���̂̈�ł���n��E���E�{���i2001�j�̌������ʂɂ��A91�N����94�N�܂Łi�́j���ԁA��������i��̓I�ɂ̓R�[�����[�g[17]�j�͓K��������啝�ɏ����Ă������Ƃ��킩���Ă���BGDP�f�t���[�^�[�̑O�N��ł̉������n�܂���94�N�I��育��A�����ĉ~�h�����[�g��79�~�^�h���Ƃ������ȉ~���Ɍ������ċ}�����J�n���钼�O�܂ŁA�e�C���[�E���[���ł͐����������Ȃ��i���ΓI�ȈӖ��ł́j���������Ƃ��Ă������Ƃ����炩�ƂȂ��Ă���v�ƁB
�@�܂�A���_�I�ɂ́A�o�u�������A���Z�������߁A����������ł͂Ȃ��A���������������Ⴍ���Ă����悩�����A�Ƃ����킯�ł���B
�@�������A�o�u���Ƃ͂Ȃ����̂��B�����I�Ȑ��Y�̕K�v�����@�����ߏ蓊���́A�ǂ̂悤�ɂ��Đ��Z�����̂��H�@�o�u�������̍������͕K�R�ł͂Ȃ������̂��H�@�u�K���v�Ƃ́H
�@�Ȃ��A�K������u�啝�ɏ����Ă����v�̂��A���̓���̐������f�̊�b�ɂ����������i���_�I�X�^���X���܂߂āj�͉����H�@���ꂱ�����𖾂���Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B�����A����͂����ɂ݂͂��Ȃ��B�u�K��������啝�ɏ����Ă����v�Ƃ����f�肪���邾���ł���B�ᔻ�Ƃ��Ă͕s�\���ł���A�����I�łȂ��B
P�D165�iiii�j���Z���[������̈�E�̈Ӗ�
p.166�u90�N��O�����̋��Z����̉^�c�͖��炩�ɉߏ�Ȉ������߃X�^���X�E�E�v�Ɣᔻ�B�u���炩�Ɂv�H�@�u�ߏ�ȁv�H
�u����ɁA95�N�ȍ~�ɂȂ�Ɖ~�̑h�����[�g���啝�ɏ㏸���n�߁A����ł�GDP�f�t���[�^�[�̏㏸���͈�т��ă}�C�i�X�ƂȂ�f�t�����n�܂��Ă���B�����������Ԃɑ��A����͌�Ɂu�[����������v�ƌĂ��悤�ɂȂ���ɒႢ�����ɃR�[��������}�����ސ���������B�������A�o�ς̓f�t���̌��ʂƂ��āA���ڋ������[���ƂȂ��Ă����������̓v���X���ێ�����Ƃ����A����I�ȈӖ��ł́u��������㩁v�ɗ�������ł��܂������߁A�[����������͖ڗ��������ʂ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ������ƍl������v�ƁB
�@���́A���������Ă����܂ł�90�N��O���̓���̋��Z����������߂��A�Ƃ������ƂɂȂ�B
�@�������A�Ȃ����₪���̂悤�ȉߏ�Ȉ������߂��s���A���s�ł����̂��A�Ƃ������Ƃł��낤�B�o�u���Ƃ��̕���̓��{�o�ϑS�̂ɐ�߂�Ӗ��������ق����K�v�����낤�B
p.175
�@�U�@�s�\���ȋ��Z�ɘa��������̌������@�n�ӓw
�@1 ���͂̎��_
�@�u����GDP��������1990�N�㏉�߈ȍ~�A����𑱂��Ă���B����A����ҕ�����90�N�㖖���牺�����Ă���A�f�t�����i�s���Ă���v�Ƃ����͎̂����F���B��������A���̌������ǂ��ɋ��߂邩�����ƂȂ�B�����ƌ��ʂ̊Ԃɂ͂�������̊֘A������B���������āA�u���̓�̕]����ɏƂ点�A90�N�㏉�߈ȍ~�̋��Z����^�c���y��_��傫��������Ă���̂����炩�ł���v�ƂȂ邩�ǂ����H�@����قǂɓ���̋��Z����^�c�͌����̌o�ϓ����ɉe���͂�����Ƃ�����̂��낤���H�@�o�u���ɗx�����͓̂��₩�H���Ԋ�Ƃ̃o�u�����̍s���́H�@���₢���ɂ��_�́A�o�ς̍����I�^�c�̕��@��͍������ŁA���܂�L�v�ł������I�ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ����H
�@�����Ȃ��Ƃ��A�{���̘_�������Ă��邩����A�u���炩�v�Ƃ͂����Ȃ��̂ł͂Ȃ����H
�@����ᔻ�̑����A�u����̓o�u���c���ɉ��S���������łȂ��A�o�u���ׂ��ł����s�����v�Ƃ����B�o�u�������ɁA���̂悤�ɕ]�����邱�Ƃ͂���Ӗ��ŊȒP�ł���B���́A�o�u�����ɂ����āA�ǂ��������̂��H�@�o�u�����̖��Ԋ�Ƃ̋������悤�ȕs���Y����߁A�y�n���@�́A�����������ꂪ�ǂ̂悤�ȏ����ň����N�������̂��H
�v���U����[18]�Ɏ�����{�o�ςƐ��E�o�ς̕s�ύt�I���W�́A����̐ӔC���H�@�u�ߓx�̃h�����v�����̂��߂ɋ���������h���̑啝�����������f�Վ��x�s�ύt�A�~�������ێ��x�s�ύt���������̓����g��ɂ�鍕���k���̗v�����Ԏ����̍����s�ϓ��ƐԎ��k���ȂǁB
���������A�ւ��畂���яオ�邱�Ƃ́A���{�o�ς̗A�o���s�ύt�ɑ傫���Ȃ����A���ꂪ���N�̂悤�ɑ������A�Ƃ������Ƃ���b�ɂ���B
���{�̗A�o��������i�f�Ս�����������j���v���͉����H
�A�����J���n�߂Ƃ��鑼�̍��X���A����ɂӂ��킵�����{�ւ̗A�o���s���Ȃ��i�s��Ȃ��j�̂͂Ȃ����H
�@���������f�Օs�ύt�A���ێ��x�s�ύt�̔w�i�ɂ��鐶�Y�\�������ƂȂ낤�B
�@�A�o��}�����ꂽ���Y�\�́E���Y�́E�����͂ǂ��ɗ���邩�H
�@�O������v�����ꂽ�̂́A�f�Ս������̓����g��H
�@����ȓ����g�吭��͍s��ꂽ���H�@�����̐������L���ɂȂ�悤�ȈӖ��ł́u�����g��v�́H
�@���̂��߂̍����̍ŏI���v�̊g��́H
�@����Ȃ����āA�s�K�v�ȕ���Ɏ����i�ߏ莑���j�����ꍞ�̂ł͂Ȃ����H�@�y�n���@�B
�@�ȏ�̂悤�ȃo�u���Ɍ��������A�ւ�����Ƃ���A���₾���̐ӔC�łȂ����Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B
�@���O���̎s������������ߏ�Ȃ��тȓ��{�̐��Y�\�́A�������ɂ����ߏ�Ȏ��{�~�ρi�c��ȋ��Z���Y�j���A����ɂ���Ƃ������ƂɂȂ�͂��Ȃ����B
�@�����i���{�̉ߏ�~�ρj�ɂ́A���{�����̐����̖L�����Ȃǂ��}�����܂�荏�܂ꂽ���Ƃ�����͂��Ȃ����H�@������{���{��`�̖�萫���I�o���Ă���̂ł͂Ȃ����H
�@�A�����J�Ȃǐ�i�����ւ̗A�o�E���{�A�o���}������A�����g��ɂ����E������Ƃ��A�A�o�i���i�Ǝ��{�́j�h���C�u�́A�����Ⓦ��A�W�A�Ɍ��������̂ł͂Ȃ����B
���ꂪ�܂��u�������̃O���[�o�����v�A�u�����V���b�N�i�����̍H�Ɖ��j�v�A�u���������v�A�f�t���������N��������ƂȂ����̂ł͂Ȃ����H
�@�Ƃ���A90�N��㔼����2000�N�����ɂ�����f�t���́A�P�Ȃ���Z�I���ۂł͂Ȃ��A��b�ɍH�Ɖ��̕s�ϓ����W�E�������̕s�ϓ��Ȃǂ�����A�ƌ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@p.177�u1990�N�㖖�ȍ~�̃f�t���Ƃ̊֘A�ł́A��������̗����ȏ��i�̗�����A�p�\�R���Ȃ�IT�i���ʐM�j�֘A���i�̒l������ȂǁA���̋����V���b�N�i�T�v���C�V���b�N�j�̉e�����Ă���Ƃ̌����v�́A��̍����I�A�ւ������Ă���B�܂�A���Z����̎����Ƃ͈Ⴄ�Ƃ���ɖ�肪���邱�ƂɂȂ�B
P�D198
�S�@�܂Ƃ�
�@�u���Z�ɘa���s�\���ł��ꂪ�l�b�N�ɂȂ��ē�����������Ă���Ƃ̉����͊��p���ꂽ�v
�@�u90�N��㔼�ȍ~�ɕ��̋����V���b�N���������A���ꂪ�����������������Ƃ����W���m�F���ꂽ�B����A�s�\���ȋ��Z�ɘa���f�t���̎傽�錴���ł���Ƃ̉����͊��p���ꂽ�v�ƁB
P�D202�@�n�Ә_���ւ̃R�����g�ƃ��W���C���_�[
P�D210�@�_����ʂ��ĕ����яオ��_�_
��IV��
�s�Ǎ����̃C���p�N�g�͂ǂꂾ����
�@7�́@��s�@�\�̒ቺ��90�N��ȍ~�̃f�t����@�@�@�@�{������
�@8�́@��s�@�\�ቺ�������͐����͂��������邩�@�@�x�@�딎�E�ؑ�G��
7�́@��s�@�\�̒ቺ��90�N��ȍ~�̃f�t����@�@�@�@�{������
p.219
�u�}�N�����Y���̒ቺ���n���������o�����X�V�[�g�̈����ɂ����v����v�̘A�ւ̂Ȃ��ŁA�O���̗v���������B
�������ɁA���̒n�������E�ߏ蕉�́A�o�u���Ƃ��̕���̎���̂悤�Ɏv����B�o�u���Ƃ��̕���ŁA������(�����̓��v��������Ȃ����A700���~���������̖c��ȕs���Y���l(�n��)���������v��o�Ă����ƋL������(�m�F�K�v)�B
p.238 ������
�@�{�͂ł́A�u�݂��a��v�Ɓu�ǂ��݂��v�̓�������������_�F
�u�܂��A�݂��a�茻���ɂ��ẮA�X2�|93�N�A�����97�|98�N�̓�̎����ɂ݂�ꂽ���A���ꂪ�������������ȉe���������炵���Ƃ�����̂́A97�|98�N�̋�s��@�̎����݂̂ł���A90�N��S�̂�ʂ���������̐����v���Ƃ͂Ȃ�Ȃ��E�E�E�v
�u�����ǂ��݂��ɂ��ẮA�����̎��،��ʂ���A������Ǝ�ւ݂̑��o�������ɑ���s�݂̑��o���𒆐S�ɑ������Ă������Ԃ����炩�ƂȂ����B�܂������̃f�[�^�𗘗p���āA���Y�����ቺ���Ă��镔��ɁA��葽���̎��{�X�g�b�N������t���ƌ������Y�z���̘c�݂ɂ��Ă��m�F�����v
p.239�u��s�ɂ��ǂ��݂��s���́A�s�NJ�Ƃ��������ĉߏ苟���\�����������A��ƕ���S�̂̎��v���E���Y����ቺ�����Ă�����v���̈�ƍl�������B�܂��A���ꂪ�n��������ʂ��đ����v���������A�����̃f�t����������炵���\���ɂ��Ă����ؓI�Ɏ����v
�@�u�ǂ��݂��ɂ�鎑���z���̘c��[19]�����邽�߂ɂ́A���ݐi�s���ł��鎑�Y����̌��i������苭�����A��s����̉ߏ�i������I�[�o�[�o���L���O�j�����邱�Ƃ������d�v�ł���B�����̊�Ƃ́i�����ėD�ǂȊ�Ƃقǁj�A�o�����X�V�[�g�̌��S����D�悵�ă[���������ł��؋���ԍς��Ă���A��������ɂ���o�ώ�̎��̂����Ȃ��v�ƁB
�@���̒�����́A�܂��ɑS�̓I�ȓ��{�o�ςɂ�����ߏ莑�{���Ӗ�����B�D�ǂȎY�Ǝ��{�����悪������Ȃ����ƁA���ꂪ���݂̈�Ԃ̖��ł��낤�B
�@
�������A���E�̐l�X�́A���悫���������߂āA�Y�Ǝ��{�̓��������߂鐺���Ă��镪�삪����̂ł͂Ȃ����H
�@���E�̕n���n�сA��J���n��́A���̋�̓I�Ȏp�ł͂Ȃ����H���{�s���A���{�̗L�@�I�\���̒Ⴂ����������J���n��́A�������̍����n��ł�����̂ł͂Ȃ����H[20]
�@�A�W�A�J����s���ُA�C�\��҂̔����L�����{��(2004�N9��3����������)�ɂłĂ������A�A�W�A�J���ɂ�������{�̕��a�I�o�ϓI�v���́A����܂��܂��d�v�ɂȂ낤�B
�@�܂����łɁA2004�N9�����݁A�����s��͂��Ȃ芈�C�����߂��Ă���A�V����Ƃ̂��߂̃}�U�[�Y�s��Ȃǂ���؏�ꐔ�����Ƃ��A���Ă���B�V��������̃��F���`���[��Ƃ��V�����s����@��N�����n�����āA���̏��������s��̗]�莑�����W�ߎn�߂��A�Ƃ������Ƃł��낤�B�ǂ̂悤�Ȋ�ƌQ���A�V����������J���Ă��邩�A�������K�v�B
�@�u�肻�ȋ�s�̎������L���ɂ��Ă��A���I���������ɂ��12���ɂ܂Ŗc����Ȏ��{�́A�ȑO�̑ݏo�K�͂��ێ����邽�߂ł͂Ȃ��A�����܂ł��s�ǂȒ�����ƌ����̑ݏo���̐��Z�A�ݏo�����z�̃X�������Ɏg���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�ƁB
�@
�@�������Ǝ���A��ߏ莑�{���������壁A����Y�����ቺ���Ă��镔�壂����X�g�����邱�Ƃ��x�ꂽ�Ƃ������Ƃ̂悤�ł���B
�@�Ȃ����H�@�e�Y�ƕ���Ƌ�s�Ƃ̊W�̗��j�����ƂȂ낤�B�����A�������Ǝ���A��ߏ莑�{���������壂́A���t�Ō����ƊȒP�����A������������邱�ƁA�܂��ʊ�Ƃɑ����Č������邱�Ƃ́A����ȂɊȒP�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B�����̖��Ԋ�Ƃ̎s�ꋣ���̒��ŁA�ǂꂪ�����c�邩�͋��������߂Ă����̂ł���A���Y�j�A�e�Y�Ɣ�{�ɂƂ��Ă��A�e���Z�@�ւɂƂ��Ă��A�ǂ��܂Ŕ��f�\�͂����邩�́A��肾�낤�B����������́A�D�Nj�s�ƕs�Nj�s�Ƃ����ΓI�ɕ������Ă���Ƃ������Ƃł��낤�B�������鑤�̋�s�Ɠ�������鑤�̋�s�A�ȂǂƂ��āBUFJ�Ƃ�������Ȋl�����߂��鑈�D��Ƃ��āB
�@
8�́@��s�@�\�ቺ�������͐����͂��������邩�@�@�x�@�딎�E�ؑ�G��
�P�@�͂��߂�
�@p.246 �s���{���ʃf�[�^�̔�r���͂Ȃǂ���̌��_�Ƃ��āA�u�s���{���P�ʂŋ敪�����n��ʂ̋��Z�@�ւ̌��S���Ɠ��Y�n��o�ς̃p�t�H�[�}���X�Ƃ̊Ԃɂ͗D�ʂȊW�͌��������Ȃ��v
�@�u���Z�̋@�\�s�S��1990�N��ȍ~�̒���Ɉ��̉e����^���Ă��邾�낤���A���̉e���͕����I�ł���A������̎���Ƃ͍l���������v�B���̂����A�u�݂��a����v�ɉ����A��ǂ��݂��ࣂɂ��Ă��A������̎���Ƃ݂Ȃ���قǂ̍ޗ��͂Ȃ��A�Ƃ��ے�I�ɓ��ݍ���ł���_���A�{�͂ƑS�ĂƂ���|�C���g�v�ƁB
------------------�@
��L�̂悤�Ș_����]������ꍇ�ɂ́A��̓I�Ȏ������ł��邾�����ʓI���̓I�Ɋm�F���Ă����K�v������B���ꂼ��̑Η��I���ꂪ�A���́A���̓I�Ȋ֘A�̈ꕔ���������o���ċ������Ă���Ƃ������ʂ����邩��ł���B
���̊�b�I�ȓ��v�����Ƃ��A���t�{�̢�N���o�ύ�������肪����ɁA�����Č��邱�Ƃ��Ӗ������낤�B
�ŋ߂̂��́A���Ȃ킿�A����15�N�x�N���o�ύ������A��16�N�x���A�܂��͍ŐV��16�N�x���݂Ă݂悤�B
�������Ƃ��āA�o�u���Ⓒ����1990�N����2003�N�܂ł̗A�o�������́A�ǂ��ł��������H
�����Ȃ��Ƃ́A���{�ƃA�W�A�̌��т������ɋ����Ȃ������ʁA�A�o���ł̓A�����J���O���̊������啝�Ɍ����������Ƃł���B���̓_���m�F���邽�߁AH16�N�x�N���o�ύ������̎��̕\�����Ă݂悤�B�A�o�n��ł̓A�W�A�̊��������̊Ԃ�31.9������47���ɂ܂łɏ㏸���Ă���B����ɑ��āA�A�����J�̊�����30.7������23.9���ɂ܂ʼn������Ă���B�P�Ƃ̍��ƂƂ��Ă͕č�����ʂ��ێ����Ă��邪�A���̍��Ƃ��Ē������}�㏸���Ă���A�킸��2.2�����猻�݂ł�12.4���܂Ŋ����𑝂₵�Ă���B
�A���������X���ł���B���Ȃ킿�A�A�W�A�͂��̏\���N�Ԃɓ��{�̗A�o��Ƃ��Ĉ��|�I�ȏd�݂����悤�ɂȂ�A29.1������45.0���ɑ������Ă���B�A�o�捑�Ƃ������āA�A���ł͒��������܂�20.1�����߂ĕM���ɖ��o��[21]�B
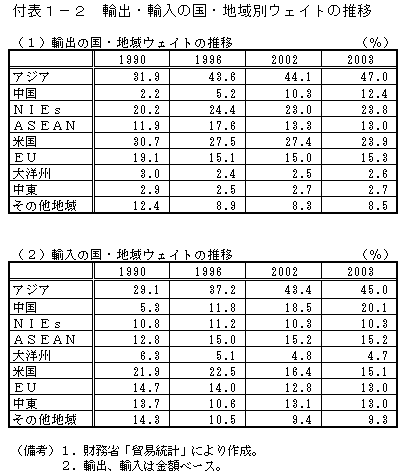
�@