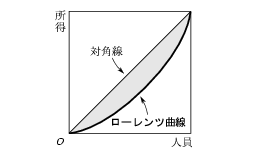File
No.1�X�V���F2004/09/10
�W���[�t�E�X�e�B�O���b�c�i�m�[�x���܌o�ϊw�ҁj
�w�}�N���o�ϊw(��2��)�x���m�o�ϐV��ЁA2001�N���ᔻ�I����
�ÓT�h�o�ϊw�E�J�����l���̌n�Ƃ̔�r
�\�J�����l���̌n�̕����E�����Ɓu�n���l�ށv�o�ςւ̂��̍����I�K�p�̂��߂Ɂ\
�l�ނ̘J���ƒn���̑��݊W�E�E�EW.�y�e�B�u�J���͑f�ޓI�x�̕��ł���A�y�n�͂��̕�ł���v
�y�n�E�n���Ȃ����Đl�ނȂ��B
�@�n���j�̈�Y���Ƃ��Ă̐l��
�@���̐l�ނ̗��j�I�Ȍo�ϐ���(���Y�l��)�̔�r�I�V�����`�ԂƂ��Ă̎s��o�ρE�ߑ㎑�{��`(15���I�ȍ~)
p.3�����s��E�E�E�E���v�Ȑ��Ƌ����Ȑ�����_�ʼn��i�����E�E
�E�~�N���o�ϊw�B
�@�펯�I�K��F���邢�́A�����I�s��Љ�̂��ׂĂ��т��K��B
�������A���̐����\�͂̌��E�́A���m������Ă��Ȃ��B
���Ȃ킿�A���_�(�����̈�v�_)���A�c��Ȏ��ɑ��l�ȏ��i��ނ̂��ꂼ��̒P���œ����I�ȉ��l�E���i�̗ʓI�E�䗦�W�ɂȂ��Ă��邱�Ɓi���{��`��i���̌���������Ε�����悤�ɁA�S���ꗥ�̒ʉ݂ƒʉߒP�ʁA����ɂ�鏤�i�̉��i�\�������l�\���j�A���������āA�S���i�����ʂ��鎿��O��Ƃ������I�W�ł��邱�ƁA�������������Ƃ������Ƃ����m�ɂ���Ă��Ȃ��B
�����i�ɋ��ʂ��鎿�A�������̂����ł����Ă͂��߂āA���̗ʂ̑������Ӗ��������A��r�ł��A�ʓI���A�䗦�Ȃǂ�ł���B�_���I���w�I�v�l�̊�{�ł��낤�B�ʂ̑����E�䗦���Ӗ������̂́A�����������̂����݊Ԃɂ����Ăł����B
�S���i���E����������S���i���A�����ɂ����ċ�̓I�Ɏ������̂ŁA���̎��A���i���g�̓����Ɏ����Ă��鋤�ʂ������͉����H
�A�_���E�X�~�X�A�f�C���B�b�h�E���J�[�h�ȗ����J�����l���̍��{�I�ÓT�I�Ӗ�(�����Ēn���K�͂̏��i�o�ρA�ō��x�ɔ��W�����s��o�ς̌��݂ɂ��ѓO�����{�@���̈Ӗ�)�͂����ɂ���B���i�̉��l�i���̉ݕ��\���Ƃ��Ẳ��i�j�����̂́A�J��(���i�ɂ͒��ۓI�l�ԘJ��)���A�Ƃ����̂ł���B
�����i�����u�W�ɂ������Ƃ��iA�̏��iX��B�̏��iY�ʁA�E�E�E�j�A���̎��I���u�W�����ۓI�l�ԘJ�����Ώۉ�����Ă���Ƃ������Ƃɂ���B�����������ʂ̎��������������̂Ƃ��āi���i�����҂����������̏��i�������ɂ����ē��u���邱�Ƃɂ���Ă����������p���ɊҌ�����j��������Ă���A�ƁB
�����i�ɂ����Ă͑��݂Ɍ��p�E�g�p���l���Ⴄ(���������Ēʖ�s�\��)���A���������Ⴂ�̂��鏔���i�������ɂ����ē��u�����̂�(���i���Y�҂����������ɂ����Ď��������̏��i������̂�)�A�X�̏��i�������������ʎ�����������ɂ����Ă��A�ƁB�����������ʎ��̂��̗̂ʓI�䗦�Ō������Ă���A�ƁB
�X�e�B�O���b�c���A�_���E�X�~�X�����p���Ă���B�����A��Ԋ̐S�̂Ƃ���i���l�_�j�������ۂ蔲�������Ă���B���Ȃ��Ƃ��A�o�ϊw���j�ɂ����鍪�{�I�ɈႤ�������Ă����B
���R�����A����ɂ����v�Ƌ����̈�v�����_=�s�ꉿ�i�������A�s�ꉿ�i�͉���\���Ă��邩�A���̎����A���ꂱ���������ׂ����A�ƃX�~�X�i���i�̎������l�Ɩ��ډ��l�ɂ����j�A���J�[�h�i���l�ɂ����j�A�}���N�X(�Ƃ��ɁA�u���p���g�p���l�`���̘J���v�Ɓu�������l�i���l�j�̎��̂Ƃ��Ă̒��ۓI�l�ԘJ���v�Ƃ����J���̓�d���̉�)�͂����B
�o�ϊw�̃R���Z���T�X�@
�V���e�B�O���b�c�́A�u�o�ϊw�҂̈ӌ�����v���Ă���d�v�ȓ_�v�Ƃ��āA��Scarcity,
�C���Z���e�B��Incentives�A����Ɩf��Trades�A���iPrices��4������Ƃ���B
p.4�u���v�Ƃ́A�������̂������Ƒ����H�ׂ�ɂ́A���̉�����������߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���Ȃ킿�A�t���[�����`�ł͂Ȃ�(There is no free lunch)�B�����l�ԎЉ��̊�{�I�����ł��飂ƁB�i����́A�w�������i�Ɍ��E������Ƃ������Ƃł���B�e�l�͍w�������i�����ɂ���Ď�ɓ���Ă��邩�H�J���҂Ȃ�A�����ł���B�����͉��ɂ���Č��܂邩�H�j
�������A�����ł������́A��̈Ӗ��ł��肤��B��́A���R�Ȋw�I���̓I�ȑ��ʂł���A�����̎����Ă��鎑��(�ݕ�)��O��Ƃ���ƁA���l�ȐH���i�̂Ȃ����玩�����u�H�ׂ�v���̂̑I���́A���肳���A�Ƃ������Ƃł���B
�s��Љ�E���i�o�ώЉ�ł́A�����̎����Ă���ݕ��ʂŁA���l�͏��i�Q���玩��̗v���E�~����������i���E���i��I�����邵���Ȃ��B(���i�ݕ��o�ςł͂Ȃ��Љ�ł́A���Ȃ킿���i���Y���s��ꂸ�A���n�����̂⑺�������̂Ƃ������Â��Љ�A���邢�͌Ǔ��̃��r���\���E�N���[�\�[�ł́A���i�����͂Ȃ��A�l�Ԃ́A���������̘J��(����)��K�v�����̐��Y�ɓ`���I���K�I���Y�͂ɍ��킹�ĐU������A�������ێ�����B�����ł́A�J���́E�J�����Ԃ̌��萫�i���j�����ƂȂ�B
���́A���i�ݕ��o�ςɂ����Ă��A�V���e�[�O���b�c�̂����u���v�̍����Ƃ��āA���i���w�����邽�߂̉ݕ����擾�����J�����Ԃ̌��萫(��)������B
�ݕ����ǂ�����擾���邩�H
����ɂȂ�Ȃ�قǖ��炩�Ȃ悤�ɁA���Ȃ킿�Љ�̒��ŘJ���͏��i����ʉ�����x�����ɉ����āA�J������āA�u�����v�㉿�Ƃ��ĉݕ��Ă��邱�Ƃ͎Љ�I�펯�ƂȂ�B�ݕ��Ƃ́u��莞�Ԃ̘J���v�̑Ή�(���̏ؕ[)�ł���B���{��s�����̐��E�̒�����s���́A���ւ̈���ɉ߂��Ȃ����A���̎����A���������u��莞�Ԃ̑Ώۉ����ꂽ�J���v�Ƃ������̂�\��������̂Ƃ��āA���̑Ή��W�̈��萫�ɂ����āA�ʗp�́E�M�p��B���{�S���A�T�����[�}��5�疜�l�ȏ�́A��莞�Ԃ́u�J���̑Ή��v�Ƃ��Ċl�������s�����A�܂��ɂ��̂悤�Ȏ��̂�\������ʗp�͂̂�����ŐM�p����B
�S�o�ϐ���(���i�ݕ��o��)�́A�����Ɏ����I���̓I������u���Ă���B���{�Љ�A���㐢�E�̈��|�I�����̐l���͂܂��ɂ�����펯�Ƃ��ė�������̂ł͂Ȃ����B
���ׂĂ̏��i�A���ׂČ����������̂́A�l�ԘJ���̎Y���ł���B���̘J�����Ԃ̑Ώۉ����ꂽ���̂Ƃ��ď��i�̉��l(���i�̉��i�̎���)������B
�V�ÓT�h�ȍ~�̋ߑ�o�ϊw�͂܂��ɁA���̓_�����Ȃ��B
�ȏ�̃R�����g�́A�ÓT�h�o�ϊw(�X�~�X�����J�[�h���}���N�X)�������I�Ȑ��E�I�s��o�ρE���E�I���{��`�̔��W�܂��āA�����Ԃ点�邱�Ƃ��A���E�̌o�ϖ������Ă��������ŁA�����̉����̂��߂ɁA�K�v�ł��낤�A�Ƃ̗��ꂩ��̂��̂ł���B
���i�̉��i(���̎��̂Ƃ��Ẳ��l)�̓����́A�l�Ԃ̘J�����Ԃł���Ƃ������ƁA�X�̏��i�ɓ����E�Ώۉ����ꂽ�J�����Ԃ́A�����i�̌������̂��̂�ʂ��āA���I�ɓ������̂ɊҌ�����ʓI�ɂ�������������(�ʓI�Ɍ��萫�E���̂������)�ƂȂ�̂ł���A�����������̂Ƃ���(�Љ�I�K�v�J�����ԂƂ��āA�Љ�I�����W��ʂ��Ď��������̂Ƃ���)�A�]�������B
p.4�u�C���Z���e�B�u�v�E�E�E�u�K�ȃC���Z���e�B�u����邱�Ƃ́A��{�I�Ȍo�ϖ��ł���B����̎s��o�ςɂ����ẮA����������Ɍl���]�ނ��̂Y����悤�ɃC���Z���e�B����^���A�����͌l�������C���Z���e�B�u�������炷�B���L�����܂��l�X�ɁA���������~�����o�Ȃ��A�ނ�̎��Y���őP�̕��@�ŗp���悤�Ƃ����A�d�v�ȃC���Z���e�B�u��^����v�ƁB
���(���{)�̖ړI�������ł��邱�ƁA���̖ړI�̒B���̂��߂ɂ͎s��ŏ��i��̔����Ȃ���Ȃ炸�A���������ĎЉ�(���l)���K�v�Ƃ��]�ނ��̂Y���̔�����K�v�����邱�ƁA�܂��Ɏ��{��`�I�s��o�ς̌�����C���Z���e�B�u��ƕ\�����Ă���B
�@�Ƃ���ŁA��l�ɓ����C���Z���e�B���������炷����̂́A����ࣂł��낤���H�@����Љ�A���{��`�Љ�ɂ����āA���l�ɢ�����C���Z���e�B����������炷�̂́A�������낤���H�@�����́A�����̂��߂ł���B�u�����C���Z���e�B���v����������̂́A�悸����ɂ́A���|�I�ɑ����̐l�X�ɂƂ��ẮA�����邽�߂ɂ͢��������������Ȃ�����ł���B�Ȃ����B�����Ă������߂̎�i�A�����Ă������߂̎�i�Ƃ��Ă̏��i����肷�邽�߂̉ݕ�����Y�����L���Ă��Ȃ�����ł���B���X���傷��Љ�̈��|�I�����̐l�Ԃ��A�����邽�߂̐��������Y�����i�����L���Ă��Ȃ�����ł���B�����邽�߂Ɉ��|�I�����̐l�X�������Ă���̂��J���\��(�J����)�����Ȃ�����ł���B
�@���{��`�̐��Y�l���́A�܂��ɔ_������_�������܂��܂̌o�H�E���@�ŒǕ����A���Y��i�����L�̐l�X���ʂɍ��o�����Ƃƌ��т��Ă����B�����鎑�{�̌��n�I�~�ρi�ߒ��j�́A�_���̓s�s���o���s�s�W�����ٗp�J���҉��̉ߒ��ł������B����́A�����{�̔����I�ɂ��}���ɐi�W�������Ƃł������B
�@���L�̐��{�̘J���͓��v�ɂ��A1956�N�ɏA�Ǝ�4,171���l�̂����A�ٗp�҂�1,913���l�A���Ȃ킿�����ȉ��ł������B����ɑ���40�N���1996�N�ɂ́A�A�Ǝ�6486���l�̂����A�ٗp�҂�5,322���ɁA���Ȃ킿8���ȏ�i�W�Q���j�ɏ���Ă���B�_�ƁE�_���A��ׂȎ��c�ƁE�Ƒ��]�Ǝ҂������������ƁA�ٗp�ҁi������i�����(����)�Ɉˑ�����l�X�j����ΓI�ɂ��䗦�I�ɂ����������Ƃ������Ă���B�s��̋ߑ㉻���ꂽ�Љ�A�s�s�ɏW������ߑ�Y�Ǝ��{�̂��Ƃł����L���Ȑ����̉\�������邱�ƁA�t�ɖL���Ȍo�ϕ��������͔_���ł͕s�\�ɂȂ邱�ƁA�����̔w�i�ɂ��邱�Ƃł���B�_������l�X��ǂ��o���v�b�V���v���Ɠs�s�������t����v���v���Ƃ̗Z�����A���������A�ƍ\�������o�������Ă���B���E�̑����̊J���r�㍑�ł͂܂��Ɍ��݁A���������_������̓s�s�ւ̐l���ړ�(�ꎞ�I�ȓs�s���ӕ��̃X����������)�E�_���̘J���҉����}���ɐi�W���Ă���B
�@���{�̍ŋ�40�N�Ԃ��J���͒�������(�o���Fwww.stat.go.jp/data/roudou/3.htm)
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@1956 �@1966�@ 1976�@1986�@ 1996�@40�N��
|
�P��: ���l,
��
|
|
|
���a31�N
|
�@41�N�@
|
�@51�N�@
|
�@61�N�@
|
�����W�N
|
������
����8�|���a31
|
�����{��
����8�����a31
|
|
�@
�j
�@
��
�@
�v
�@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15�Έȏ�l��
|
6,050
|
7,432
|
8,540
|
9,587
|
10,571
|
4,521
|
1.75
|
|
�@�J���͐l��
|
4,268
|
4,891
|
5,378
|
6,020
|
6,711
|
2,443
|
1.57
|
|
�@�@�A�Ǝ�
|
4,171
|
4,827
|
5,271
|
5,853
|
6,486
|
2,315
|
1.56
|
|
�@�@���S���Ǝ�
|
98
|
65
|
108
|
167
|
225
|
127
|
2.30
|
|
�@��J���͐l��
|
1,776
|
2,537
|
3,139
|
3,513
|
3,852
|
2,076
|
2.17
|
|
�A
��
��
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�ٗp��
���c�Ǝ�E�Ƒ��]�Ǝ�
|
1,913
2,258
|
2,994
1,831
|
3,712
1,551
|
4,379
1,458
|
5,322
1,147
|
3,409
-1,111
|
2.78
0.51
|
|
�_�ы�
������
�T�[�r�X��
|
1,437
805
507
|
1,006
1,178
682
|
601
1,345
876
|
450
1,444
1,205
|
330
1,445
1,598
|
-1,107
640
1,091
|
0.23
1.80
3.15
|
|
���S���Ɨ�
�J���͐l���䗦
|
2.3
70.5
|
1.3
65.8
|
2.0
63.0
|
2.8
62.8
|
3.4
63.5
|
1.1
-7.0
|
1.48
0.90
|
(��)�P�D���a�R�P�N�A�S�P�N�ɂ͉��ꌧ�̐��l���܂܂�Ă��Ȃ��B
�Q�D���S���Ɨ��́A�@�@�J���͐l���ɐ�߂銮�S���Ǝ҂̊�����(���S���Ǝҁ��J���͐l��)�~100
�@�@�R�D�J���͐l���䗦�́A15�Έȏ�l���ɐ�߂�J���͐l���̊�����(�J���͐l����15�Έȏ�l��)�~100
�@���{��15�Έȏ�̏A�J�\�Ȑl��1��571���l�̂����A����҂�3852���l����B�ނ���܂���{�I�ɂ̓T�����[�}��(�ٗp��)�̌������ގ҂ł���A����Ɏ��Ǝҁi225���l�j���ٗp�������Ă�����̂ł���A�Љ�I�ɂ����Όٗp�҂ɑ�����i���Y��i�E���Y�����l�X�ł͂Ȃ����Ƃ͖��m�j�B
�@�Ƃ���A���{�Љ�́A�����I�ɂ͢���K���ЉƂł����������ȎЉ�\���ł���B�قƂ�ǂ��ׂĂ̐l���ٗp�҂Ȃ������̈��ގ҂ł���B�K���Ƃ��āA���{(���Y��i)�����L���Ă���l�X�̐��́A���{�S�̂̒��Ŕ��ɏ��Ȃ��A�Ƃ����悤�B
�@����ł́A���Y��i�E���{�����L���Ă���̂́A�N���B����͂܂��ɓ��{�̏ꍇ�A�����č��x�Ɏ��{��`�����W�������قǐ��E�̂�����Ƃ���ŁA�@�l(���)�ł���B�@�l�����Y��i�̏��L�҂ł���A���{�̏��L�҂ł���B
�@�����āA�����@�l�����́A���{�̏��L�̎���ł���A�����ꏭ�Ȃ���A�܂��A���̎Љ�̖����`�I�l�ԓI���n�x�ɑΉ����ł͂��邪�A���{�̘_���ɂ���ē�����Ă���B������{�Љ�(�L�����E�̍��x��i����)�̢���L�������ɂ���̂ł���A����́A�܂����@�l�̏��L���ł���A�Ƃ����ׂ��Ȃ̂ł͂Ȃ����B���̖@�l�̍s�����������ɂȂ낤�B�@�l�����{�Ƃ��Ă̊�b���������A�����ɐl�ԓI�ɍ����I�Ɍo�c���s���悤�ɐ��n���Ă��邩�A���ꂪ���ƂȂ�B
�@�@�l��Ƃɂ�����u���{�̘_���v�Ɓu�l�ԂƘJ���̘_���v�̂��߂������́A���{�I�ȁu�]�ƈ��匠�v�A��l�{��`��ƣ�ɂ����Ă��A�K�R�I�Ȃ��Ƃł��낤�B
�@����ނ���A�@�l�ɂǂ��܂Ől�ԓI�_�����ѓO����͗ʂ����邩�A�@�l�������Ɏ��{�̘_���܂��l�ԓI�_���ʼn^�c����邩�A���ꂪ����Љ�̉ۑ�ƂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ��낤���B
�o�ϊw�҂̈ӌ�����v���Ă����O�̓_�A���Ȃ킿
p.4-5�u����Ɩf�Ձv�Ƃ͉����Ӗ����邩�H�@�X�e�B�O���b�c�ɂ��A
�u�����I�����͗��v�ݏo���B�l�Ԃ̎���ł��낤�ƁA�܂��������z�����f�Ղł��낤�ƁA���ׂĂ̎���҂͎����I�������痘�v�邱�Ƃ��ł���B����܂��͖f�Ղɂ���āA����҂͔�r�D�ʂ����o�ϊ����ɓ������邱�Ƃ��ł���v�ƁB
�@�����I����=���R�̈�̏d�v�ȗv�f�B�������A�l�Ԑ����ɂ����āA�o�Ϗ�̌����́A���R�̈ꑤ�ʂł����Ȃ��B
�@�o�ςɂ�������E�T�[�r�X�́u�����I�����v�́A�����Ȃ闘�v�ݏo���̂��H
�@���iA�i����1���b�g���j�Ə��iB(�p��1��)�Ƃ̌����́A���iA�i�����j�̏��L�҂ɂ́A�����̎����Ă��Ȃ��ʂ̌��p�̂��鏤�iB(�p��)����ɓ����B���iB(�p��)�̏��L�҂́A�����̎����Ă��Ȃ��ʂ̌��p�̂��鏤�iA�i�����j����ɓ����BA��B���A�����������Ă��Ȃ����p�E�L�p���E�L�v�Ȃ��̂���ɓ����B���݂��ɗ��v�ł���B���ꂪ���i�����̈�̑��ʂł���B���p�E�g�p���l�͕ʁX�ł��邱�ƁA�Ⴄ���p������������(���i)�����������A���i���Ⴄ���p�������Ă��邩�炱�����݂��̗��v(���p�E�g�p���l�̖ʂ�)�ƂȂ�A���������藧�B
�@�����A�����A���̌����ɂ����āA���iA������150�~�A���iB��200�~�Ƃ���B���݂������v�邽�߂ɂ́A���������łȂ���Ȃ�Ȃ����낤�B����Ƃ��A���l(���i)�͂���������ǂ��A���݂������Ă��Ȃ����̂̌����ŁA���̓_�ł��݂��Ɂu���v�v�ƂȂ邩��������悤�Ƃ������ƂɂȂ邾�낤���H�@150�~�̂��̂ƈꖜ�~�̂��̂��������邩�H�@150�~�̂��̂�1���~�̂��̂Ƃ��������邩�H�@�����ł͂Ȃ��ł��낤�B
������ׂ��ʓI�䗦(�����䗦)���K�v�ƂȂ낤�B�Ⴆ�A���iA�̋���2���b�g����300�~�Ə��iB�̃p��1�Ҕ���300�~�������ł���A�������������ɂ����Č��������Ƃ��A���҂͂��݂��ɑ������Ȃ��B
�@�����������������l�̌������������i�̂��̂̌����A���ꂪ���i�����̌����ł��낤�B
�@�܂�A���i�����ɂ����ẮA�g�p���l�̖ʂł̗��v�ƌ������l(���i�E���l�̉ݕ��\��)�̖ʂł̗��v�Ƃ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�g�p���l�̌����ɂ����ẮA���͂܂������ʂł���B�������l�ɂ����ẮA���������ŗʂ��������ɂȂ�(�����ł��邱�Ƃ����݂��̗��v�ł���A�����̊�{�����ƂȂ�)�B
�@�X�e�B�O���b�c�̕\���́A���̓�̊W�������܂��ɂ��Ă���B���i�̎��́����l�����̉��l�̎��̂��ǂ��K�肷�邩�A�������|�C���g�ɂȂ낤�B
�@
�X�e�B�O���b�c���A�u�o�ϊw�҂̈ӌ�����v���Ă����4�̓_�v�Ƃ́A���iPrices���Ƃ����B
���i�Ƃ͉����H
�{���Ɍo�ϊw�҂̊Ԃň�v���Ă���̂��H
�@
�u�����I�s��ł́A���i�͎��v�E�����̖@���Ō��܂�B���v�Ȑ��⋟���Ȑ����V�t�g����Ƌύt���i�͕ω�����B���l�̌����́A�J���s��⎑�{�s��ɂ����Ă͂܂�B�J���̉��i�͒����ł���A���{�̉��i�͗��q���ł���B�v
�@���������̋����̎��R���A���S���̓x�����ɂ����āA���v�Ƌ��������ꂼ��ɍ��E���邱�ƁA�����Ă��̋ύt�_�ʼn��i�����܂邱�ƁA�����ے肷����̂͂��Ȃ��B
�@���́A���̋ύt�_���A�s��ɂ��閳���̏���̂��ꂼ��ɈႤ�̂͂Ȃ����ł���B�����̋ύt�_�́A1���b�g��150�~�ł���B�����̋ύt�_�́A100�O����400�~�ł���A��ˌ��ĂP�R�O���ẲƂ�5000���~�ł���ȂǂȂǁB�Ȃ��A�����i�́A����=�ύt�_���Ⴄ�̂��H
�@�X�e�B�O���b�c�̐��Y���s��Ɋւ��鏖�q�i��.�Q�P�j�ɂ��A�u�o�ςɂ͖����̐��Y���s�ꂪ����A�����̍����ƂɈ�̎s�ꂪ���݂��Ă���E�E�E�X�̍��Ɋւ��ẮA���̎��v�Ȑ��Ƌ����Ȑ��Ƃ̌�_�ŋύt���i���^������v�ƁB
�@����ł́A�����ɂ�����̌X�̋ύt���i���A���Ƃ��Ώ�L�̂悤�ɋ����A���M�A�p���ȂǂȂǖ����̏��i���ƂɁA����ύt���i�ƂȂ��Ă��邪�A���̋ύt���i���A������̂�100�~�A������̂�1�~�A������̂�100���~�ƗʓI�ɈႢ������̂͂Ȃ����H�@
�@�ύt�́A�������������̏��i�̌ʓI�ȋύt���i���A�Ⴄ����������ł��Ȃ��B
�@�܂��ɁA�������A�A�_���E�X�~�X�A���J�[�h�A�}���N�X�Ƒ����J�����l��(�����l�̎��̂͏��i�ɓ�����ꂽ�Љ�I�ɕK�v�Ȑl�Ԃ̘J���ʁE�J������)�̏o�Ԃł���B
���ꂼ��̍��̋ύt�_(�ύt���i)�́A���̎��X�̂��ꂼ��̍��ɓ�����ꂽ�J���ʁi���ԂŌv�ʂ���A���ꂼ��̍��̐��Y�ɎЉ�I�ɕK�v�ȘJ�����ԁj�̈Ⴂ�ɂ��A���l�̈Ⴂ(���i�̈Ⴂ�ŕ\�������)�́A���ꂼ��̍��Ɏx�o����Ώۉ����ꂽ�J���ʂ̈Ⴂ�ł���A�ƁB
�@�J���s��ł��A�ύt�_(�����E���^�̎x���z)�������̈Ⴂ�������Ă���킯�ł͂Ȃ��B
�@��s��ƒn���s�s�A�_���ł͎����A�T�x�A�����Ȃǂ̈Ⴂ������B
�@�܂��A�E�K�E�E�\�ɂ���āA�����Ɉ��̍�������B
�@�����A���{���v�������悤�ɁA�Y�ƁA�E��A�K�w�Ȃǂɂ���Ă���ύt�_�̏�����B
�@�����͉��ɂ���ċK�肳���̂��H���ɂ���Č��܂�̂��H
�@���́A�����ɂ���B
�@�}���N�X�́A�u�J���̉��i�v�Ƃ������̂́A���́A�J���\��(�J����)�̉��l(���̉ݕ��\��)�ł���Ƃ����B����\�͂����J����(���_�I���̓I�ɓ�������)���u�������Ƒ���{�����炷�邽�߂̔�p�v=�u���������̑��z�v���u���̐��������ɓ������Ώۉ����ꂽ�J���ʁE�J�������v���A�J���͂̉��l(���̉ݕ��\���Ƃ��Ẳ��i)�ł���A���ʂ̈ӎ��ɂ����ẮA���̘J���͂̉��i���A��J���̉��i��ƊϔO����āA�x�����Ă���̂��Ƃ����̂ł����B
�X�e�B�O���b�c���A��ʂ̊ϔO�Ɠ������A�������u�J���̉��i�v�ł���B
�}���N�X�́A�������J���͂̉��i�ł���A�Ƃ����B�@
�����Ⴄ���H
�t�����l�̍\�����l����Ƃ��A���̖�肪����I�ɏd�v�ɂȂ�B
���L�̘J�����ԂɑΉ����镽��13�N���Ƃ낤�B�t�����l�\���́A�ǂ̂悤�ɂȂĂ������B(�@�l��Ɠ��v�FH13)
�@�l��Ɠ��v(�t�\�T�F�t�����l�̍\��)�ɂ��A
�l����75.1��+�x�������E������4.5��+���Y�E�s���Y���ؗ�9.6��+�d�Ō���3.8��+�c�Ə��v7.0�����t�����l100���@�ƂȂ��Ă���B
�@�t�����l�̋K��ƍ\�����疾�炩�Ȃ悤�ɁA�t�����l�Ƃ͂��������̗L�p�Ȏg�p���l(���p)���̏ۂ������l�ł���B
����ꂪ�����悤�ɁA�t�����l�́A���Y�N�x�E�l�X�̓���(���̓I���_�I�J��)�ɂ���ĐV�����t��������ꂽ���l�ł���B�l�Ԃ��J���ɂ���āA�V�������l��t��������B
�@���̑S�̂̕t�����l�̂����A�l����Ƃ��ē����l�X�E�J������l�X���擾����̂́A75���ł���B
(�N�ɂ���āA72���̂��Ƃ�����A73���̂��Ƃ�����A�i�C�̕ϓ��A���㍂�̎��с��t�����l�̎����x���W���Ă���A���ΓI�ɌŒ�I�Ȑl������ɑ��āA����ȊO�̏�]���l�̕������A�s�i�C�̎��ɂ͌�������E�E�E���ۓI�ɂ͘J�����z�����オ��=�䗦���Ƃ����Ȃ�A����ɑ��čD�i�C���s��̏��悭�Ĕ��グ�D�����ƁA���̕�����������E�E�E�J�����z���͉�����)
�@������ɂ���A�t�����l�̂��ׂĂ����l���擾����̂ł͂Ȃ��B
�@�l���A100���ԓ����A100�Ƃ����t�����l��t�����������A�ނ��J���̑Ή��Ƃ��Ď��̂́A75���ԕ��ł���A���l�I��75�ł���B
�@�J���������Ԃ̉��i�Ƃ��Ē������l���Ă��邪�A����Ȃ�A100���ׂĂ̂͂��B�Ȃ��A���̈ꕔ�ł���75���A��J���̉��i��Ȃ̂��H
�@���̍��{�I���ɓ����邽�߂Ƀ}���N�X�͌ÓT�h�o�ϊw�̌������d�ˁA�J���ƘJ���͂̈Ⴂ�������B�ނɂ��A�������̂͘J���͂ł���A75���ԕ��A75�͘J���͂̉��l�ɑ�������A�ƁB
���{�o�ς�S���̂́A�����l�X�A���̑��̂ł���B
���{�o�ς̖��N�̔��㍂�Y����̂́A�����l�X�̑��̂ł���B
���{�o�ς̑S������S���̂́A�����l�X�̑��̂ł���B
���̐��_�I���̓I�J��(�@�B���E�Z�p���E��̐i����ł́A���|�I�ɓ��]�J���E���_�J���̃E�G�C�g���A�S�J���̎��Ǝ��Ԃň��|�I����������)�̎��Ԃ́A������l�����蕽�ρA���L�̂Ƃ���ł���B
���J���l����������A���{�̋ΘJ����l�X�̑��J�����Ԃ��Z�o�ł���B
�܂��ɁA���{�Ŏd��������l�̂��̖����A�����A���N�����J���������A�����A�����A���N���t�����l�i��+���j�A�V�������l�ݏo���B�����l�X�͂��̐V�������l�̂Ȃ���v�����͋��^�Ƃ��Ď��A����A�����Ɛ������ێ�����B
���{�̍ŋ߂̖��N�̖@�l��Ɠ��v�ɂ��A���{�̖@�l��Ƃ̖��N�̑��t�����l�́A�ݕ��z�ŕ\������Ƃ�������250���~-260���~���x�ł���B����N�̑��J�����Ԃł��A���{�̈�J�����Ԃ�����̉ݕ��\��(���Ȃ��Ƃ��@�l��Ƃ̂���)���A�o�Ă��邱�ƂɂȂ�B
�����ΘJ���v�����@�����P�R�N�����ʊm��(�����J���ȓ��v)
|
���@�@��(����)
|
�������^���z
|
���܂��Ďx
�����鋋�^
|
��������^
|
����O���^
|
���ʂɎx��
��ꂽ���^
|
|
351,335�~
|
(-1.2)
|
281,882�~
|
(-0.8)
|
263,882�~
|
(-0.5)
|
18,000�~
|
(-4.2)
|
69,453�~
|
(-3.0)
|
|
�J�����ԁ@�@�@
�@�@�@
�@�@�@�@(����)
�@�@
�@�@�@�@(�N��)
|
�����J������
|
������J������
|
����O�J������
|
�o�@�@���@��
|
����O�J������
(���@���@��)
|
|
153.0����
|
(-0.8)
|
143.6����
|
(-0.7)
|
9.4����
|
(-4.4)
|
19.9��
|
<-0.1>
|
12.6����
|
(-8.5)
|
|
1,836����
[1,848����]
|
1,723����
[1,714����]
|
113����
[134����]
|
�@�@�@�@�@
|
151����
[169����]
|
|
�ف@�@�p
�J���ٓ�(����)
|
��p�J����
|
��ʘJ����
|
�p�[�g�^�C��
�J�@���@��
|
���@�E�@��
|
���@�E�@��
|
|
43,378��l
|
(-0.2)
|
34,281��l
|
(-1.1)
|
9,097��l
|
(
3.6)
|
2.06��
|
<0.03>
|
2.15��
|
<0.06>
|
�@�� 1�j�i�@�j���͑O�N��i���j�A�� �����͑O�N���i�|�C���g���͓��j�A[ ]���͎��Ə��K�͂R�O�l�ȏ�ł���B
�@ �@2�j�����J�����ԁA������J�����Ԃ̔N���Z�l�ɂ��ẮA�e���ԕ��ϒl���P�Q�{���A�����_�ȉ���P�ʂ��l�̌ܓ��������̂ł���B����O�J�����Ԃɂ��ẮA�����J�����Ԃ̔N���Z�l���珊����J�����Ԃ̔N���Z�l�������ĎZ�o���Ă���B
�@�l��Ƃɓ����l�X�͑��̂Ƃ��āA�ނ�S�̂̑��J�����ԂŁA�t�����l�Y����B100(��)�̕t�����l�����o���B�S�]�ƈ��̎d���̐��ʂ��A�t�����l�̑��z(100)�ł���B
���̂����A�����l�X�́A�l����Ƃ���75�i���j�����B
�c��̘J������(25)�́A�u�l����ȊO�̕t�����l�v�̂��߂̘J�����ԂƂ������ƂɂȂ�B���Ȃ킿�AH13�ł����A�����́A���̂悤�ɂȂ��Ă���B
�x�������E������4.5��+���Y�E�s���Y���ؗ�9.6��+�d�Ō���3.8��+�c�Ə��v7.0��
�@�@�l��Ƃɓ����S�]�ƈ��́A���Z�@�ւ���������(����)�A��Ƃ̎��{�Ƃ���ȏ�A���q�E�����������������̎d��(�J������)�ŁA�x����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B(�x�������E������)
�A�y�n�E�s���Y�����A�n��E���ؗ��̎x�����̂��߂ɂ����̘J�����Ԃ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B(�s���Y�����ؗ�)
�B�@�l��Ƃ̑��݂���Љ�̈ێ��̂��߂Ɍ����I���S(�d�Ō���)���x����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A��������������̎d��(�J������)�ŁA�܂��Ȃ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B(�d�Ō���)
�C����ɁA����ɂ͈��̔z�������x����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̔z�������x�����邾���͘J�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����ɁA�����́A�����������ׂĂ̌o�c���A�����̂����ɐ��s������V�Ƃ��ē��ʂ̏ܗ^�����(������V)�B������A�S�]�ƈ����������J�����Ԃ̒�����܂��Ȃ���B(�c�Ə��v)�@
�@�ȏ�̐����܂��āA�܂��t�����l���v���悭�l���āA���āA�w�����N�́A����(����)���u�J��(�S�J������)�̉��i�v�ƍl���邩�A�u�J���͂̉��i�v�ƍl���邩�H
�@�����̋����I�s��Љ�ł́A�u�J���̉��i�v�Ƣ�J���͂̉��i����ӑR�ƂȂ��Ă���̂ŁA��������l���Ă݂�K�v������B�B
�@�l����ȊO�̕t�����l����(����Y����J������)���A�S�]�ƈ����t�������鉿�l��(�t�����l���Y�̂��߂̘J������)�A���ꂪ���Y��i�̏��L�ҁA���Ȃ킿�A�y�n���L�҂⎑�{�̏��L�ҁA���{�@�\���ʂ����������ɔz�������̂��A�ƌ����������A�ǂ��݂邩�H
�@�ʂ̌�����������A���q�⊄�����A�n��E�s���Y���ؗ��A�d�Ō��ہA�z�����A������V�̂��ׂĂ��A�J�����Ԃ���b�ɂ������̂��A�Ƃ݂�̂��A���������J�����ԂƂ������̂̂Ȃ����̂Ƃ݂�̂��H�@���Ȃ킿�A�����l�̎��̂�J���ƌ���̂��A�����łȂ��̂��H
�@�����A���q�E�������A�n��E�s���Y�����ؗ��A�d�Ō��ہA�z�����A������V�Ȃǂ̉��l(�ݕ��z)�̎��̂��A�J���łȂ��Ƃ���A���ɉ������̂Ƃ��Ă���̂��H�@�ǂ����炻���̎��̂͐��܂�Ă���̂��H
�@�����Ȃ��Ƃ��A���{�S���A5�琔�S���l�̋ΘJ����l�X�́A�����́u�J���̑Ή��v�Ƃ��Ď������E��������A�d�Ō��ۂ��x�����Ă���B�ΘJ����l�X�̑d�Ō��ۂ́A�u�J���̈�莞�ԁv�Ɠ������B
�@��Ƃ��x�����d�Ō��ۂ��A�u�x�o���ꂽ�J���̈�莞�ԕ��v�ƑΉ�����̂ł͂Ȃ����H�@
�u��莞�Ԃ̘J���v(�Ώۉ����ꂽ����)�ƌ������̂������d�Ō��ۂ̓����ł͂Ȃ����B
�@
�X�e�B�O���b�c�@�u���́@�R�@��{�I�������f���ɂ�����s��ύt�v���A�J���s��A���Y���s��A���{�s��̢�s��ύt����A���ꂼ������v�Ȑ��Ƌ����Ȑ��̌�_�Ő�������B
�@�������A�o�ό����Ƃ��āA��ʓI���ϓI�ɍL�͂ɑÓ����Ă���u�J�����i�v�́A���ꂼ��̎Љ�ŁA���鐅���ɂ���B��Ō����悤�ɁA�u�J���̉��i�v�̐����͂��Ȃ�Œ�I�ł���B�Ȃ����H�@�i�C�̕����͂���ɂ�������炸�A�ł���B�Ȃ����H
�@�J���̋����Ȑ������v�Ȑ����A���ꂼ��̎Љ�ɂ����āA������E���ɂ���B���̂��Ƃ̒�������ɂ�����Ӗ��́A�P�Ȃ���v�E�����Ȑ��ł͐����ł��Ȃ��B���v�E�����Ȑ��������ł���͈͂͌���I�ł���B
�Œ�������x�́A�P�Ȃ�@���K��ł͂Ȃ��A�����I�ȍ���������B�J�����Ԃƒ����Ƃ̑Ή��W�̌����I�ȍ����͉����B���ꂪ�����B
�@
�@���{�s����A�u���{�̉��i�v�Ƃ���闘�q�̋ύt�_���A�������v�Ȑ��Ƌ����Ȑ��̌�_�Ƃ��Đ��������B���ׂāA�����������̎��v�����W�ŁA���܂�Ƃ���B
�����A���{�̎��v�ʂ����Ō��܂�A���{�̋����ʂ����Ō��܂邩�A���̌���I�ɏd�v�ȓ_�́A��̋Ȑ����ꎩ�̂���͉������炩�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B
�����́A�u�ƌv�ɂ�钙�~�̋����v���瓱���o�����Ƃ����B�������A�����̎��{�s�������킩�邪�A��Ǝ��g���������p��A�����̎��{�������A���v���������̑��A�ȂǢ���~����������{�s��ɓ�����B�����ɂ����ĂȂ���ƌv��Ɍ��肷��̂��A���q�͂Ȃ��B���������A��ƌv��Ȃ�T�O�ɋΘJ�҉ƌv����Ə��L�҉ƌv���A�ꏏ�ɂ��邱�Ƃɖ�肪����B
�����A���v�́A���Ƃ��V�K�������t�@�C�i���X���邽�߂̎������v���瓱���o����飂Ƃ����B�����A�ƌv���Z��݁E����ړI�̂��߂ɢ�������v����o���ꍇ������B
���v�Ƌ�����P���Ɂu��Ɓv�Ɓu�ƌv�v�œ���̂́A���������͂Ȃ����B��������ʗ��_�͒P�������K�v�ł���B��ʗ��_������P�������Ă���̂��H�@�����A���̏ꍇ�A��ʗ��_�Ƃ��Ă̒P�����́A�ǂ��܂ŗ��_�I���ۓI�ɋ�����邩�B
p.22�u�R�D�T�@�s��̑��݊W�v�́A���i���E���S�̂Ƃ��đ��݂ɉe���������ƌ����_�ł́A���̂Ƃ��肾���A�����͒P��������Ă��܂��Ă���B
�u�Ⴆ�A���������㏸�̉e���́A�J���s��ɔg�y���邱�ƂɂȂ�v�͓̂��R�Ƃ��āA�܂��A����̉��i�������Ȃ�ƁA�ƌv�̎��������i�����ꎞ�ԑ������������ʂƂ��ĉƌv���w���ł���悤�ɂȂ���̑������j�͌������A�J���̋����ʂ����������悤�Ƃ��飂ƁB���̌X���͂���Ƃ��Ă��A�ނ�����������������ł����₻���ƁA�J�����Ԃ��������������t�@�N�^�[�������B����͎��̖��ł���A�P���ɢ���������飂Ƃ͂����Ȃ��B
��ʋύt�̐����Ƃ��ẮA����̉��i�ϓ��̑S�̓I�ȘA�ւ�ʂ��āA����ύt��Ԃ���ʂ̋ύt��ԂɈڂ�A�Ɨ��_�I�ɑz�肷�邱�Ƃ́A�������\�ł���B
�X�e�B�O���b�c�́A�u�R.�U�@�t���[�z���v�ɂ����āA��o�ς��\�����邳�܂��܂ȕ���Ԃ̊W�́A�����t���[�z��circular flow�ɂ���Đ}������飂Ƃ��A�u�}��-12�@�P���ȃt���[�z�}�v�������B
�@�u�P���v�ł��邩��Ƃ����āA�������P�����ɂ͌��x������B(���Ȃ��Ƃ����w�҂ɑ��Ă͕s�e��)
�@�u�}���\12�v�ł́A
�@�@�@��̗���A�u�ƌv�����E�T�[�r�X�ɑ���x����������v�A
�@�@�@���̋t�̗���A�u�ƌv�������A�����g�A����������v���}������Ă���B
�@���m�Ɍ����Ȃ�A���̓�̗���́A�Ȗ��ɐ�������ɂ́A�K�ł͂Ȃ�(�}�ɐ����͂��Ă��邪)�B
�@�O�҂̗���ɑ���̂́A�u�ƌv�����E�T�[�r�X�̍w��������v�ł���B����Ŕ�������������B
�@��҂̗���ɑ���̂́A�u�ƌv���u�J���v�A�y�n�s���Y�����݁A���{������v�ł���B����ŁA�Ή��W(�u�J���v�̏ꍇ�A�����W�A�y�n�s���Y�̏ꍇ���݊W�A���{�̏ꍇ�A�����E���v�W)����������B
�@�X�e�B�O���b�c�̐}���ł́A�ƌv�Ɗ�Ƃ��Βu����Ă���B�ƌv�̒��ɂ́A�u�J���v��̔�����J���҂Ƣ��Ƃ̏��L�ң���ꏏ�ɂ���Ă���B�����Ɨ������ꏏ�ɂ���Ă���B�������茴���Ɨ������茴���̍��{�I�Ⴂ���A�����ł͎̏ۂ���Ă���B
�@
�@�}���P�R�ɂ́A�u���{����ƊC�O���傪��������ꍇ�̃t���[�z�v��������Ă���B�����̖��ɂ́A��L�̂悤�ȕs�\��������͂茩����B
�@
�@���̓_�͊�{�I�ɏd�v�ł���A���_�I�ɐ��m�Ȓ莮�����Ǝv����B
���Ȃ킿�A�u�����̃t���[�z�}�́A�o�ϑS�̂ɂ����邳�܂��܂ȉƌv��`����ŗL���ȕ��@�ł���B�}���\�����Ă��鑽�������x�ϓ������́A�����I���P�����ł���B�P�����Ƃ���ɐ�������W�ł���A�����͊֘A����T�O�̊�{�I�Ȓ�`���瓱���o�����B���Ƃ��A�ƌv�̏����́A�����w�����邽�߂̎x�o+���~(��Ƃւ̎����̗��o�z)�ɓ������Ȃ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�ƁB
�P�����W�́A������I��Ȃ��̂ł����āA�ʋ�̓I�ȓ����������Ӗ�������̂ł͂Ȃ��B������A��̕��ŁA�u�Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�ƕ\��������Ȃ��B
���x�̍P�����W���A��Ɉ�т��ēK�p���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�u�J���̎x�o�v�Ɓu�����v�ƊW�ł��K�p���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�u�J���v�A��J���ͣ�̈Ⴂ�̈Ӗ��́A�܂��ɂ����Ō���I�ƂȂ�B���̓_�������A�`���Ɏw�E�������_(�o�ϊw�҂ɂ���Ă������_)�ł���B���ꂪ�t�����l�̍����I�������\�ɂ��邩�ǂ����B���ꂪ�����B
p.35 �u5.2�@�s���S���v
�o�ς̊�{�I�������f��(���S���̑O��)�̓K�p�̐���E�E�E��{�I�ѓO�ƌl�I�E�ʓI�E�ꎞ�I�E�n��I���̕s���S���imperfect information�E�E�E�@���Ƒ��l�ȕ������ʎ��ۂƂ̑��݊W�ɋA������B
�@
����́A�s��o�ρE���I�����o�ςɖ{���I�Ȃ��Ƃł���B���͉B�����B
�s���S��s���S����
�@
�@�@
��.�T�U�@�uA.�R�@�����搔�̌v�Z�v�ŁA�搔�v�Z���s���Ă���B�������A���̏搔�̉ߒ��́A�o�ς̌�����ɉh�������̂ł͂Ȃ��A����Ȃ颉��裂ł���B
�@���Ȃ킵�A������10���h���������ꍇ���l���A�܂�����E�������0.9�ł���A�Ⴆ�A������10���h����������Ə��9���h����������Ɖ��肵�Ă��飁B
�@������10���h����������ƁA���̂������i��9���h���ɂȂ�A�Ƃ����̂́A�����̌_�@�̏�ԂȂǂ��݂Ȃ���A�������Ȃ��B
�@�����܂ł��A����裂ɂ��������Ȃ��B
�@�������d��Ȗ�肪����B
�@��ŏ���10���h���̓��������͎x�o��10���h������������Ƃ��āA�Y�o�ʂ��Ȃ킿������10���h�����������邩�H
�@10���h�����������Ƃ���B�Z�o����ɂ��Ă���̂ŁA���E�T�[�r�X�̐��Y�ɓ�����ꂽ���̂Ƃ��悤�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@Ar
�@����ꂪ�AG-W �E�E�EP�E�E�EW�f-G�f �Ō����悤�ɁA
�@�@�@�@�@�@�@�@�@Pm
�����Ƃ��Ďx�o�����ݕ��́A�]�ƈ�(�J����)�ٗp�̂��߂̎x�o�iAr=V�j�ƁA���Y��i�w���̂��߂̎x�o�jPm=���j�ɕ������B���̂��Ƃ��̔䗦�́A���ꂼ��̌o�ς̔��W�i�K�̊e�Y�ƕ���̎��{�\���E�Z�p�\��(���{�̗L�@�I�\��)�ɂ���ċK�肳���B
�@���Ƃ��A���F�����S�F�P�@
�@10���h���̓����̏ꍇ�A�J���҂��ٗp����̂�2���h���A���Y��i���w������̂�8����h���Ƃ������䗦�ɂȂ�B
�@���̍\���̎��{���A���Y�ߒ��ł͂ǂ̂悤�ɐV�����t�����l��t�������邩�H
�@���{�̍ŋ߂̕t�����l�\���́A�l����75��(72�p�[�Z���g����75���ňꉞ75���Ƃ��Ă�����)�A���q�E�������A�s���Y�����ؗ��A�d�Ō��ہA�c�Ə��v�����킹��25���Ƃ������ƂɂȂ�B���F�����R�F�P�Ȃ̂ŁA
�@���̐��Y�ߒ�����o�Ă������Y���́A
�@c=8���h��
�@����2���h��
�@m��0.67���h��
��������ƁA���̎��{�ƋZ�p�̍\���ɂ����ẮAW�f�\G�f=10.67���h���Ƃ������ƂɂȂ�B
(�����ɂ́A���Y��i8���h���̂����A�����ȂǗ������{�����Ƌ@�B�Ȃǐݔ��ւ̓���=���̒P�ʊ��Ԃɂ����錸�����p����ɕ����Ă݂Ă����K�v������)
�@���ɁA�ٗp�҂�V����2���h������Ƃ����Ƃ������ƁA���̋�����9�������J����(�ٗp�҂͎g�p�����A1���~�����A�Ƃ����ߒ��͂��肤��B
�����A8���h���Ɋւ��ẮA�P���Ȕ����ł���B�ݕ�8���h���̂Ɛ��Y��i8���h�����̍��Ƃ������������ꂽ�킯�ŁA�����ł̏�����́A100���ł���B
�@�Ƃ���ƁA���ɏ������0.9�Ƃ��Ă��A�ٗp�ւ̎x�o�Ɛ��Y��i�ւ̎x�o�Ƃł͉e��������Ă���B�����������Ƃ��A�搔�v�Z�ł͂Ȃ��l������Ă��Ȃ��B
�@�P�Ȃ鉼��ƁA����ɂ��ƂÂ��P�Ȃ鐔�w�̌v�Z�ł����Ȃ��B�o�ς̌����̓������A�����̏��v�f�ɕ������āA�g�y���ʂ��݂Ă��Ȃ��̂ł���B
��P�� ���S�ٗp�ƃ}�N���o�ϊwFull-employment Marcoeconomics
p.59�u���{�ɂ́A���Ƃ��Ȃ����������肵���o�ς��ێ����A�܂��o�ϐ����𑣐i�����������ӔC������A�ƍL�������ɐM�����Ă���B���������M�O�f����1946�N���S�ٗp�@(Full
Employment Act of 1946)�ɂ́A�u�������i��p���āA�ő���Ɍٗp�A���Y�A�w���͂i���邱�Ƃ́A�A�M���{�̌p�����ׂ�����ł���ӔC�ł���v�ƁB
�@���z�ƌ����̍�
�@�����̌o�ϊw�҂̊Ԃ̋c�_�A�ӌ��̈Ⴂ
p.60 �A�����J�o�ςɊւ��鏖�q�E�E�E�f�ՐԎ��ƍ����Ԏ��̊W�ɂ��āE�E�E�u���S�ٗp���f���̉��p�v�̌����E�E�E�u�f�ՐԎ��͍����Ԏ��̌��ʂł��邱�Ƃ�A�o�ϐ������̒ቺ���܂������Ԏ��̌��ʂł��邱�ƂȂǂ��������v�ƁB
�@���{�́A90�N��A���m�̂悤�ɁA�o�u����̒����\���s���ŁA����ȍ����Ԏ��������悤�ɂȂ����B�����A�f�Ղ́A�\���I�ɍ����𑱂��Ă���B
�@���������āA�A�����J�̏ꍇ�A�u�f�ՐԎ��������Ԏ��̌��ʁv�ł���Ƃ��Ă��A���{�̏ꍇ�́A������Ԏ��ɂ�������炸�A�f�Ս������\���I�ɑ��݂��飂Ƃ�����B
�@���āA�ǂ��������邩�H
�@
��1��
�}�N���o�ϊ����̑���Macroeconomic
Goals and Measures
�P�@�}�N���o�ς̎O�̕a
�@�@�@���ƁA�C���t���[�V�����A�ᐬ�����A
p.62�u��Ƃ͘J���Ǝ��{���ƌv���璲�B���č��Y����A�܂����͉ƌv�ɔ̔�����A�ƌv�͊�ƂɘJ���⎑�{����ē��������ɂ���Ă��̍����w������v�Ƃ������A���łɃR�����g�����悤�ɁA��ƂƉƌv�Ƃ̓@�́A�����̌o�Ϗz���l����ꍇ�A���܂�ɂ��P�������ꂷ���Ă���B��ƊԎ�����A����Љ�̏d�v�Ȕ����W���Ȃ��A��Ƃ́A����{���ƌv���璲�B���飂Ƃ����͈̂�ʓI�ł���B���x�Ɏ��{��`��ƃV�X�e�������B��������Љ�ɂ����āA�Љ�̎��{�̈��|�I�������������^�p���Ă���̂͊�Ƃ��̂���(�@�l)�ł���A�ƌv�ł͂Ȃ��B
�@
p.64
�Q�@�o�ϐ���
�@�����́E�E�E�������Y���E�E�E���Y�����J�����Ԃ�����Y�o��
�Q�D�P�@�Y�o�ʂ̑���
�@�@�Y�o�ʂ́A�����̏��i�̑����ł���A��ݕ����l�����v�����Ƃ����B�u��������A���Y�S�̂�v���̐��l�邱�Ƃ��ł���B���̐��l�����������Ygross demestic product�܂���GDP�ƌ����v�ƁB
�@�����ŁA���i�̉ݕ����l��\�����̂Ƃ��Ẳ��i�𗘗p���邱�Ƃɂ��āA���Ŏ��̂悤�ɐ�������B
�@�u���i��p����̂́A��r�̏���֗��Ȃ��߂���ł͂Ȃ��B���i�́A����҂��������܂��܂ȍ��ɂǂꂾ�������l�������Ă��邩���f���Ă���B���Ƃ��A�I�����W�̉��i����̉��i��2�{�ł���Ȃ�A�I�����W��(���E�I��)���2�{�̉��l�����邱�ƂɂȂ�v�ƁB
����E�I�ɣ�Ƃ����̂́A���v�Ƌ��������߂�ꍇ�ɂ͈Ӗ������B��_��ݒ肷�鎞�ɂ́B
�������A�����i�ňႤ���̌�_�̑��݂̗ʓI�䗦�A����͢���E�I��ƌ������Ƃł͉����������Ă��Ȃ��B
�@�I�����W1�̉��i=200�~�Ƃ��悤�B
�@��P�̉��i��100�~�Ƃ������Ƃł���B
�@
�@�I�����W1�����2�@���ꂪ�����ł���B
�@
���̓����𐬗�����铯���̂��͉̂����H
�@���̓����ɂ����ẮA���l���������B�����̗������A�������l�ł���B��̏��i�ɋ��ʂ�����͉̂����H�@��̏��i�ŗʓI�ɂ݈̂���āA�����������͉̂����H
�@�A�_���E�X�~�X�A���J�[�h�A�}���N�X�̘J�����l���́A��̏��i�ɂ����āA�Љ�I�ɕK�v�Ȑl�Ԃ̘J��(�������ꂽ�J��)�������Ȃ��̂ł���A���̗ʂ͎��Ԃɂ���đ�����A�Ƃ����B
�@���ݓ��{�̎����́A�P���J���ł��Ƃ���750�~�Ƃ�800�~�ł���(�ȉ��̌v�Z�ł͉���750�~�Ƃ��悤�B���̎����́A1���Ԃ�����̘J���҂̂����J���ʂƓ������͂Ȃ��B���{�̖@�l��Ƃ̕t�����l���v�ɂ��A����(�l����)�́A���J�����Ԃ�70������75���ł���i�ȉ��̌v�Z�ł͉���75���Ƃ��悤�j�B
�@�P���J��1���Ԃ̉��l���́A���@�~75����750�~�@�@X=1000�~
�@�u�I�����W5�����10�v�̐��Y�ɓ�����ꂽ�J���ʁ��P���J��1����=1000�~�Ƃ������ƂɂȂ�B�@
�@�I�����W1�̐��Y�ɗv�����Љ�I�ɕK�v�ȘJ�����ԁ�12���E�E�E�I�����W�P�̉��l��12���J������
�@���1�̐��Y�ɗv�����Љ�I�ɕK�v�ȘJ�����ԁ�6���E�E�E�E���1�̉��l��6���J�����ԁA
�@�Љ�I�K�v�Ȑl�ԘJ���Ƃ����ǂ���̏��i�ɂ����ʂ̎������������̂��A��莞�Ԃ̗ʓI�䗦�ő��݂ɂ͂�����A�Ƃ������Ƃ͂��̂悤�Ȃ��Ƃł���B
�@���r���\���E�N���[�\�[���A�Ǔ��ŁA�I�����W�̐��Y�̂��߂̘J���ɂ́A�ނ̘J�����Ԃ�12�����g���A��̐��Y�̂��߂ɂ�6�����g���A�Ƃ������W�ł���B��̂ق������Y�ɗv����(�����Ȃ���Ȃ�Ȃ�)�J�����Ԃ��I�����W�̔����ōςށA�Ƃ������Ƃł���B
�@���ʂ̐l�Ԃ̈ӎ��ł́A���ꂼ��̏��i�ɓ�����(�x�o����)�ݕ��z(�R�X�g)�������ӎ��ɂ̂ڂ�B�����A���̔w��ɂ���̂́A�J�����Ԃ��Ƃ������ƁA���ꂪ�J�����l���ł���A�J���̈��ʂ����͏��i���l�i���̉ݕ��\���Ƃ��Ẳ��i�j�̎��̂ł���B
�@���ׂĂ̏��i�̉��i(���l)�́A�����I�Ȑl�ԘJ���̂��̂Ƃ��ǂ��̎Љ�ŕK�v�ȘJ�����Ԃ̗�=�����I�Ȃ��̗̂ʁA�����獇�v���邱�ƂɈӖ�������B���v�ł���B
�X�e�B�O���b�c�ɂ����Ă��A���Y���͘J�����ԂƊW���Ă����B���������āA�J�����Ԃ�����(���i���i)�̋K��v���ł��邱�Ƃ́A����ʂł͔F�߂Ă���B����������т����������œK�p���Ă��Ȃ������ł���B
�@������J�����Ԃɂ܂ŊҌ����Čv�Z���邱�ƁA�����ɘJ�����l���̌ŗL�̈Ӌ`������ƌ����Ă�����������Ȃ��B
�@GDP�̌v�Z�ɂ����āA�����Ɩ��ڂ���ʂ��邪�A����ł́A���������Ŋ��Z����Ă���B���̏ꍇ���A�����̐��������ꂼ��̕����̘J�����Y���ɂ܂ŊҌ����āA�S�𑍍̂����A�J�����ԂŔ�r���邱�ƂɂȂ�A�����x�͓O�ꂷ��ł��낤�B
�@�@
�Q�D�Q����GDP
�Q�D�RGDP�̑���
�@�ŏI���A�v���[�`final goods
approach�E�E�E�ŏI�I�ȗ��p��(�ŏI�I����ҁ��ŏI�I�Ȍl����Ɛ��Y�I����A���{�A�A�o�}�C�i�X�A���̍��z)���Ƃɕ��ނ��ꂽ���E�T�[�r�X�̉ݕ����l�̍��v
�ŏI��(���ԍ����T����������)�̉��l���z���v�Z
�@ C���l����consumption�E�E�E���ԏ���
�A I���������Ă���@�B���H��ɐݒu�����肷�邽�߂�(���Y�I����̂���)��Ƃ��g�p�������������investment�E�E�E���ԓ���
�B G���{���w���A�������E�T�[�r�X�E�E�E���{�x�ogovernment
spending
�C X�A�o
�D M�A��
GDP=C+I+G+X-M
�t�����l�A�v���[�`
�@�t�����l�������i�i���Ԃ̌l����Ɠ����A����ѐ��{����A���i�A�o���j�̔̔�������������ƒ��ԍ��Ɏx���������z�̍��z
�@
p.72�u�t�����l����Ƃ̎����|���ԍ��̔�p�v
p.73�uGDP�͐��Y�̊e�i�K�ł̕t�����l���Z�o���邱�Ƃɂ���đ��肳���B���Ȃ킿GDP�́A�ȉ��̂Ƃ���ł���B
�@GDP���S��Ƃ̕t�����l�̍��v
p.73 �����A�v���[�`�@
�@��Ƃ��������������z����鍀�ڂ���Ă���킷���́B
�@��Ƃ̎���������+���q�x����+���ԍ���p�{�Ԑڐ�+����
�@
��Ƃ̕t�����l�́A�������璆�ԍ��̔�p����������������
��Ƃ̕t�����l������+���q�x����+�Ԑڐ�(��Ƃ��x�����Ԑڐ�)+����
���Y�o�ʁ������̍��v
p.74-75 GDP�E�E�E�E���E�T�[�r�X�̐��Y�����ɏœ_�Ăđ������鐔��(���l)
�u�L���s�^���E�Q�C���́A���Y���l�̑������ł���A���������Đ��Y(�Y�o��)������킷�����Ƃ͂܂������قȂ������̂ł���BGDP���v�����邽�߂̍��������v�Z�Ƃ́A���E�T�[�r�X�̐��Y�����ɏœ_�Ă���̂ł���A�L���s�^���E�Q�C�����܂�ł��Ȃ��v
|
�X�e�B�O���b�c�w�}�N���o�ϊw��2�Łxp.75���쐬
|
|
|
|
�\1�|1
|
�A�����J��GDP(1995)��ŏI���A�v���[�`�Ə����A�v���[�`
|
|
�@�@�@�@�@�@�@�ŏI���A�v���[�`
|
�@�@�@�@�@�@�@�����A�v���[�`
|
��
|
|
����
|
49,234
|
�ٗp�ҏ���
|
42,094
|
58.1
|
|
����
|
10,675
|
�����E���ݗ��E���q��
|
24,425
|
33.7
|
|
���{�x�o
|
13,585
|
�Ԑڐ�
|
5,959
|
8.2
|
|
���A�o
|
-1,017
|
|
|
|
|
���v
|
72,478���h��
|
���v
|
72,478���h��
|
100�D0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�\1�|2
|
�@���{��GDP(1996�N)�F�ŏI���A�v���[�`�Ə����A�v���[�`
|
|
�@�@�@�@�@�@�@�ŏI���A�v���[�`
|
�@�@�@�@�@�@�@�����A�v���[�`
|
��
|
|
����
|
303.0���~
|
�ٗp�ҏ���(����)
|
281.1���~
|
55.9
|
|
����
|
149.2���~
|
�����A���ݗ��A���q��
|
186.3���~
|
37.0
|
|
���{�x�o
|
48.5���~
|
�Ԑڐ�
|
37.7���~
|
7.5
|
|
���A�o
|
2.3���~
|
���v��̕s�ˍ�
|
ϲŽ2.1���~
|
ϲŽ0.4
|
|
���v
|
503.0���~
|
���v
|
503.0���~
|
100
|
GDP�̂�������A���{�̏ꍇ��60�����x�ɑ��A�A�����J�́A68���B���{�̑��ΓI�ߏ������������яオ��B
GDP�̂����������A���{�̏ꍇ�A��30���ɑ��A�A�����J��14.7���B���{�̑��ΓI���ߏ蓊���������яオ��B
GDP�̂������{�x�o�i����j���A���{�̏ꍇ��9.6���ɑ��A�A�����J��18.7���Ɣ{�߂����炢�̊����ƂȂ��Ă���B
GDP�̂����A���{�͏��A�o�������ŁA�A�����J�͐Ԏ��ƂȂ��Ă���B������A���{�̑��ΓI�ȉߏ�����Ɗ֘A���錻�ۂł���A�A�o�Ő݂����Ƃ̌��ւ̎��{�~�ρA���{��Ƃ̍��x�Ȏ��{�~�ρE�����Ɗ֘A����ł��낤�B
���{�̍����������~�ςɑΉ����A�����A���ݗ��A���q����GDP�ɂ��߂銄�����A�A�����J���3.3���������A�t�Ɍٗp�҂̏�����GDP�ɂ��߂銄���͂́A�A�����J���2.1�����Ⴂ�B
���{�ƃA�����J���ׂ�ƁA���{�̕����A�����J��莑�{��`(���{�~�ρ����Y�g��Ώd�E�����̏���}��)�A�Ƃ����f�[�^�ł����B
��T�[�r�X�c�ƣ�A��ߘJ����A�N�̔��ɑ����̃t���[�^�[��(���S���l)�A��҂̏����s����ɂ��ƒ�`���̓���A�����̎Љ�i�o�ɉ����ĕK�v�ȕ�q�ی�̂��߂̐ݔ��̕s�\�����A���q���Ȃǂ́A��Ƃ̉ߏ�Ȏ��{�~�ρA�ߏ�ȋΖ����ԂȂǂ��Ӗ����Ȃ����H
�A�Ǝ҂����܂�ɂ������Ԏd������������ƁA�����ꏊ�����Ȃ�����A�ƒ됶���̎��Ԃ��]���ɂ���A�ΘJ�҂̐l�Ԃ̍Đ��Y�����������܂��Ɍ��݂̓��{�Ő��E�ɗނ����Ȃ��قNj}���ɐi�W���Ă��鏭�q���́A��ƒ��S�Љ��ƂɎs���I�����̖L�������D���Ă��邱�Ƃ̔��f�ł͂Ȃ����H)
�@�A�����J�̏ꍇ�A���{�Ȃǂ�菊���i�����傫���A�g�債�Ă���Ƃ�����B
���{�������i�����g�債�Ă���Ƃ�����B
�������W�j�W���ŋc�_����Ă���B
GDP�̒��ɐ�߂������A�ٗp�ҏ��������́A�������������i�����l�������ꍇ�A�A�����J�Ɠ��{�ʼn����Ӗ����邩�H
�@�X�e�B�O���b�c�́AGDP���@�B�̌���(�������p����)���܂������l���ɓ���Ă��Ȃ����Ƃɒ��ӂ𑣂��Ă���B��+�����t�����l����������GDP�͂���킵�Ă���B
�@���̂��Ƃ́A���͎̏ۂ��ꂽ�������p�ƂƂ��ɁA���Y������ė������Ȃǂ̑�O��̏��v���̎̏ۂɂ��Ȃ��肩�˂Ȃ��B
���w�}�N���o�ϊw��2�Łxp.78�E�E�E�uGDP�́A�o�ϐ����ɂƂ��Ȃ����̈����͔��f����Ȃ��B�܂�GDP���v�͌���������w�W�ł�����B�Ⴆ�A����n���������A�����������邽�߂��X�т̔��������肵���Ƃ��悤�B�����������̐X�т́A�����I���̎��Ԃ��o�āA���炵�����̂ł���B�X�є��̂ɂ���āA���̌o�ς̎Y�o�ʂ͌v���͏㏸���邪�A���̍��̎��Y�͌�������B���������Y�o�����́A�����\�i�T�X�e�i�u���j�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�����ō��A�����������̂��A����V�R�����ւ̉e�����l���ɓ��ꂽ�O���[��GDP�ƌĂ��V���������o�όv�Z�̌n�ł���B��̐X�є��̂��ɂƂ�Ȃ�A�O���[��GDP�ł͒ʏ��GDP����V�R�����̌�����������������邱�ƂɂȂ�B�����S���҂́A�O���[��GDP�w�W�ɂ���āA�X�є��̂ɂ��ʏ��GDP�͑������邪�A����͒��������Ȃ����Ƃ�m�邱�Ƃ��ł���B�X�є��̂́A�Љ�̕x��������̂ł͂Ȃ��A��������������Ă���̂ł���v�ƁB
�S�@�C���t���[�V�����@
�@�X�e�B�O���b�c�̒�`�͉����H
�@�u�����f��̑S�����ł�����1920�N��ɂ́A�f��̓��ꗿ��5�Z���g�������B�n���E�b�h�S������1940�N��㔼�ɂ́A���i��50�Z���g�ɏ㏸�����B1960�N��㔼�ɂ�2�h���ɂȂ�A���݂�7�h�����z���Ă���B�����������i�㏸�͌����Ĉُ�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��A���̂قƂ�ǂ̍��ɂ����l�̂��Ƃ��N�����Ă���B�������������̍��̉��i�̑S�ʓI�ȏ㏸���C���t���[�V�����ƌ����B�v
�@�����Ŗ��͉����H�@���i�́A���i�i���E�T�[�r�X�j�̉��i�ł���B���i�̉��l�������Ȃ�A���i�͍����Ȃ�B
�@�u���ꗿ�v�Ƃ������ۓI�ȋK���ʼn��i��]�����Ă������H
�@�f��̍쐬��i�����j�A��f���̋K�͂�@�B�ݔ��A�f��X�^�[�̐������o�������̑��A���ꗿ���Z�肷���b�ƂȂ鏔����������ł��낤�B
�@���������āA�����������ꗿ���K�肷�鏔������������ꍇ�A���R�̋A���Ƃ��āA���ꗿ���オ�邱�ƂɂȂ�B�����ł́A�����̉��l�Ɖ��i�i���̉��l�̉ݕ��\���j�Ƃ̊W�����s���ďオ�邱�ƂɂȂ�B
�@�����֘A�̍��ƃT�[�r�X�i����������w��consumer price index CPI�E�E�E���ϓI�ȉƌv�̏����̎g����������킷���̃o�X�P�b�g�A���̕ω��j��������ׂ����t���������ď㏸����A������ɂ�������͂Ȃ��B�J�����Y�͂̔��B�ɔ����A����ɉ��������ƃT�[�r�X�̖L�����i���p�A�g�p���l�̎��Ɨʁj��������B
�S�D�P�@�C���t���[�V�����̑���
�@�@���E�T�[�r�X�ɂ���ăC���t�������������B
�@���E�T�[�r�X�ɂ���Ă͉��i����������̂�����B
�@�u�ߋ�20�N�Ԃɂ킽���āA�ʕ����̉��i��220���A�K�\�������i��138���A��Ô383���㏸�������ŁA�R���s���[�^�[�̉��i��90���ȏ���������Ă���B�o�ϊw�ł͑S�ʓI�ȉ��i�����̕ω���������߂邽�߂ɁA�����̍��̉��i�㏸���̕������v�Z����B�v
p�D86�u�o�ϊw�ł́A���ɂ��d�v�x�̈Ⴂ�f����ɍۂ��āA���ړI�ȕ��@��p����B���Ȃ킿�A����҂���N�w�������̂��������̑g�ݍ��킹�i�o�X�P�b�g�j�����N�w�������炢����ɂȂ�̂��A��₤�̂ł���B
�S�D�Q
�A�����J�̃C���t���[�V�����@
�P�D
��ꎟ���E�����A����E�����A�����1973�N-81�N�̎O�̎����������A�C���t������5���ȉ��ł���A20���I��ʂ��āA�����͔�r�I����B�����A20���I��������1960�N�㏉�߂܂ł̊��Ԃ����ƁA�C���t�����͕��ς���Ɩ�P���ɂ����Ȃ������B
�Q�D
���������̎����E�E�E��ꎟ���E����̕s�����ɂ͕�����15���ȏ�A�����B1930�N��̑勰�Q���ɂ͕�����30���ȏ㉺�������B�E�E�E19���I���ɂ͕����������������Â���f�t���[�V����deflation���d��ȊS���B
�R�D
�����}�㏸�E�E�E���C���t�����E�E�E�ŋ߂ł́A1970�N�㖖����1980�N�㏉�߂ɂ����āB1980�N�ɂ�13���ȏ���㏸�B�@
�S�D�R �C���t���[�V�����̏d�v���@
p.89�@�C���t���[�V�����́A���{���Γ��i�����j���͂邩�ɏ���Ώo�i�x�o�j��������A�ߑ�ȐM�p���^��������Ƃ����A�o�ϐ���̏d��Ȏ��s�̋A���ł��邱�Ƃ������B
�@�������A�^�̖�肪�w��ɂ���ɂ�������炸�A�������C���t���[�V�����ɋA����邱�Ƃ���������B1973�N�̐Ζ����i�����́A���E����A���I�ȃC���t���[�V�����i�C���t���E�X�p�C�����j�Ɋ������B�A�����J�̐Ζ��A�o���ւ̎x�����͋}�����A����Ӗ��ł͕n�����Ȃ����B�E�E�E�Ζ����i�㏸�ɂ�鐢�E�I�s���̂��߁A�����̌����͂��������傫���Ȃ����B�������ăA�����J�̘J���҂̎��������͉������Ă��܂����B
�S�D�S ���̑��̕����w���@
����ҕ����w���b�o�h�́A���ϓI�ȏ���҂̎x�o��ΏۂƂ���C���t���[�V�����̎ړx�B
�@���Y�ҕ����w���o�o�h�E�E�E���Y�҂���̔�����邳�܂��܂ȍ��̕��ω��i�B
�T�D�@��v��3�ϐ��Ԃ̊W
�@�@���{���ڎw���}�N���o�ϐ���̎O�̎傽��ړI�E�E�E�Ⴂ���Ɨ��A�Ⴂ�C���t�����A�����o�ϐ���
�@�O�̕ϐ��Ԃ̋K����
�@�@�@�s�����i���Y�팸�E�����j�����Ɨ��㏸�i���C�I�t���ꎞ���فA�����j���C���t�����ቺ���o�ϐ�����������I�s��ł́A���i�̔�����������i�����グ�͂��܂�Ȃ�
�U�D�t���[�ƃX�g�b�N
�@�f�c�o�A�f�m�o�C�m�c�o�Ȃǂ̎w�W�́A1�N������i�N���j�̎w�W�B�E�E�E�E���Ԃ�����ő��肳���ʂ��t���[flows�Ƃ����B
�t���[�ƑΔ䂳���̂́A�X�g�b�Nstock�̓��v�B�E�E�E����ꎞ�_�ł̎w�W�B
�@�Ȃ��ł��ł��d�v�Ȃ̂́A���{�X�g�b�N�B�E�E�E����͌o�ς̐��ݐ��Y�\�͂̊�b�ƂȂ������E�@�B�̑����l�ł����B
�@���鎞�_�̎��ƎҐ��́A�X�g�b�N�B
-------��_p.98-101---------�@
�����o�όv�Z�̏����ڂ̑��݊W
�t�����l�T�O�ƍ����o�όv�Z�ɂ����邻�̎��ۂƂ̑��݊W���A�����I�łȂ��B
�t�����l�T�O�̎g���������i�@�l��Ɠ��v�̏ꍇ�ƍ����o�όv�Z�̏ꍇ�̈Ⴂ�j�B
p.74 �ł́A�u���������Y���f�c�o���S��Ƃ̕t�����l�̍��v�v�Ƃ����B
�@�����āA�f�c�o���������x�o���f�c�d�@�E�E�E�������x�o�ɂ́A�u�Œ莑�{���Ձv���Œ莑�{����̐��Y���ւ̉��l�ړ]�E���l��U�������܂܂�Ă���B
�@�i�f�c�o�̏ꍇ�́A�u�S��Ƃ̕t�����l�̍��v�v�Ƃ������A���̏ꍇ�̕t�����l�͂�+�������ł͂Ȃ��A���̕������ӂ���ł���A��Ƃ̏ꍇ�̂�+��+�������������Y���������x�o�@�ƂȂ��Ă���j
���{�̖@�l��Ɠ��v�ɂ�����t�����l���l����+���q�E�������{�n����ݗ�+�d�Ō���+�c�Ə��v�A
�@�E�E�E���������āA���̏ꍇ�́u�t�����l�v�ɂ́A�Œ莑�{���Օ��͊܂܂�Ă��Ȃ��B
�@�@�@�@����ǂ��납�A�������{�����i�������̉��l�j�̈ړ]�������܂܂�Ă��Ȃ��B
��Ƃ̔��㍂�ɂ͂����s�ώ��{�̉��l�ړ]���������܂܂�Ă���B������A���������Y�z�i500-530���~�j�����傫���z�ƂȂ�B���Ȃ킿�A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��1,068��9,329���~�i���j+257��8,691���~�i��+���j
�@
-------------------
��2��
���S�ٗp���f��
�P�@�}�N���o�ϋύt�E�E�E���f��
�Q�@�J���s��E�E�E�J���s��̋ύt�E�E�E�J�������́u��e�͓I�v�Ƃ̉���
�Q�D�P �J���̎��v�Ƌ����̕ω�
�@�@�Z�p�i���E��������ɂ�����J���s��̕ω��i���v�j�́A�n���E�Ȋw�Z�p�J���̎��v�����i���������̑����X���j�A�P���J���i���n���J���j�̎��v�����i���������̒ቺ�X���j
�@�@�@�B����H�Ƃ̋Z�p�i���̈Ӗ�����
�R�@���Y���s��
�R�D�P ������
�R�D�Q �����v�Ƌύt�Y�o��
�S�@���{�s��
�S�D�P ���~�E�E�E���B117�u���،����ɂ��ƁA���~�͗��q���ɑ��ċ���قNJ����I�ł͂Ȃ����A���~�Ȑ��͂��됂���ɂȂ�v
�S�D�Q ����
�l���Ƃ�����������w������E�E�E���̓����́A���Z����financial investments
�@�@���Z�����́A��Ƃɋ@�B�⌚���Ȃǂ̎��{�����w�����邽�߂̎��������E�E�E
p.118�u�V�����@�B�⌚���Ȃǂ̎��{���̍w���́A���{������capital
goods investments�E�E�E�}�N���o�ϊw�Ō��������Ƃ́A���{�������̂��Ƃł���A���Z�����̂��Ƃł͂Ȃ��B�v
�����̏d�v�Ȍ���v���E�E�E�@�����\���i�s��g��\���E���v�g��\���j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A���q���E�E�u�����̊�Ƃ͓������t�@�C�i���X���邽�߂Ɏ�����������B���̎������������邽�߂ɋ�s�Ɏx����Ȃ���Ȃ�Ȃ����z�ł���������p�́A���q���ł���B��Ƃ��x�������͉ݕ��z�ł���킳��Ă���A���̍w���͂̓C���t���[�V�����ɂ���Č������邽�߁A���ƂȂ鎑����p���������q���ł���B�@���q���������Ȃ�ƁA�����ݏo�������v���W�F�N�g�͂����Ȃ��Ȃ�B���Ȃ킿�A��s�ɗ��q���x��������ɁA�����Ƃ��`�������X�N��⏞���ė]�肠����v�������炷�����v���W�F�N�g�͂����Ȃ��Ȃ�B
�@���Ƃ���Ƃ��\���Ɍ����������Ă��Ă��A���q���͏d�v�ł���B���q���́A��Ƃ̎����Ă��邨�����@���p�A���Ȃ킿��Ƃ��������s�킸�ɁA���{�����̊�Ƃɂ��̂�����݂��Ă����Ȃ������ꂽ�͂��̎����ł���B
���q���Ə����̉ݕ��z�̊���������݉��l�̊W
�S�D�R ���{�s��̋ύt
�T�@��ʋύt
�U�@��{�I���S�ٗp���f���̊g��
�U�D�P���{
�U�D�Q�}�l�[�T�v���C
�U�D�R�f�Ձ@
��3��
���S�ٗp���f���̉��p
�P�@�����Ԏ�
�P�D���o��
�Q�D�����J���o��
�R�D�卑�J���o��
�Q�@�f�ՐԎ�
�@�@�f�ՐԎ��ƍ����Ԏ��́A���ΓI�Ɏ����I�Ȃ��̂ł���B���{�̍����Ԏ��͑傫�����A�f�Ղ͍����ł���B
�@�Ƃ��낪�A�X�e�B�O���b�c�́Ap.148 �}3�|6�@�����Ԏ��Ɩf�ՐԎ��@�̓��v�������A����̓�͘A�����ē����Ă��邪�A����͋��R�ł͂Ȃ���Ƃ��Ƃ��Ȃ��ɏ����Ă���B��J���o�ςɂ����đ��ł��Ƃ��Ȃ�Ȃ������x�o�����i���邢�͍����x�o�팸���Ƃ��Ȃ�Ȃ����Łj�́A�f�ՐԎ��ƊC�O����̎����̑����������炷��Ƃ������A�}3�|6�������Ă���̂́A�����Ԏ����}���ɑ�����Ƃ��ɖf�ՐԎ����}���Ɍ������Ă��鎞���������Ă���B�����Ԏ��Ɩf�ՐԎ��́A�K���������s�I�ɘA������̂ł͂Ȃ��A����������̂ł���B
���R�̑��ݘA��(���s�I�A��)�W�́A�f�ՐԎ��ƍ����Ԏ��̑��݂̊Ԃɂ���̂ł͂Ȃ��B
�����A�u�C�O����̎ؓ���̑������f�ՐԎ��̑������Ӗ�����v�Ƃ����̂͂��̂Ƃ���ŁA�܂��ɒ��ړI�ȑΉ��W�ɂ���Ƃ�����B�Ȃ����H
2.1 ���{�̗��o��
�@�f�Ղ̃t���[�Ǝ��{�̗��o��(�t���[)�̘A��(�����P�[�W)�́A�s��o�ό����̕K�R�I���ʁA�s��o�ό������̂��̂ł���B
�A�����J�E�E�E�f�ՐԎ����A��(�x����)�|�A�o�i���j�����{(��)����
��f�ՐԎ��ƊC�O����̎��{�����́A�������̂��̌������ł���킵���ɉ߂��Ȃ���̂ł���B
�u���A���}�C�i�X���A�o�i���f�ՐԎ��j�́A���{(��)�����Ɠ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�ƁB����́A���{�I�ȍP��������ƁB
�X�e�B�O���b�c�������Ă͂��Ȃ����A�t�ɓ��{�ɂ��Č����A
�@�f�Ս������A�o�|�A�������{�i���j���o�@�Ƃ������ƂɂȂ�B
��f�Ս����ƊC�O�ւ̎��{���o�́A�������̂��̌������ł���킵���ɉ߂��Ȃ���ƁB
�X�e�B�O���b�c���ŋ߂̓��{�ɂ��āA
�u���݂ł́A���{�͗A��������A�o���s���Ă���A���̍��z�͓��{����̎��{���o�z�ɓ������Ȃ��Ă���v�ƁB
2.2 �בփ��[�g
p.151�@��בփ��[�g�����i�A���Ȃ킿��̒ʉ݂̑��Ή��i�ł���B���Ȃ킿�A�����鉿�i�Ɠ��l�ɁA�בփ��[�g�����v�E�����̖@���ɂ�茈�肳��飂ƁB
�@�����A�Ȃ��A����Ƃ���1�h��200�~�O��ŁA�ʂ̎����ɂ�1�h��100�~�O��Ȃ̂��A�h�C�c�Ɖ~�Ƃ̑��Ή��i�̓���I�ȕϓ�����ʂ���ǓI�ω��̔w�i�ɂ��邱�Ƃ͂Ȃɂ��A�Ƃ������Ƃ́A���ς�炸�X�e�B�O���b�c�ł͂����炩�ɂ���Ȃ��B���̔w��ɂ���A���Ă̘J���̐��Y�͂̕ω��ɂ܂Ō������i�߂��Ȃ��B
�@���̎��X�̈בփ��[�g�̕ω����K�肷��v���ɂ́A���i�̗A�o��(���Ă̏��i���i�E�E�E���������Ă��̐��Y�̂��߂̐��Y�͊i���Ȃ�))�A�f�Ս��z�������U�������������z�����E���q���ȂǑ��l�ȗv�����֘A���Ă��邪�A�Ȃ���ǓI�ɂ���͈͓��ɂ���A�܂������I�ɕω�����̂��A���̂��Ƃ̌����̂��߂ɂ́A���i���i�̊�b�𐬂��J���Ƃ��̐��Y�͂��������ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
P�D160-161�̓��{��ŃN���[�Y�A�b�v�����Ɠ��{�̖f�Վ��x�̒����X����́A�q�ϓI�f�[�^�Ƃ��̕��͂ł���A�����[���B
p.167
��O�͂̌��_�����ŁA��O�͂̊e�����ł͂܂������c�_����Ă��Ȃ��������Ƃ��A���������đ�O�͂̂���܂ł̏��q����͕K�R�I�Ȍ��_�Ƃ��ďo�Ă��Ȃ����Ƃ��A�u�{�͂œ�����}�N���o�ϊw��7�Ԗڂ̈ӌ��̈�v�͌o�ϐ����Ɋւ�����̂ł���v�Ƃ����`�ŏq�ׂ���B���e�I�ɂ́A�܂��ɘJ���̐��Y�͂̔��B�������o�ϐ������Ƃ������Ƃ��q�ׂĂ���B���Ȃ킿�A
�@��o�ϐ���Growth
���������̏㏸�́A���Y���̏㏸��K�v�Ƃ���B���Y���̏㏸�́A�����J���iR&D�j�ւ̎x�o�A�V�����Z�p�E�v�����g�E�ݔ��E�C���t���X�g���N�`���[�ւ̓����A�����ĘJ���͂̏n���̌����K�v�Ƃ���v�ƁB
�@�Ƃ��낪�A���̐���������ǂނƁA�o�ϐ����̏��v���̐����Ƃ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B
�������A�����Ԃ��Ƃ̑�13�͂ł́A�͑S�̂Łu�o�ϐ����Ɛ��Y���v����舵���Ă���B�����ł̓��e���������ƂȂ�B
----------------------�@
��Q�� ���Ƃƃ}�N���o�ϊw
�P�@�}�N���o�σ��f���F�Ę_
p.176�u���Ƃ̊�{�I�Ȑ����́A�J���̋����Ȑ����邢�͎��v�Ȑ��̃V�t�g�ɑ��āA�������\�����₩�ɂ͒������ꂸ�A���̌��ʁA���Ȃ��Ƃ����炭�̊ԁA�܂����ɂ͂��Ȃ蒷���Ԃɂ킽���āA�s������ɂ�����J�����v���J��������菬�����Ƃ������Ƃ��N���肤��A�Ƃ������Ƃł���v�ƁB
�@���Ƃ̌������A����ł͢�������\�����₩�ɒ���������Ȃ����Ƃɋ��߂��Ă���B
���{�̒~�ρA�ߏ萶�Y�ȂǁA�s��z���͂��鐶�Y�ߏ�E���{�ߏ�ɂ́A�܂��A���{�~�ςɔ����Đi�W���鐶�Y�͂̔��B�A���{�̗L�@�I�\���̍��x���Ƃ��������ΓI�ߏ�l����n�o����@���́A�m��Ȃ����A��������Ă���B
p.177�u�����̂悤�ɂ��₭��������鉿�i���������ŁA�������Ƃ�����������Ȃ����i������B�����́A�Ƃ�킯�������Ƃ�����������Ȃ����i�ł���B���Ƃ��A�����J�ł́A�J���g���͂����@��3�N�̒����_�������ł���B�܂��A�J���g�������݂��Ȃ���Ƃ��A�J���҂ɔN���ɂ��̒���������`���A���ɂ����ƒ�����̘J���҂��ق�����A���i���v�����������Ƃ��Ă��A����ɔ������Ē����𑬂₩�Ɉ���������Ƃ����s�����Ƃ邱�Ƃ��S�O����v�ƁB
�@�����ł��A���Ƃ̌������A�����̍d�����ɋ��߂��Ă���B
�@�����āA���́u�����̍d�����v���K��������̂Ƃ��āA�Œ�����@������Ƃ����B����ۂɂ́A���Ƃ��ٗp��i�ق���j��������ቺ�����邱�Ƃ�]�Ƃ��Ă��A�Œ�����@�������W���Ă��飂ƁB
�@����Ȃ�A��Œ�����@����Ȃ����A���Ƃ͂Ȃ��Ȃ邩�A�����Ȃ��Ȃ�̂��H�@���������Ȃ��u�Œ�����@�v�����肳�ꂽ�̂��H�@���̌o�ϊw�I�𖾂Ȃ��ɁA��Œ�����@��⢒����̍d������ɁA���Ƃ̌��������߂�̂́A�������ׂ����Ɖ𖾂��ׂ����Ƃ̕����ł����Ȃ��B
�u�ߋ�15�N�Ԃɂ킽���ă��[���b�p�����̎��Ɨ��͔��ɍ������ł��������A���̗��R�͕����I�ɂ������̍d�����ɂ���A�ƈ�ʂɂ͍l�����Ă���v�ƁB
�@����ł́A�X�e�B�O���b�c�͂����ł͂Ȃ��̂��H
�@�u�����I�ɂ́v�Ƃ������A�����Ȃ�Ӗ��������H
���2���ŏœ_�����Ă���̂́A1�T�ԁA�P�����A�����������N�ԂƂ����^�C���E�X�p���ł���Z���ł���B�Z���ɂ����ẮA���{�X�g�b�N�̐����̑����͔��ɏ����������ł���Ɖ��肳��飂ƁB
�@1�T�ԁA1�����Ȃ�A�J�������ʂ��傫���ω�����͂����Ȃ��B���łɑO�Ɍ������{�̐�㓝�v������킩��悤�ɁA�l�Ԃ̐��Y�A�J���ҁA�ΘJ�҂̐��Y(�l���ϓ�)�́A���������Z���Ԃŕω�������̂ł͂Ȃ��B�J���҂̐���1�T�Ԃ�1�����ŋ}�ɑ�������A�}�Ɍ������肷��킯���Ȃ��B
�Z���Ԃ��l�@����Ȃ�A�J�����������Ƒz�肷��̂͂ނ��뎩�R�ł���B
���������Z���ԂɎ��Ƃ�����������A�ٗp�̑��傪���������肷��Ƃ���A����́A�J���̋����̑�(���Ȃ킿�������l�Ԃ̏A�Ɖ\�l���E�L�D�Ґl���Ȃ�)�̕ϓ��ł͂Ȃ��A���i�s��̑��A���{�̑��Ɍ��������邾�낤�B������A�𖾂��ׂ��́A�Z���I�Ȃ��̂Ƃ��ǂ��̏��i�s��̕ω��̗v���ł���A���{�̑��̗v���ł��낤�B�Ƃ��낪�A���̌����͂Ȃ��B
�@����Ɗ֘A���āA�����ł́A���Ƃ̏d�v�Ȍ����Ƃ��Ă̎��{�~�ρE���Y�͂̍��x�����A�l�@�͈͂��珜�O���Ă��܂��Ă���B���ɐ��Y�͂̔��W���ɖ��Ȏ����z�肵�Ă��邱�ƂɂȂ낤�B�������A���ł�19���I�ȗ��A10�N�����̌o�Ϗz�Ȃǂ�����A���Y�͏㏸�Ǝ��{�~�ς̂����܂�̊ɖ����́A���������Ƃ������ƂɂȂ낤�B
�������A�����̌o�ς̓����̂Ȃ��ł́A�ŋ߂ɂȂ�Ȃ�ق�(���{��`�I���Y�̍��x���ɔ���)�A�����N������A���{�~�ς͖����ł�����̂ł͂Ȃ��A�܂�����ɔ������{�̗L�@�I�\���̕ω�(�Z�p�I���W�Ǝ��{�\���̕ω�)�������ł��Ȃ����낤�B
���Ƃ������炷�d�v�ȗv�����̏ۂ��Ă����A���Ɍ���ꂽ����Ɣ����v�������������Ȃ����ƂɂȂ�B
�����������̂ł͂Ȃ��A������������Ƃ������Ƃł͂Ȃ����B
2�@�J���s��
p.178 ��Ȃ�炩�̗��R�ɂ��A�J�����v�Ȑ����ˑR�����ɃV�t�g���A���̒��������ɂ��������v�����J���҂̐������������Ƃ��悤��Ƃ����B
�@
���̉��肻�̂��̂ɖ��͂Ȃ����H
�@�J�����v���ˑR�������́A�s��́u�ˑR�v�̕ω��̊��ł���A���Y����K�v���E�J������K�v����������������ł͂Ȃ��̂��H
�@���Ƃ��A����܂ŏ��i���w�����Ă����n�悪��ЊQ�ŋ}���Ɏ��v�����炵���ꍇ�A�����������Ƃ͂��肤�邾�낤�B���̏ꍇ�A�s�ꎩ�̂��k�������̂ŁA�����K�͂̐��Y�ł͉ߏ�ɂȂ�B������A���̏����������Ȃ�A���Y�����炵�A�J�������炷�A�Ƃ����͕̂K�R�ƂȂ�B
�@���̘J���̌��炵���ɂ́A�����B��͕��ʂ̂����ŁA��萔�̘J���҂����ق���B�����ł��肤��̂́A���[�N�V�F�A�����O�ŁA�S�ٗp�J���҂̘J�����Ԃ�Z�k��(����ɉ����Ĕ䗦�I�ɒ��������������邪)�A�ٗp���͈̂ێ����邱�Ƃł���B
�@��˔��I��Ȍ����Ȃ�A����ɂӂ��킵���Ή��̎d�������낤�B
�@����ɂ������č\���I�Ȍ����Ȃ�A����ɂӂ��킵���Ή��̎d�������낤�B
P.179�ŁA�u�J�����v�����Ɋ֘A����Љ�I���̑啔���́A�o�ϓI�ȕ��S���ꕔ�̐l�����ɉߏd�ɏW�����Ă��܂����Ƃ��琶����v�Ƃ����̂́A���Ɉꎞ�I�˔��I�Ȍ����ɂ��u�J�����v�����v�̏ꍇ�ɂ͓��Ă͂܂��Ă��A��J�����v�������ʂɂ͓��Ă͂܂�Ȃ����낤�B
p.180�@�u�����I���Ɓv�Ƣ���I���ƣ�̒�`�E�����������܂��ł���A�����������̈Ӗ����������ӓI�ł���B
�@��J�����v���������A�J�����v�Ȑ����E�E�E�����փV�t�g�����Ƃ��悤��Ƃ��A���̏ꍇ�A����������₩�ɒ��������Ȃ�A�V�����ύt�ɂ����āA������w2/�o�ɉ������A�ٗp�ʂ͂k2�Ɍ�������B���̏ꍇ�ɂ�����ٗp�̌����͎����I���Ƃł��飂ƁB
�@
����₩����Ɓu�����I�v�Ƃ����̂ł���B����͢��������i���H�����^���[�j�Ɋւ���Ђǂ���`�ł͂Ȃ����H
�u�ΏƓI�ɁA�J�����v�Ȑ��̃V�t�g�����������1/�o�ɂƂǂ܂�Ȃ�A�ٗp�ʂ͂k3�܂Ō�������B���̒��������ł́A���������l�͍������k1�ɂƂǂ܂��Ă��邪�A�ނ�̂��ׂĂ��E����킯�ł͂Ȃ��B���ꂪ���I���Ƃł���involuntary unemployment�v�ƁB
p.181 ��c�_��P���ɂ��邽�߂ɁA�ȉ��̕��͂ł́A�J����1�l����̘J�����Ԃ͈��ł���A���J�����Ԃւ̎��v�̌����͒��ړI�Ɍٗp�����Ɍ��т��Ɖ��裂��Ă���B
�@
����́A���{��`�I�s��o�ςł������ʂ̉���ł���B
�@�������A�Ȃ��A��J�����Ԃ͈�裂łȂ���Ȃ�Ȃ��̂��H
�@�Љ�̔��W(���Y�͂̔��B)�ƂƂ��ɁA�l�ނ͘J�����Ԃ����炵�Ă����̂ł͂Ȃ����B�܂��ɁA�Љ�̑S�̓I���W�́A�J�����ԒZ�k�������炵�Ă����A�]�ɂƎ��R�����ꂾ�����i�ł��A�l�ԓI�Ȃ̂ł͂Ȃ����B
���Y��(�Ȋw�Z�p�̔��B)�́A��菭�Ȃ��J�����Ԃł��L���Ȑ�����ۏႷ��̂ł͂Ȃ����H
�Q�D�P ���Ƃƒ����̍d����
�q�ϓI�f�[�^�E����
p.181 �u���������A���Ȃ킿���������̕ω����ς݂̒����f�[�^�Ō���A�o�Ϗ�Ԃ��ω����Ă��A�����͂���߂Ă킸�������ω����Ȃ����Ƃ��킩��B�}4-3�́A1982�N����1994�N�̃A�����J�̎��������Ǝ��Ɨ���`�������̂ł���B���̊��ԂɁA���Ɨ���5.3��������9.7�p�[�Z���g�̊Ԃ�ϓ����Ă��邪�A���������͂قƂ�Lj��ł���B��ʂ̎��Ƃ����݂��Ă����勰�Q���ɂ����Ă����A���������͉������Ȃ����A����߂Ă킸�������ቺ���Ȃ������B�v
�@����͌��R���鎖���ł���B
�@���̌��R���鎖������A���_���o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���̌��R���鎖�����Ӗ����Ă��邱�Ƃ́A
���ɁA�����������d���I�����玸�Ɨ��̕ϓ�����������̂ł��Ȃ��A�Ƃ������Ƃł���B�Ȃ��Ȃ�A�������������̑S���Ԃ�ʂ��āA�قڈ���I�ɐ��ڂ��A�傫�ȕω����Ȃ��ɂ�������炸�A�i�C�ϓ��A�i�C�z�͌����邩��ł���B�����������d���I�ŕω����Ȃ��Ƃ������������̒��ŁA���Ɨ��ɂ͑傫�ȏz�I�ϓ��E�ω�������A�Ƃ������ƂȂ̂ł���B���̏z���̕ϓ��́A�]���āA�ʂ̗v���Ő������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
���ɁA���Ɨ��́A�z�I�ɕϓ�������ɂ��Ă��A���̊��Ԓ���ʂ��āA�Œ�ł�5.3���������Ƃ������R���鎖���ł���B�ÓT�h�o�ϊw���\�����A�}���N�X�����k�ɗ��_�������悤�Ɂi���{��`�I�~�ς̈�ʓI�@���F���{�̗L�@�I�\���̍��x���E���{�̏W�ϏW���E���ΓI�ߏ�l��=�Y�Ɨ\���R�̗ݐi�I���Y�j�A���{��`�I�s��o�ςɂ����ẮA���ΓI�ߏ�l��=�Y�Ɨ\���R���\���I�ɍ��o����A�ێ�����A�˂ɑ��݂���̂ł���B
�Ƃ��낪�A�X�e�B�O���b�c�́A����Ƃ́A�T�^�I�ɂ́A��������������Ȃ����ɘJ���̑����v�Ȑ����V�t�g���邱�Ƃɂ���Ĕ������飂ƁA���������A���Ƃ̔����������������������Ȃ�����Ƃɂ����Ă���B����́A�o�ϓI�_���̐����Ƃ������́A���{��`�ٌ̕�_�ɉ߂��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B
�@�����A���̔ᔻ�������Ă��A��J���̑����v�Ȑ��̃V�t�g�́A�T�^�I�ɂ́A�Y�o�ʂ��ω����邱�Ƃɂ���Ĕ������飂ƕt�������Ă���B
�@�܂��ɁA��Y�o�ʂ̕ω���������A���Ȃ킿�A���R�Ȏs�ꋣ���̂Ȃ��ł̐��Y�L���p�V�e�B�̕ω��Ǝs��̑傫���������A���Ƃ��Ƃ����ł���B������̍d������Ɏ��Ƃ̌��������߂����Ƃ������ŏC�����Ă���̂ł���B
�@
�Q�D�Q
���ƂƑ��J�������@
p.183�@��قƂ�ǂ̎��Ƃ͘J�����v�Ȑ����}���������V�t�g���琶���飂ƌJ��Ԃ��B���Ȃ킿�A���Ƃ̒Z���I�ȗv���������悤�Ƃ��Ȃ��B
���{��`���E�ɍP��I�Ȃ���p�[�Z���g�ȏ�̎��Ɨ��͂ǂ��Ȃ�̂��A�����������Ȃ��B
�u�Z���Ԃő��J���������啝�ɃV�t�g����悤�ȏꍇ������B���Ƃ��A1990�N�㏉���̃C�X���G���ł́A���V�A����̃��_���l�̑�ʈږ��ɂ��A�J���͂�10���ȏ㑝�������v�ƁB
�P���Ɉږ��������A�J���͂���ΓI�Ɉꎞ�I�ɑ��債���̂�����A����������E�ꂪ�Ȃ��͓̂��R�ł���B������A���������J�������̋}���ȕω��ɂ�鎸�Ƃ̑����́A���������̒����Ƃ͊W�Ȃ��B�Ƃ��낪�A���̏ꍇ���A���̂悤�Ȍ��t���}�������B
�u���̂��ߒZ���ɂ����ẮA�����������\���ɂ͑��₩�ɒ������ꂸ�A���Ƃ����債���v�ƁB
���Ƃƒ����������x�Ƃ������Œ�ϔO�Ō������Ă���Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����́A�o�ϊw�̗��_�ł͂Ȃ����낤�B
�܂��ɁA���������̒��������Ƃ̑����ƊW�Ȃ����Ƃ́A�X�e�B�O���b�c���w�E������̕��͂̂Ƃ���ł���B���Ȃ킿�A
�u����ɒ��ڂ��ׂ������́A���̍����Ɨ���5�N�Ԃ��o���ɂ��Ƃ̐������������Ƃł���B�������A���̒����́A���������̒ቺ�ł͂Ȃ��A(�J�������̑����ߍ��킹��悤��)�J�����v�Ȑ��̃V�t�g�ɂ���Ď������ꂽ�������傫�������v�ƁB
�܂��ɁA��J�����v�Ȑ��̃V�t�g��́A��قǂ������悤�ɢ�Y�o�ʂ��ω����邱�ƣ�A���Ȃ킿���Y�̊g��ɂ���āA�K�R�I�ɘJ���͎��v���g�傷��̂ł���B
p.184 Close-Up�u�f�V�ƌٗp���v
�@�����ł͂P�X�X�S�N3���̐�i7�J��������c�i������f�V�j�̃f�g���C�g��c�ɃR�����g���Ă���B����E�I�Ȍٗp���Ƃ��̑���c�_����j��ŏ��̌ٗp�T�~�b�g�ƂȂ�����ƁB
����ہA1980�N�ォ��1990�N��ɂ����Ẵ��[���b�p�́A�������̎��ƂɔY�܂���Ă����B�A�C�������h�ƃX�y�C���ł́A5�l�Ɉ�l�ɋ߂����������Ǝ҂Ƃ�����Ԃ��Â��Ă����B�I�����_�̌������Ɠ��v�͂�����͂܂��Ȑ������������A�g�̏�Q�ғo�^�����Ԃ��������B���Ă����B�I�����_�ł́A�g�̏�Q�ҋ��t�����ƕی����t����������A���R���ɂ��������������Ă����̂ŁA���Ǝ҂̑������A���ƕی����t�ł͂Ȃ��g�̏�Q�ҋ��t�̐\���������Ȃ��Ă����̂ł���(���ۂ̎��Ɨ��́A5�l�ɂP�l�Ƃ�������������)�B�
p.185
�u�f�V�����́A���̎�v�ȗv�������n���J���҂ƒ�n���J���҂ɂ���_�ɂ��Ă͓��ӂ��B���Ȃ킿�A��(��)�n���J���҂̋����ߏ��E����ɏ\���Ȃقǂɂ́A�ނ�ɂ���������v�Ȑ����E���փV�t�g���Ă��Ȃ������B�ނ��떢(��)�n���J���҂̎��v�Ȑ��������ɃV�t�g�����������������̂ł���v�ƁB
����́A�Ȋw�Z�p�̔��W�A���̐��Y�ߒ��ւ̓����Ƃ����J���̐��Y�͂̔��B�̕K�R�I���ʂł͂Ȃ����H�@���{��`�̔��B�A����ɔ����~�ρE�W�ϏW���Ǝ��{�̗L�@�I�\���̍��x���Ƃ́A���n���J���҂̑�Q���ߏ�ɂ��邱�Ƃł͂Ȃ��̂��B
�����A�X�e�B�O���b�c���Љ��悤�ɁA���̌����Ƃ��āu�ł��L�������ꂽ�̂́A�����Ƃ̌������Z�p�i���ɋA������̂ł���B���Ȃ킿�A(�R���s���[�^�[���g����\�͂̂悤��)�n���x�̍����J���҂ɑ�����v���A���������n���������Ȃ��J���҂ɑ�����v�ɔ䂵�đ����������Ƃ������Ƃ̌����ł���A�Ƃ�����̂ł���v
���̈�ʓI�Ȍ���������킯�ɂ͂����Ȃ��B
�Ƃ��낪�A�X�e�B�O���b�c�́A�����܂ł��A�����̍d�����A�Œ�����Ȃǂ������Ɨ��̌����Ƃ��Ď����o���A��������B���Ȃ킿�A�����͂������������l�X�ɂ��邩�̂悤�ł���B
�u�A�����J�ł͖��n���J���̎��������͒ቺ�������A���[���b�p�ł͍������ɐݒ肳�ꂽ�Œ�������n���x�̒Ⴂ�J���҂̎����������������邱�Ƃ�W�����B�ނ���1970�N�ォ��1990�N��ɂ����Čٗp��(�]�ƈ�)�̎��������́A�A�����J�ł͂قƂ�ǒ���Ă����̂ɂ������āA���[���b�p�ł͖��N��2���㏸�������Ă����v�ƁB
�X�e�B�O���b�c�̓A�����J�̎��Ԃ𐳓�������B�@
�A�����J�̘J���҂̎��������̒ቺ�����邪�A�ΘJ�҂̎����������ቺ�����������������Ă��A�����̐l������������A�ٗp�n�o�����邩�炢���Ƃ������Ƃ̂悤�ł���B���Ȃ킿�A
�u�@1993�N����1995�N�ɂ�����700���l�ȏ�̌ٗp�n�o���Ȃ��ꂽ�A�����J�Ƃ͑ΏƓI�ɁA1990�N��O���̃��[���b�p�ł͖��ԕ���̑��ٗp�n�o�͂قƂ�ǃ[���ł������B���[���b�p�̌ٗp�����Ɋւ��āE�E�E�L��������Ă��錩���̈�́A���[���b�p�̘J���s��̍d�����ɂ��̌��������߂Ă���B���[���b�p�ł́A��Ƃ��J���҂����ق��邱�Ƃ͔��ɍ���ł��邪�A���������傫�Ȍٗp�ۏ�̗��ʂɂ́A��Ƃ��ٗp�J���Ґ��𑝂₷���ƂɊւ��Đ_�o���ɂȂ�Ƃ�����肪����B���Ȃ킿�A���[���b�p�ł́A�E��ꂽ�l�͏��Ȃ����A�E���l�͏\���ȍK����������̂ł���B���[���b�p��������́A��(��)�n���J���ҊԂ̕s����(�������������[����)�Ɛl�I�����̂���߂Đ[���ȉߏ����p�Ƃ����o�ό������̑r���������炵�Ă���悤�ł���v�ƁB
�I�����_�Ȃǂł́A��i�I�ȃ��[�N�V�F�A�����O��������B�X�e�B�O���b�c�̏�L�̂悤�Ȏw�E�́A���łɍ����������̂ł͂Ȃ����B
��.185
�R�@�Z���ɂ����鐶�Y���s��
��.185
���āA���悢��X�e�B�O���b�c���A���Ƃ̊�{�I�Ȍ����ł��颎Y�o�ʂ̕ω���̖��ɂƂ肩����B
�܂��A�u���Y���s�ꂩ��c�_���n�߂悤�v�ƁB
p.186
�����ŁA�ǂ̂悤�ȉ���łǂ̂悤�Ȑ}����邩�Ƃ����ƁA
�܂��A�u���S�ٗp�Y�o�ʁv�x���̒����𐂒����`���f�i���̂����͑��̐}�ł���т��ėp�����Ă���j�B
�}4-5�Ő����Ŏ��̂悤�ɂ����B�u���S�ٗp�Y�o�ʂx���́A�����ȑ������Ȑ��ɂ���Č��肳���v�ƁB
������Ƒ҂��ė~�����B
�������Ƃ������Ƃ́A�����o�ϑS�̂̊��S�ٗp��Ԃł̑����Y���̂��Ƃł���͂����B�Ƃ���A���̐��Y�ɂ́A���̎��X�̐��Y�͐����ɉ����āA�K�����̘J�����Ԃ��Ώۉ�����Ă���͂����B���Ȃ킿�A���̘J�����Ԃ̉ݕ��\���Ƃ��Ă̕����̂��鐅�������m�ɂ�����͈̔͂ɂ���͂����B
�ɂ�������炸�A�}�Ƃ��̐����ł́A���������́A���������[�������͍ی��Ȃ������܂ŁA���R�ɂ��肤�邩�̂悤�ȁu�����̑������Ȑ��v�Ƃ́A�܂���������z�̎Y���ł����Ȃ��B
���������������������͈Ӗ��̂��邱�ƂȂ̂��H�u���S�ٗp��ԁv�ł̎Y�o�ʁi�x���j�́A�����Ȃ镨�������i�o�j�ł��\�Ƃ��Ă���̂����A��������������ł͂Ȃ����H
���S�ٗp�����̎Y�o�ʂ́A�����������[���Ȃǂł��A�܂�����Ȃ��������������ł����肤��̂�(�`����Ă��鐂���̎��H�͂��̂��Ƃ��Ӗ�����̂���)�B����̔������悸���Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B
�Ƃ��낪�A�����ŁA�u�J���s��̒Z�����͂̏ꍇ�Ɠ��l�ɁA���Y���s��̒Z�����͂ɂ����āA�����͌Œ肳��Ă���Ɖ��肷��v�̂ł���B�u���Ȃ킿�Z���ɂ����ẮA�����v�Ȑ��Ƒ������Ȑ����ϓ����Ă������͂قƂ�Ǖω����Ȃ��v�ƁB
���̉���Ȃ�A�u���S�ٗp�Y�o�ʁv�x�����Œ肵�Ă����āA�����������[��������ɍ��������܂ʼn\�ł��邩�̂悤�Ȏ����������̂�����ł���B
p.188 �u���v������������ꍇ�ɂ̓C���t���[�V���������ɂȂ�v�ƁB
�@�����㏸�ƃC���t���[�V�����Ƃ͓������H
�R�D�P ���Y�\�͂������o��
p.188 ����S�ٗp�Y�o�ʈȉ��̐�����ɂ���o�ςŁA�ٗp�̂��߂ɂȂɂ������炢�����A
p.189�@��������Ď҂����ׂ��I�����͖��炩����Ƃ����B�{�����H
�@�@�@�i.M.�P�C���Y�̌��t�A�u�����ł́A�����݂͂Ȏ���ł��܂��v�Ƃ������t�����p���āA�o�ς̎������߂ɔC���钷���I������́u���Ǝ҂ɂ͂قƂ�LjԂ߂ɂ͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ��āA������v�Ȑ����E���V�t�g�����飐�������B
����ł́A�X�e�B�O���b�c�������o���̂͂Ȃɂ��B�h�s�o�u��������ċ��a�}�u�b�V���������s�������Ƃ𐳓�������悤�Ȃ��Ƃł���B���Ȃ킿�A���h�x�o�����A���Ƃ��Ă�����̂ł���B���ꂪ�A�m�[�x���o�ϊw�܂�������o�ϊw�҂��A��ʓI�Ȍo�ϊw���ȏ��Ō������Ƃ��H�m�[�x���܂̂��������̊���̂��Ƃ͂Ȃ����̂��H���ɂ������锽�Ȃ���m�[�x���܂͐ݒ肳�ꂽ�̂��H
�Z���I���ʂ͕ʂƂ��āA���h�x�o�����������I�ɂ����炷���͉̂��Ȃ̂��H
�������{�x�o�ł��A�����̐l�ԓI�o�ρE�l�ԓI�Ȋw�Z�p���̍\�z�̂��߂̎x�o�����肤��ł͂Ȃ����B
�@�@
�@�u(���^�̕��������ɂ�����)����A�����A���{�x�o�A���邢�͏��A�o�̎��v��������ǂ̂悤�ȏo�������A�����v�Ȑ����E���V�t�g������v�ƁA�܂���ʓI�ȑI���\�����w�E����B�Ƃ��낪�A�������ł���B
�@�u���{�ɂƂ��Ă̈�̑I�����́A���{�x�o�̑����ł���B���Ƃ��A���h�x�o����������A(�����镨��������)�����v�͑������A�����v�Ȑ��͉E���V�t�g����B���̂Ƃ��o�ςɉߏ萶�Y�\�͂�����ꍇ�ɂ́A�����v�Ȑ��̃V�t�g�͎Y�o�ʂ�������v�ƁB
�@�i�`�X�E�h�C�c�������x�o(�R������)�ŁA�u�Y�o�ʂ������v�A�킸�����N�Ţ���S�ٗp��ԣ�������炵�A�i�C�������B�������A���̌�ɗ������̂͂Ȃ����̂��H
�@�u�b�V�������̍��h�x�o�����̌�ɗ����̂́A��`�Ȃ��C���N�U���푈�ł͂Ȃ������̂��B��ʔj��͂ǂ��ɂ��邩�H���܂��Ɍ������Ă͂��Ȃ��ł͂Ȃ����B
�R�D�R
�s��̋����T�C�h
�@����Ƃ��ɂ���������Ƃ���Ȃ��B
�S�@���{�s��Ƃ̘A��
p.192�@�J���s��Ɛ��Y���s��E�E�E����̓�̎s��͎��{�s��Əd�v�ȓ_�ŘA��(�����P�[�W)���Ă��飂ƁB���̂Ƃ��肾���A�܂��Ɂu�ǂ̂悤�Ɂv���������ƂȂ�B
����{�s��ɂ����ė��q���́A���Z����monetary policy�ɂ���ĉe�����飂ƁB����͂ǂ��ł��낤�B�����A���q���́A���{�⒆����s���̋��Z����ɂ���Ăǂ��܂ʼne�����A�ǂ��܂Ŏ����I�ȉ^���@���ɏ]���̂��A���ꂪ���ł͂Ȃ����B
�@�P�ɢ�e�����飂Ƃ����̂́A���ۂ̐����ł����Ȃ��B
�Â��āA
�u���Z����Ƃ́A�}�l�[�T�v���C(�ݕ�������)�Ɨ��q���̃R���g���[���ɂ������ĐӔC�����{�@���ł����A�M�������x������Federal Reserve Board�����{����s�ׂł���v�ƁB
�}�l�[�T�v���C�́A�ǂ̒��x�܂Ő��{�@�ւ̎��{����s�ׂɂ���č��E�����̂��H�����I���̉\���́A�ǂ͈̔͂��H
�u�A���i�eed�j�����q�����㉺�����A���Y���s��ƘJ���s��ɏd�v�ȉe�����y�ڂ����Ƃ��ł����v�Ƃ������A��㉺�����飊�͂Ȃɂ��H��㉺�����飂��Ƃƌo�Ϗz�E�����̌o�ώЉ�̕K�v���̕ϓ��Ƃ͂ǂ̂悤�ɂ������̂��B�����Ƃ��̐S�̂��Ƃ����m�ł͂Ȃ��B
p.192-193�u�A�₪�A�o�ϊ����͒�؋C���ł���ƍl�����Ƃ��ɂ́A�A��͗��q���ቺ��I�����邩������Ȃ��v�Ƃ����B
�@���{�ł́A�\���I�s�����ŁA���₪���ɒႢ���q���Ɋׂ�����(����ȏ�ɗ��q�������������邱�ƂȂǂł��Ȃ��悤�Ȓᗘ�q���Ɋׂ�����)�A�������ԁA�����ł��Ȃ������ł͂Ȃ����B�܂��A����ȏ�ɗ��q�������������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ł͂Ȃ����B
�@���q�������������Ă��A�]�莑��(�]�莑�{)����悤�Ƃ����Ƃ��o�����Ȃ�������A���ᗘ�q���͑����B
�����A���{�����v�����ƌQ�̏o��(�s��̊J��E���Y�g��E�����g��)�������A���q�������グ(�㏸)���\�ɂ���B
p.193
������A�A�₪�C���t�����̏㏸�����O���Ă����Ȃ�A�ʏ�A�A��͗��q���������グ�飂Ƃ����B����͂ǂ̂Ƃ���Ƃ��āA�u�グ���v�A����сu�ǂ�����ǂ��ցv���K�肷����̂͂Ȃɂ��H
�@�����ɁA�ݕt���{�������v�Ƃ̑��݊W�ł��낤�B
�@�ݕt���{������̂͂ǂ��ɂ��邩�H
�@�ݕt���{������͉̂��̂��߂Ɏ��{����邩�H�ǂ̒��x�̗��q���Ȃ�A��邩�B
�@����́A�ݕt���{�������(�Y�Ǝ��{)�̗����\��(������)�ɊW����B������(�c�Ɨ��v��)���Ⴏ��A���̒Ⴂ�͈͂Ŏx�������\�ȗ��q���̎���������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�@�Y�Ǝ��{�́A�ʏ�̗��_�I�z��ł́A�������҂��o������(�c�Ɨ��v)�̂Ȃ����痘�q���x��������ł���B
����Ȋ�Ƃ̏ꍇ�A���Ȃ炸�A�����i���c�Ɨ��v�j�����q�i���x�������E�������j�̊W���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����ŏ��߂Đ���ȉc�Ə��v(��Ǝҗ���Unternehmersgewinn)��������B
���{�̖@�l��Ɠ��v�����p����A���̂悤�ȊW�����藧���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�c�Ə��v���c�Ɨ��v�|�x�������E������
��T�\�@�t�����l�̍\��
|
|
(�P�ʁF���~�A��)
|
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
�@
|
�\����
|
�@
|
�\����
|
�@
|
�\����
|
�@
|
�\����
|
�@
|
�\����
|
|
�t�����l
|
2,704,127
|
100.0
|
2,675,469
|
100.0
|
2,766,294
|
100.0
|
2,568,917
|
100.0
|
2,578,691
|
100.0
|
|
�@�l����
|
2,033,555
|
75.2
|
2,019,617
|
75.5
|
2,025,373
|
73.2
|
1,928,607
|
75.1
|
1,899,189
|
73.7
|
|
�@�x�������E������
|
182,101
|
6.7
|
144,427
|
5.4
|
135,564
|
4.9
|
116,524
|
4.5
|
109,119
|
4.2
|
|
�@���Y�E�s���Y���ؗ�
|
273,979
|
10.2
|
249,560
|
9.3
|
256,993
|
9.3
|
247,182
|
9.6
|
258,664
|
10.0
|
|
�@�d�Ō���
|
143,363
|
5.3
|
113,593
|
4.3
|
107,279
|
3.9
|
97,515
|
3.8
|
100,415
|
3.9
|
|
�@�c�Ə��v
|
71,129
|
2.6
|
148,272
|
5.5
|
241,085
|
8.7
|
179,089
|
7.0
|
211,304
|
8.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�t�����l��
|
19.6
|
19.4
|
19.3
|
19.2
|
19.4
|
|
�J�����Y��(���~)
|
712
|
694
|
702
|
695
|
712
|
|
�i���j�P
|
�D�t�����l���l����{�x�������E�������{���Y�E�s���Y���ؗ��{�d�Ō��ہ{�c�Ə��v
|
|
�Q
|
�D�c�Ə��v���c�Ɨ��v�|�x�������E������
|
|
�R
|
|
�D�t�����l����
|
�t�����l
|
�~100
|
|
���㍂
|
|
|
�S
|
|
�D�J�����Y����
|
�t�����l
|
|
�]�ƈ���
|
|
|
�܂�A���q�����K�肷��d�v�ȗv���́A��Ƃ̉c�Ɗ����ł���A���̗������i�c�Ɨ��v���j�ł���B
�����A���q�����K�肷��̂́A�ǂꂾ���̗]�莑�����s��ɂ��邩�Ƃ����������̏����ł���B���{�ɂ�����ᗘ�q���́A�܂��ɂ��̋������ɂ����Ă͈��肵���������҂��]��(�����@���{�����߂�)�c��ȉߏ�̎����]�肪����A�Ƃ������Ƃł���B
���Ɨ��ƎY�o�ʂƂ̑��݊W�Ɋւ�����ؕ��͂���A�u�I�[�N���i�I�[�J���j�̖@���v�Ȃ���̂�����Ă���B
p.194�u���������ςȌo�����E�E�E�E�L���Ȃ̂��I�[�N���̖@���E�E�E�W�����\���哝�̂̌o�ώ���ψ���iCEA�j�ψ����߂��A�[�T�[�E�I�[�N��Arthur Okun�̖����Ƃ������́E�E�E�I�[�N���́A�p�[�Z���g�Ōv�������Y�o�ʂ̑������́A�������p�[�Z���g�Ōv���������Ɨ��̒ቺ���̖�2�{�ł��邱�Ƃ��v�Z�ɂ���Ď������B���Ȃ킿�A���Ɨ���7������6���֒ቺ����A�Y�o�ʂ�2����������̂ł���v�ƁB
�T�@����E����̃A�����J�o�ςɊw�ԃ}�N���o�ϊw�I���P
p.195�u�}�N���o�ϊw��̕��L������ɂ킽��R���Z���T�X�́A�����I�ɂ́A����E���Ȍ�̐��\�N�Ԃɂ����链�������o����ʂ��Č`�����ꂽ���̂ł���v�Ƃ����B
�@���̐��\�N�Ԃ̌o���Ō����ꂽ�R���Z���T�X�́A��������ᔻ�I�Ɍ�������ɒl����B
�T�D�P�@�P�l�f�B�������̌��Ł@
p.195 �X�e�B�O���b�c�́A�P�l�f�B��������1963�N�ȍ~�̏����Ō��ł��A�����v�Ȑ����E���V�t�g�����A���������������߂邱�ƂȂ��Y�o�ʂ��������ƕ]�����Ă���i�����̌o�ς��ߏ�ݔ��̏�ԂŁA���Y�I�ȘJ���҂Ƌ@��L�������Ă���ƍl���Ă��������̌o�όږ�̗\���������������j�ƁB
p.196�u���Ɨ���1965�N�ɂ�4.4���ɒቺ���A1960�N��㔼��ʂ���4���ȉ��ɂƂǂ܂����B����ɂ�1964�N����1966�N�̎���GDP�́A����5.5���Ƃ������ٓI�Ȑ������������v�ƁB
�@�������A���̓����̓x�g�i���푈�g��̎����������B�펞���������v���g�債�A�����Ɏh����^�����A�Ƃ����邾�낤�B
�@�����Ă��̋A���́A�A�����J�o�ς̑啝�Ԏ��A�j�N�\���V���b�N�Ɏ��铹�ł���B�Ƃ���A1960�N��̐����́A��ʓI�ɐ�������ŕ]������Ă͂Ȃ�Ȃ����낤�B
�T�D�Q ���[�K���������̐���
p.196-197 �u���[�K���������ɏA����1981�N�����̃A�����J�̃C���t�����́A���łɍ����ɒB���Ă������A�Ȃ��㏸�X���ɂ��������߁A�C���t���[�V�������~�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����l�����L�܂��Ă����B���̃C���t���[�V�����ɃX�g�b�v���������̂́A�A�M�������x������c���ł������|�[���E�{���J�[�iPaul�@Volker�j�̎�r�ł���Ƃ���Ă���i�������A���̉ߒ��ŁA�A�����J�o�ς͐��ň��̌i�C��ނɊׂ邱�ƂƂȂ����j�B�A��́A�M�p�̃A�x�C���r���e�B�[�i����\���j�̈������߂����q���̈����グ�Ƃ������s��i���Ƃ����B�{���J�[���C���t���[�V�����͎��������ƍl�������O�̗��q����20�����L�^�����B�E�E�E�A��̐���ɂ��A��Ƃ͓������팸���A�܂��ƌv�͎����Ԃ�Z��Ȃǂ̍w�����팸�����B�v
p.197 �u�����[�����ƂɁA�A�₪�����v�}������Ƃ��Ă����̂ɂ������A��������͌o�ς��h�����Â��Ă����B���Ȃ킿���[�K���哝�̂́A���Ŋz�E���邾���̐��{�x�o�̍팸�킸�ɁA���ł��s�����B�������A�������q���㏸�̌����́A���ł̌��ʂE����ȏ�̂��̂ł���A�E�E�E�����v�Ȑ��͍����V�t�g�����B�v
�u���̂��߁A�A�����J�͑傫�Ȍi�C��ނɊׂ����B���Ɨ���11�����A�n��ɂ���Ă�20���ɒB�����B���������ʂŁA���̌i�C��ނ��C���t���}�������͔��ɑ傫���A1980�N�ɑ���13���ɒB���Ă����C���t�������A1983�N�ɂ͂킸����3.2���܂Œቺ�������B�v
�T�D�R 1991�N�̌i�C���
�T�D�S �o�ς��h�����邽�߂̍����Ԏ��팸
�@1993-1994.�N�����g���o�ω���
�@�u�N�����g����1993�N�\�Z�E�E�E���z5000���h���̍����Ԏ��팸�̂��߁A���̌�5�N�Ԃɂ킽���ďĂ�2500���h���̐��{�x�o�팸��2500���h���̑��ł��s�����Ƃ���e�Ɋ܂ނ��́B�v
�@�����팸�Ƒ��ŁE�E�E�E�����v��������
�@�����A�u�ؓ���ɂ���������v�̌����i�����ď������ؓ���͌�������ł��낤�Ƃ����\�z�j�́A���q����ቺ�����A�����ė��q���̒ቺ�͓������h�������B�����������������̌��ʂ́A�����v�Ȑ����E���V�t�g�����邱�ƂɂȂ����B���̌��ʁA�o�ς͉Ɍ������A�����A2�N�Ԃɓn����500���l�ȏ�̌ٗp���n�o���ꂽ�v�ƁB
�@�u�b�V�������̘p�ݐ푈�Ƃ��̌�̌i�C���
�@����ɂ������閯���哱�̌o�ω�
�@����̌��1990�N��̌R���\�Z�팸�Ȃǂ̉\�����J�E���g�ɓ����K�v�B
p.200-201
�u���̃G�s�\�[�h�ƁA�O�q�̃��[�K�����������ɋN�������G�s�\�[�h�ɂ����āA�����̃P�[�X�ŁA���q���̌��ʂ͍�������̌��ʂ𗽉킵�Ă���B���[�K���������̃P�[�X�ł́A�������g���I�ł������ɂ�������炸�A�����q�����i�C��ނ������炵���B����N�����g���������̃P�[�X�ł́A��������ُ͋k�I�ł������ɂ�������炸�A�ᗘ�q�����o�ς��������v�ƁB
p.201���{��`�I�s��o�σV�X�e���̕K�R�I���ʂƂ��āA�o�σf�[�^���s�m���ł��邱�ƂɊւ���ʔ��������F��
�u�������Ď҂́A���������ʂ��鐅�����������Ă��Ȃ������łȂ��A�����̌o�ς��ǂ̂悤�ȏ�Ԃɂ���̂��A�܂�����̌o�ς��ǂ̂����ȏ�Ԃɂ������̂������A���m�ɂ͂킩��Ȃ��̂ł���B�o�ς̋����𑪒肷��M���ł���f�[�^���쐬����ɂ͎��Ԃ�������B�A�����J�ł����Ƃ��v���ɍ쐬�����̂͌ٗp�f�[�^�ł��邪�A�����̌ٗp�f�[�^�͓�����2�T�Ɏ��W����A������1�T�ɔ��\�����B���̏d�v�Ȍo�σf�[�^�͍쐬�����̂ɐ��T�Ԃ�����B�����ăf�[�^���ŏ��ɗ��p�\�ɂȂ������_�ł́A�����͎b��I�Ȃ��̂ł���A����傫�ȏC�����Ȃ���邱�Ƃ�����B
�@1991�N�ɔ��\���ꂽ�Y�o�ʃf�[�^�ɂ́A�i�C�̉����͔��Ɋɂ₩�ł��邱�Ƃ�������Ă����B������4�N�ȏ���o��1995�N1���ɔ��\���ꂽ����f�[�^�ł́A�P�X�X�P�N�̌i�C���~�͈ȑO�l�����Ă��������͂邩�ɐ[���Ȃ��̂ł��������Ƃ������Ă����B�E�E�E�i�����ǂ����v���ɒ����f�[�^�����肳��������A�������Ď҂����ǂ����Ɋ�Â������������悢�^�C�~���O�ōs�������Ŗ��ɗ����낤�v�B
p.207
��T�� �����vAggregate Demand
��S�́u�s���S�ٗp�v�ł́A�u���Ƃ̂����Ȍ����́A�J�����v�Ȑ����V�t�g�����ɂ�������炸����ɑ�������悤�Ȏ��������̉�����Ȃ����Ƃɂ���Ƃ������Ƃ��w�v�Ƃ����B�J��Ԃ��A�ᔻ�I�ɃR�����g�������A����́A���̃C�f�I���M�[�Ƃ����ׂ��ł���B������Ƃ����o�ό��ۂ̐����Ƃ͂����Ȃ��B
�@�u���������v����������A���Ƃ͋N���Ȃ����̂��Ƃ��ɁA���Ɩ����u���������v�̖��ɂ��Ă���B����ׂ��o�ϊw�B���ꂪ�m�[�x���܂̌o�ϊw���H
�@�������A���̏d�v�ȗv���������Ƃ��Ă͂��Ȃ��B
�@���Ȃ킿�A�u�܂��A�J�����v�Ȑ��̃V�t�g�̂����Ȍ����͑��Y�o�ʂ̌����ł��邱�Ƃ��w�v�ƁB
�@�����A�Ȃ��A���Y�o�ʂ́u�����v����̂��H�@�����Y�o�ʂ̊g��A�c���A���Ō����Ƃ����i�C�z���K�肷����̂͂Ȃɂ��H�@