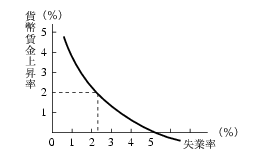[1] 1���������܂蒷���Ȃ����̂ŁA�����B�t�@�C���P�Ƒ�5�͖`�������͏d��
[2] �����ɂ��̋c�_���x�z�I�ȍl�����Ƃ��ė��z���Ă��邩�́A���Ƃ���90�N��̒����s���̌������c�_���钆�ł���v�ȍl�����̂ЂƂƂ��ďo�Ă��邱�Ƃ���A�킩��B�����s��(�������)�̌����Ƃ��āA���v���v���A�������v���̓������Ƃ��A�u���v���̗͓_�̈�ł�������̉����d�����v���w�E�����B�{��w�u�P�́@���{�o�ς̒�����Ƌ����T�C�h�v�l�c�G��E�x�����`�E���t�{�o�ώЉ���������ҁw�_���@���{�̌o�ϊ�@�|������̐^�����𖾂���|�x���{�o�ϐV���ЁA2004�N5�����Ap.5.
������̍d������́A�X�e�B�O���b�c���}�N���o�ϊw�ʼn����Ă��邭�炢������A�A�����J�ɂ��A�����i���{��`���ɋ��ʂ̂��Ƃ��낤(EU�����ł͂����Ƌ����d���������邾�낤)�B������A���{�́A������90�N��̒���������A�A�����J��EU�����ɂ����ʂ̗v���ł͉����Ȃ����Ƃ́A�_���I�ɂ������̏�ł��A���炩�ł͂Ȃ����낤���H
�@�{��̎咣�͂͂����肵�Ă���B�u�{��(2003)���w�E�����悤�ɁA�Y�ƕʂɎ��������Ɛ��Y���㏸�̓���������ƁA�܂���Bruno and Sachs[1985]���A1980�N��̃A�����J�o�ςŎw�E�������������̍d�������A���{�o�ς̒���������炵�Ă���̂ł���B���������̓����Y���㏸�Ɍ������������ւƐL�k�I�ɕω�������ƂƂ��ɁA�]���ȏ�ɘJ���͂̎Y�ƊԈړ��𑣂�������Ƃ�K�v�������v�ƁB�ip.20�j
���͂��������āA�u���Y���㏸�v�̏�����̔����E�n���ł���A���������V��������ւ̘J���͂̈ړ��Ȃ̂ł���B����ɁA�u�����̉����d�����v�������炤�ׂ��ł͂Ȃ��̂ł���B
�@�����āA�J���͂��V��������Ɉړ�����ɂ́A�J���͂��_��������Č`������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ȋw�Z�p�̐i�W�ɏ_��ɑΉ��ł���J���͂̌`���A�ċ��炪�K�v���낤�B�u�V�����Z�p�v�V�Ƃ����w�i�Ƃ����Y�Ƃ̖u�����K�v�v(p.23)�Ƃ����̂́A���̂Ƃ���ł��낤�B�������A�������͕��ՓI�����ł�����B
�Ȃ��A���{�ɂ�����1990�N��ɂ��ꂪ�ł��Ȃ������̂���������邽�߂ɂ́A�u�Ȃ��A1990�N��ɐV�����Z�p�v�V�Ƃ����w�i�Ƃ����Y�Ƃ̖u���v���ł��Ȃ������̂����𖾂��Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B
�@���̓_�A�����Q�̖͂�����u���{�o�ς̒�����͍\����肪�������|�Y�ƍ\�������s�ǐ��̔ᔻ�I�����v���������Ă���B
�@����ɂ��A�u�Y�ƍ\�������s�ǐ��Ƃ́A���{�o�ς̒�̎�����A�ᐶ�Y���Y�Ƃ��獂���Y���Y�Ƃւ̃V�t�g���\���ɐi��ł��Ȃ��ƌ����_�ɋ��߂錩���v�ł��邪�A�����ɂ́A�u���Y���̐L�т̒Ⴂ�Y�Ƃ��獂���Y�Ƃւ̐��Y�����̃V�t�g�v�́A�K�R�ł��K�v�ł��Ȃ��A�Ɓip.34�j�B�u�Y�Ƃ��Ƃ̐��Y���㏸�Ɋi�������݂���ꍇ�ɂ́A�����܂�ȃP�[�X�������A�ނ���A�����Y���Y�Ƃ���ᐶ�Y���Y�Ƃւ̃V�t�g��������ԂȂ̂ł���B�����āA�����ɐ����Ă���̂͂܂��ɂ���ł���v�Ƃ��āA���{�ɂ����鐻���Ƃ���уT�[�r�X�Ƃ̍������Y�V�F�A�̐���(1980�|2000�N)�̓��v�E�}�\���f���Ă���B������Y����̐����Ƃ̍������Y�V�F�A���X���I�ɒቺ���A�u�ᐶ�Y���v�̃T�[�r�X�Ƃ̍������Y�V�F�A���P��I�ɁA����90�N����ނ��돇���ɏ㏸���Ă���A�Ƃ����킯�ł���(p.38-39)�B
�����A����̎����f�[�^�́A�u�������Y�V�F�A�v�A���Ȃ킿�A�������Y�̑S�̂�100�p�[�Z���g�Ƃ����ꍇ�ɁA�����ƂƃT�[�r�X�Ƃ���߂銄���̕ω��ł���A�����ƂƃT�[�r�X�Ƃ̐��Y�z�̐�ΓI�ȕω��������f�[�^�ł͂Ȃ��B
�@���������āA���̂悤�Ɍ����Ƃ��A�����ɂ�(�����Ȃ��Ƃ������Ă���f�[�^�Ƃ̊W�ł�)�A�u�����Y���Y�Ƃł��鐻���Ƃ̏k���ƒᐶ�Y���Y�Ƃł���T�[�r�X�Ƃ̊g��v�Ƃ����̂́A��ΓI�Ȑ��Y�ʂ�Y�z�Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ����Ƃ͒��ӂ���K�v������B�u�����Y���Y�Ɓv�ł��鐻���Ƃ́A���v��A��Ίz�ł͑��債�i�i�C�ϓ��ł̕ϓ����o���������j�Ă���B�X���I�Ɍ������Ă���Ƃ͂����Ȃ��ł��낤�BEx.�@�l��Ɠ��v(�����ƁE�T�[�r�X��) �@�u�����Y���Y�Ƃ���ᐶ�Y���Y�Ƃւ̃V�t�g�v���A������ɢ��ԣ�ł���Ƃ͂����Ȃ��ł��낤�B
�@����͂����Ƃ��āA�d�v�Ȃ̂́A��o�ό����̊ϓ_����̎����̍œK�z���́A�ʏ�͂ނ���A���Y���̍������삩��Ⴂ����ɘJ�����ړ����邱�Ƃɂ���ĒB������飂Ƃ������Ƃ̈Ӗ������ł���A�u���́A�ᐶ�Y���Y�Ƃ��k�����Ă����Ȃ��Ƃ����Ƃ���ɂ���̂ł͂Ȃ��A�ᐶ�Y���Y�Ƃ��ᐶ�Y���̂܂܂łƂǂ܂��Ă���Ƃ����Ƃ���ɂ���v�Ƃ����̂́A�Ó��Ȍ����ł��낤�B�����A���̈Ӗ������Ƃ��ẮA��ᐶ�Y���Y�ƣ�̐��Y�����㏸���A������Y�����B�����A���̈Ӗ��œ��Y��ᐶ�Y���Y�ƣ�̊���������Ƃ������ƂƂ͖������Ȃ��ł��낤�B�����Ȃ镪��ɂ����Ă����Y���͂̏㏸�́A���ՓI�X���ł��낤�B
�@���̈Ӗ��ŁA�u�ᐶ�Y���Y�Ƃ̐��Y�����㏸���Ă����A���̍��̐��Y�ɂ�葽���̎����𓊓�����K�v�͂Ȃ��Ȃ�B�܂�A�t���I�ł��邪�A�����ᐶ�Y���Y�Ƃ��k����������@������Ƃ���A����͂��̎Y�Ƃ����w�����Y���x�ɂ��邱�Ƃɂ���ĂȂ̂ł���v��(p.41)�B
[3] ���Ɨ��ƒ����㏸���Ƃ̊֘A�Ɋւ��ẮA�L���ȁu�t�B���v�X�Ȑ��v������B
���Ɨ��̍������A�����}��������艺�����͂Ƃ��ē������Ƃ́A�e�Ղɗ����ł���B����͂�����ߑ�o�ϊw�����۔F���Ƃ��Ă͔c�����Ă���B
�}���N�X�̏ꍇ�A����͎��{�~�ς̕K�R�I���J�j�Y�����Ƃ���B���ΓI�ߏ�l���E�Y�Ɨ\���R�̗��_�́A���{(���̘_���Ɖ^���@�����炷���)���A�K�R�I�ɂ��̂悤�Ȏ��Ǝ҂ݏo���ƌ���B
�L��t�E�o�ώ��T����t�B���v�X�Ȑ��̐��������Ă������B
|
�t�B���b�v�X�Ȑ� Phillips curve |
|||
|
|||
|
|
�ŋ߂̃��[���b�p�����ł́A���Ɨ���10������Ƃ���������B
�����̒n��ł́A�t�B���v�X�Ȑ������̂܂ܓK�p����A�u�ݕ������㏸�����}�C�i�X�ɂȂ�v�Ƃ������ƂɂȂ邪�A�ʂ����Č����͂ǂ����H
�@����Ɨ���̑O��ƂȂ�J���҂̕��ϓI�ȘJ������(1��������J�����ԁA1�T�ԓ�����J�����ԁA�N�ԘJ�����ԂȂ�)�́A�ǂ̂悤�ɂȂ��Ă��邩�A���ꂪ���ƂȂ�B
�@�l�ނ̘J���̐��Y�͂��㏸����A���R�Ȏ��ԁA�]�ɂ̎��Ԃ𑝂₷�Ƃ����������ŁA�l�ԓI�ȘJ�����ԊǗ��𐄐i����\�����łĂ���B���̂悤�Ȍ`�ŁA���Ɨ��������Ȃ��悤�ȓw�͂��A��i�����ɂ����ċ��߂��Ă���B
�@���[�N�V�F�A�����O�_�̔��W���K�v�ł��낤�B
�o�ώj�u�`�C���f�b�N�X�̃y�[�W�ɂ��Љ�Ă��������A�l�Ԃ̎��R���J�������̊W�Ɋւ��鎟�̎w�E���A����x���ݒ��߂����B
�u���������A���R�̍��́A���R��O�I�ȍ��ړI�����������J������Ƃ������Ƃ��Ȃ��Ȃ����Ƃ��ɂ͂��߂āA�n�܂�̂ł���B�܂�A����́A���R�̂��ƂƂ��āA�{���̕����I���Y�̗̈�̂��Ȃ��ɂ���̂ł���B
Das Reich der Freiheit beginnt in der Tat erst da, wo das
Arbeiten, das durch Not und äußere Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört; es liegt also der Natur
der Sache nach jenseits der Sphäre der eigentlichen materiellen Produktion.
���J�l�́A�����̗~�]���[�������߂ɁA�����̐������ێ����Đ��Y���邽�߂ɁA���R�Ɗi�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�����悤�������l���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���A�������ǂ�ȎЉ�`�Ԃ̂Ȃ��ł��A�l�����邩����̂ǂ�Ȑ��Y�l���̂Ȃ��ł��A�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B
Wie der Wilde mit der Natur ringen
muß, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, um sein Leben zu erhalten und zu
reproduzieren, so muß es der Zivilisierte,
und er muß es in allen Gesellschaftsformen und unter allen möglichen
Produktionsweisen.
�ނ̔��W�ɂ�āA�������R�K�R���̍��͊g�傳���B�Ƃ����̂��~�]���g������邩��ł���B�������܂������ɁA���̗~�]���[�������Y�����܂��g�傳���B
Mit seiner Entwicklung erweitert sich dies Reich der Naturnotwendigkeit, weil die
Bedürfnisse; aber zugleich erweitern sich die
Produktivkräfte, die diese befriedigen.
���R�����̗̈�̂Ȃ��ł��������̂��Ƃɂ��肤�邾���ł���B���Ȃ킿�A�Љ���ꂽ�l�ԁA�������ꂽ���Y�҂������A�ӖړI�ȗ͂ɂ���Ďx�z�����悤�Ɏ��������Ǝ��R�Ƃ̕�����ӂɂ���Ďx�z����邱�Ƃ���߂��A���̕�����ӂ������I�ɋK�������������̋����I�����̂��Ƃɂ����Ƃ������ƁA�܂��͂̍ŏ��̏����ɂ���āA���������̐l�Ԑ��ɍł��ӂ��킵���ł��K�����������̂��ƂŁA���̕�����ӂ��s���Ƃ������Ƃł���B
Die Freiheit in diesem Gebiet kann
nur darin bestehn, daß der vergesellschaftete Mensch,
die assoziierten Produzenten, diesen ihren Stoffwechsel mit der
Natur rationell regeln, unter ihre
gemeinschaftliche Kontrolle bringen, statt von ihm als von einer blinden Macht beherrscht zu
werden; ihn mit dem geringsten
Kraftaufwand und unter den ihrer
menschlichen Natur würdigsten und adäquatesten Bedingungen
vollziehn.
�������A����͂�͂�܂��K�R���̍��ł���B
���̍��̂��Ȃ��ŁA���ȖړI�Ƃ��ĔF�߂���l�Ԃ̗͂̔��W���A�^�̎��R�̍����n�܂�̂ł��邪�A�������A����͂����A�����K�R���̍������̊�b�Ƃ��āA���̏�ɂ̂݉Ԃ��J�����Ƃ��ł���̂ł���B
Aber es bleibt dies immer ein Reich der
Notwendigkeit.
Jenseits desselben beginnt die menschliche Kraftentwicklung, die sich als Selbstzweck
gilt, das wahre Reich der
Freiheit, das aber nur auf jenem Reich der Notwendigkeit
als seiner Basis aufblühn kann.
�J�����̒Z�k�����͍��{�����ł���B
Die Verkürzung des
Arbeitstags ist die Grundbedingung.
[Marx: Das Kapital, S. 4073 ff. Digitale
Bibliothek Band 11: Marx/Engels, S. 7387 (vgl. MEW Bd. 25, S. 826 ff.)]�M��E�匎���X�ŁE�w���{�_�x��3���A��5�����A1050-1051�y�[�W�B
�W���J�����ȂǘJ���҂̕W���I�J�������m���E����E�@�I�����́A�J����(���̓I�E���_�I�J���ҁ����ݎЉ�̈��|�I�����̋ΘJ����l�X)�̎�̓I�A�эs���ɂ��
[4] �J���_�����ƂȂ�B
�@�}���N�X�����炩�ɂ���悤�ɁA�J���͘J���͂̑Ή��ł���ɂ�������炸�A�J���̑Ή��ƊϔO����Ă���B���̌�����ϔO�́A�����ł͗�������Ȃ����Ƃɂ��A�������E�\�͋��Ƃ����\���ŘJ������������Ă��邱�Ƃ�����킩��悤�ɁA�����l�̔\�͂ɉ��������̕K�v�ɉ������z�i���̔\�͂��ێ����������ێ����邽�߂̑���p�j���A�J�����Ƃ������ƂɂȂ�B�@
�@�ΘJ����l�Ԃ̐����̕K�v��\�͈ێ��̂��߂ɕK�v�Ȕ�p���A���������ɒ��ڂ������̂Ȃ��o�ϑS�̂̐��Y�\�͂Ǝs��\�͂Ƃ̑��݊W�̕ϓ��ɂ���Đ�����i�C�z��2�|3�N���Ƃ̕ϓ��ɑΉ����Ȃ��̂́A�K�R�ł���B
�@�J���҂̐����E�\�͈ێ��̏���p�́A���̂��߂̏����i�̉��i�ɑΉ����A���������Ă������������i���̂��A���Y���͂̔��B�ɂ���Ēቺ���邩����ŁA�ቺ����B�J���҂̕K�v�������������ȒP�ɒቺ���Ȃ��̂́A����珔�����̉��i���ȒP�ɂ͒ቺ���Ȃ����Ƃ̔��f�ł����Ȃ��B
�@���ΓI��]���l�_(��1����l���A�掵��)�̗��������߂���B
[5] �������A��ʓI�ȎЉ�̔��W�ɔ����J���҂̘J�����Ԃ̒Z�k�Ɨ]�ɂ̑����Ƃ��������ł́A���펞�ɂ����鐳�K�J���҂̋ΘJ���Ԃ̒Z�k�����A���E�I�ɒB������Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B
[6] �ʔ������ƂɁA�O���f�Ղ��o�Ă���ƁA�͂�����ƁA���Ƃ��̉��l�Ƃ������i�̂Q����(�g�p���l�E���p�Ɖ��l�E�������l)�����m�Ɉӎ����ꂽ�\���ɂȂ�B
�@����ɂ����閳���̎g�p���l�E�����̑��l�Ȍ��p���������A�o�����ݕ��z(�������l�E���l)�ɊҌ�����A�����Ŗ����̗A�����̉ݕ��z(�������l�E���l)���Βu����A�������������B
�@���l�E�������l�������Ƃ������Ƃ͕s��ɕt�����܂܂ŁA���ۂ̌o�ϗ����ł́A�u���l�v���g�p���Ă���̂ł���B
�@�����A���l�Ƃ͉����H�@�����̎g�p���l�E���p�Ƃ͈�������l�Ƃ͉����A��`����B���ꂪ�A������ߑ�o�ϊw�ɓ˂�����ꂽ���ł���B
�@�����A������ߑ�o�ϊw�͂��̍��{����������Ă���B
�@�@���J�[�h�́H
�@�@�}���N�X�́H
[7] �����F�A�����J�ł́A1980�N��㔼�̏���́A�������ƌv������97�����߂Ă����B
�@�ŋ߂ł́A����͂����炩�ቺ�����B�����������v���A����̉��������ɂ����������ϔ䗦�������Ă���̂ɂ������āA���E������͂�����������炩�������Ȃ��Ă����B
[9] �w���{�_�x����ΏۂƂ���̂��A���{�̗��ʉߒ��B��`�����ȉ��ɔ������Ă������B
�@�u���{�̏z�ߒ��͎O�̒i�K��ʂ��Đi�݁A�����̒i�K�́A��ꊪ�̏��q�ɂ��A���̂悤�ȏ������Ȃ��Ă���B
Der Kreislaufsprozeß des
Kapitals geht vor sich in drei Stadien, welche, nach der Darstellung des ersten
Bandes, folgende Reihe bilden:
�@���i�K�B���{��[9]�͏��i�s���J���s��ɔ�����Ƃ��Č�����B�ނ̉ݕ��͏��i�ɓ]�������B���Ȃ킿�A���ʍs��G�|W��ʉ߂���B
Erstes Stadium: Der
Kapitalist erscheint auf dem Warenmarkt und Arbeitsmarkt als Käufer; sein Geld
wird in Ware umgesetzt oder macht den Zirkulationsakt G - W durch.
�@���i�K�B����ꂽ���i�̎��{�Ƃɂ�鐶�Y�I�����B�ނ͎��{�ƓI���i���Y�҂Ƃ��čs������B�ނ̎��{�͐��Y�ߒ���ʉ߂���B���̌��ʂ́A���ꎩ�g�̐��Y�v�f�̉��l�����傫�����l�������i�ł���B�@
Zweites Stadium: Produktive
Konsumtion der gekauften Waren durch den Kapitalisten. Er wirkt als
kapitalistischer Warenproduzent; sein Kapital macht den Produktionsprozeß
durch. Das Resultat ist: Ware von mehr Wert als dem ihrer Produktionselemente.
�@��O�i�K�B���{�Ƃ͔����Ƃ��Ďs��ɋA���Ă���B�ނ̏��i�͉ݕ��ɓ]�������B���Ȃ킿���ʍs��W�|G��ʉ߂���B
Drittes Stadium: Der
Kapitalist kehrt zum Markt zurück als Verkäufer; seine Ware wird in Geld
umgesetzt oder macht den Zirkulationsakt W - G durch.
�@�����ŁA�ݕ����{�̏z��\�킷�莮�͎��̂悤�ɂȂ�BG - W... P... W' - G'�B�����œ_���́A���ʉߒ������f����Ă��邱�Ƃ������AW�f��G�f�́A��]���l�ɂ���đ��債��W��G�Ƃ�\�킵�Ă���B
Die Formel für den
Kreislauf des Geldkapitals ist also:
G - W... P... W' - G', wo
die Punkte andeuten, daß der Zirkulationsprozeß unterbrochen ist, und W' wie G'
ein durch Mehrwert vermehrtes W und G bezeichnen.
�@���i�K�Ƒ�O�i�K�́A��ꕔ�ł́A�������i�K���Ȃ킿���{�̐��Y�ߒ��𗝉����邽�߂ɕK�v�Ȃ�����Ř_�����ꂽ�����������B������A���{�������̒ʂ邢�낢��̒i�K�Őg�ɂ���Ƃ���́A�����ČJ��Ԃ����z�̒��Őg�ɂ�����E���̂Ă��肷��Ƃ���́A���낢��Ȍ`�Ԃ́A�ڗ�����Ă͂��Ȃ������B���ꂩ��́A����珔�`�Ԃ��܂����̌����ΏۂɂȂ�̂ł���B
Das erste und dritte Stadium wurden im ersten Buch
nur erörtert, soweit dies nötig für das Verständnis des zweiten Stadiums, den
Produktionsprozeß des Kapitals. Die verschiednen Formen, worin das Kapital in seinen
verschiednen Stadien sich kleidet, und die es bei wiederholtem Kreislauf bald
annimmt, bald abstreift, blieben daher unberücksichtigt. Sie bilden jetzt den
nächsten Gegenstand der Untersuchung.
�����̌`�Ԃ������ɔc�����邽�߂ɂ́A����������́A�`�ԓ]�����̂��̂ɂ��`�Ԍ`�����̂��̂ɂ����̊W���Ȃ��_�@�����ׂĎ̏ۂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����䂦�A�����ł́A���i�͑����l�ǂ���ɔ�����Ƃ������Ƃ��z�肳��邾���ł͂Ȃ��A���̔��肪�s�ς̎���̂��Ƃōs����Ƃ������Ƃ��z�肳���̂ł���B���������Ă܂��A�z�ߒ��ŋN���邱�Ƃ����肤�鉿�l�ϓ������������̂ł���B
Um die Formen rein
aufzufassen, ist zunächst von allen Momenten zu abstrahieren, die mit dem
Formwechsel und der Formbildung als solchen nichts zu tun haben. Daher wird
hier angenommen, nicht nur, daß die Waren zu ihren Werten verkauft werden,
sondern auch, daß dies unter gleichbleibenden Umständen geschieht. Es wird also
auch abgesehn von den Wertveränderungen, die während des Kreislaufsprozesses
eintreten können.
[Marx: Das
Kapital, S. 1638 ff. Digitale Bibliothek Band 11: Marx/Engels, S. 4952 (vgl.
MEW Bd. 24, S. 31 ff.)]
[10] �}���N�X�́A���{����(�ݕ����{�̓���)�́AG=A+Pm�ƂȂ�Ƃ���B���Ȃ킿�AA=�J����(�J��)�ɓ������鎑�{�����Ɛ��Y��iPm�ɓ������鎑�{�����Ƃł���B�������A���̊����́A�������Ĝ��ӓI�ɂł���킯�ł͂Ȃ��B��������Y�ƕ���̎��{�̗L�@�I�\���ɂ���āA��̓I�v��(�J���́E�J���Ґ�)�Ɛ��Y��i(�@�B�E�������̑�)�Ƃ͂�����̋Z�p�I�䗦���Ȃ��A�܂�����ɑΉ����Ă��̉��l(���i)�\������芄���ƂȂ�B
�@�������������̓����̋�̓I��������āA��ʓI�Ȣ�������Ă͂߂Ă��܂����Ƃ͖��ł��낤�B
�@
[11] �v���C�X�́A�������琶���鐔�̋��傳�ɂ���āA�ȒP�Ɍ��f����Ă��܂����B�ނ́A�Đ��Y�ƘJ���Ƃ̏��������ڗ����邱�ƂȂ��A���{���A�����̂Ƃ��āA��̒P�Ȃ鎩�ȑ��B���Ƃ��Č����̂Łi�}���T�X���l�Ԃ��A���̊����I�����ɂ����Č����̂Ƃ܂��������l�Ɂj�A���{�̑���̖@����s��c(1�{z)n �Ȃ�莮�ɂ����Ĕ����������ϑz�������̂ł���B����s�͎��{�v���X�����̍��v�Ac�͑O�ݎ��{�Az�͗��q��(100�̉������ŕ\�����ꂽ����)�An(��) �͉ߒ��̍s����N���ł���B
Price wurde einfach
geblendet durch die Ungeheuerlichkeit der Zahl, die aus geometrischer Progression entsteht. Da er das Kapital,
ohne Rücksicht auf die Bedingungen der Reproduktion und der
Arbeit, als selbsttätigen Automaten betrachtete, als eine bloße,
sich selbst vermehrende Zahl (ganz wie Malthus den
Menschen in seiner geometrischen Progression), konnte er wähnen, das
Gesetz seines Wachstums gefunden zu haben in der Formel s = c (1 + z)n, wo s =
Summe von Kapital + Zinseszins, c = dem vorgeschoßnen Kapital, z = dem Zinsfuß
(in aliquoten Teilen von 100 ausgedrückt) und n die Reihe der Jahre, worin der
Prozeß vorgeht.
[12] �u���{�Ƃ́A�i�v�ɑ����������đ��傷�鉿�l�Ƃ��Ă��̐����̑����ɂ���ā\���Ȃ킿�X�R���N�w�҂̌����B�ꂽ�����ɂ���ā\�A���Ȏ��g���Đ��Y���A�����čĐ��Y�ɂ����Ď��ȂB���鉿�l�ł���A�Ƃ����ϔO�́A�B���p�t�����̋�z�������y�Ȃ��h�N�^�[�E�v���C�X�̊�z�V�O�Ȏv�����Ɏ��炵�߂��B���Ȃ킿�A���́A�s�b�g���{�C�ɂ����M���āA�����p����Ɋւ���ނ̏��@���ɂ����āA�ނ̍����̎x���ƂȂ����v�����ł���B
�@�@�@�@�g�������Y�މݕ��͏��߂͏��X�ɑ��傷��B�������A���嗦�͐₦�����������̂ŁA������Ԃ̌�ɂ́A�z����₷�鑬���ɂȂ�B�L���X�g���a�̔N��5���̕����ő݂��o���ꂽ1�y�j�[�́A�����ł͂��łɁA���ׂď�������Ȃ�1��5000���̒n���Ɋ܂܂�Ă�������A�����Ƒ傫�Ȋz�ɑ��債�Ă���ł��낤�B�������A�P���ő݂��o���ꂽ�Ƃ���A�������Ԃ�7�V�����O4�y���X���ɂ����A���債�Ȃ��ł��낤�B�����܂ł킪���{�́A���̓��������̓��ɂ���āA���̍��������P���悤�Ƃ��Ă����̂ł���B�h�i�����j
(����)���`���[�h�E�v���C�X�w�����ɂ��Č��O�ɑi����x�����h���A1772�N�A19�y�[�W�B�ނ́A�c�t�Ȍx���f���Ă���B�u���˂́A�P���Ŏ�āA�����ŐB�₹�v�iR�E�n�~���g���w��u���e���̍��̔����Ɣ��B�Ɋւ��錤���x��2�ŁA�G�f�B���o���A1814�N�A��O����P�Ѣ�h�N�^�[�E�v���C�X�̍����ς̋ᖡ��P�R�R�y�[�W�j
�@�@�@�@����ɂ��A��ʂɎ؋��́A���l�ɂƂ��čł��m���Ȓv�x��i�ł���Ƃ������ƂɂȂ�ł��낤�B�������A���Ƃ��Ύ����P�O�O�|���h���N���T���Ŏ��Ƃ���A���͔N���ɂ͂T�|���h���x����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����āA���ɂ��̑O�݂����ꉭ�N�ԑ����Ƃ��Ă��A���̊Ԏ��͖��N�˂ɂ����P�O�O�|���h������݂��˂Ȃ炸�A���l�ɖ��N�T�|���h���x����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̎葱�ɂ���ẮA���܂ł����Ă��A�����P�O�O�|���h����邱�Ƃɂ���āA�P�O�T�|���h��݂��悤�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B
�@�@�@�@�����āA���͉����炱�̂T�����x�����悢�̂��H�V�����؋��ɂ���Ăł���B�܂��́A�������Ƃł���A�d���ɂ���Ăł���B
�@�@�@�@�������A�Y�Ǝ��{�����ݕ������Ƃ���A�ނ́A�����������P�T���Ƃ���A�T���𗘎q�Ƃ��Ďx�����A�T��������(������p���A�ނ��×~�͔ނ̎����ƂƂ��ɑ����͂��邪)�A�T�������{�����˂Ȃ�Ȃ��B���������āA�������T���̗��q���x�������߂ɂ��A���ł��P�T���̗������O������Ă���B���̉��肪�����Ƃ���A�������́A���q�̗��R�ɂ���āi���{�̗L�@�I�\���̍��x���A�������̈�ʓI�@���Ƃ��Ă̒ቺ�X���E�E�E���p�ҁj�A���Ƃ��P�T������P�O���ɒቺ����B
�@�@�@�@������ɁA�v���C�X�́A�T���̗��q���P�T���̗�������O�����Ƃ�Y��Ă��܂��A�����āA���̗����������{�̒~�ςƂƂ��ɉi��������B�ނƂ��ẮA���������̒~�ωߒ��ɌW���K�v�͂Ȃ��A�����A�����������Ċҗ�����悤�ɁA�ݕ���݂���������悢�̂ł���B�ݕ����ǂ����ĕ����җ����n�߂邩�́A�ނɂƂ��Ă��܂������ǂ��ł��悢�B����͂��ɗ��q�t���{�̐����̎���������ł���B
�@�@�@�@�i�}���N�X�w���{�_�x��R����Q�S�́@���q�t���{�̌`�Ԃɂ����鎑�{�W�̊O�݉��A��g���ɔ�(�V)�A�P�O�O�|�P�O�P�y�[�W�j
Die Vorstellung vom
Kapital als sich selbst reproduzierendem und in der Reproduktion vermehrendem
Wert, kraft seiner eingebornen Eigenschaft als ewig währender und wachsender
Wert - also kraft der verborgnen Qualität der Scholastiker -, hat zu den
fabelhaften Einfällen des Dr. Price geleitet, die bei weitem die Phantasien der
Alchimisten hinter sich lassen; Einfällen, an die Pitt ernsthaft glaubte und
die er in seinen Gesetzen über den sinking fund zu Säulen seiner
Finanzwirtschaft machte.
„Geld, das Zinseszinsen trägt, wächst anfangs
langsam; da aber die Rate des Wachstums sich fortwährend beschleunigt, wird sie
nach einiger Zeit so rasch, daß sie jeder Einbildung spottet. Ein Penny,
ausgeliehen bei der Geburt unsers Erlösers auf Zinseszinsen zu 5%, würde schon
jetzt zu einer größren Summe herangewachsen sein, als enthalten wäre in 150
Millionen Erden, alle von gediegnem Gold. Aber ausgelegt auf einfache Zinsen,
würde er in derselben Zeit nur angewachsen sein auf 7 sh. 4 1/2 d. Bis jetzt
hat unsre Regierung vorgezogen, ihre Finanzen auf diesem letzteren, statt auf
dem ersteren Weg zu verbessern.�g81
[Marx: Das Kapital, S. 3302 ff. Digitale
Bibliothek Band 11: Marx/Engels, S. 6616 (vgl. MEW Bd. 25, S. 407 ff.)]
����81
Richard Price, „An Appeal to the Public on the subjeet of the National Debt�h,
London 1772, [p. 19]. Er
macht den naiven Witz: „Man muß Geld borgen zu einfachen Zinsen, um es auf
Zinzeszinsen zu vermehren.�g (R. Hamilton, �gAn Inquiry
into the Rise and Progress of the National Debt of Great Britain�h, 2nd ed.,
Edinburgh 1814 [P. 133].)
Darnach wäre Pumpen
überhaupt das sicherste Mittel der Bereicherung auch für Private. Aber wenn ich
z.B. 100 Pfd. St. zu 5% jährlichem Zins aufnehme, habe ich Ende des Jahrs 5
Pfd. St. zu zahlen, und gesetzt, dieser Vorschuß daure 100 Millionen Jahre, so
habe ich in der Zwischenzelt in jedem Jahr immer nur 100 Pfd. St. auszuleihen
und ebenso in jedem Jahre 5 Pfd. St. zu zahlen. Ich komme durch diesen Prozeß
nie dazu, 105 Pfd. St. auszuleihen, dadurch, daß ich 100 Pfd. St. aufnehme.
Und wovon soll ich die 5%
zahlen? Durch neue Anleihen, oder wenn
ich der Staat bin, durch Steuern.
Nimmt aber der
industrielle Kapitalist Geld auf, so hat er bei einem Profit von
sage 15%, 5% zu zahlen als Zins, 5% zu verzehren (obgleich sein Appetit wächst
mit seiner Einnahme) und 5% zu kapitalisieren. Es sind also schon 15% Profit vorausgesetzt, um beständig 5% Zins
zu zahlen. Dauert der Prozeß fort, so fällt die Profitrate aus den schon
entwickelten Gründen, sage von 15% auf 10%.
Aber Price vergißt ganz, daß
der Zins von 5% eine Profitrate von 15% voraussetzt,
und läßt diese mit der Akkumulation des Kapitals fortdauern. Er hat überhaupt
nichts mit dem wirklichen Akkumulationsprozeß zu tun,
sondern nur Geld auszuleihen, damit es mit Zinseszinsen zurückfließe. Wie es
das anfängt, ist ihm ganz gleichgältig, da dies ja die eingeborne Qualität des
zinstragenden Kapitals ist.
[Marx: Das Kapital, S. 4269
ff. Digitale Bibliothek Band 11: Marx/Engels, S. 7583 (vgl. MEW Bd. 25, S. 0
ff.)]